
中国の兵士が猿の子供を捕まえ、船へ連れてきました。
母猿は泣き叫びながら、岸沿いに船を追いかけてきます。
数十キロ走ったところで船が岸に着くと、母猿は船に飛び乗ってきますが、すぐに死んでしまいました。
母猿のお腹を裂いて見ると、腸がズタズタに切れていたそうです。
子猿を奪われた悲しみがあまりにも深かったため、母猿の腸はズタズタに切れてしまいました。
このことから、「非常につらく悲しい気持ち」という意味で【断腸の思い】という言葉が使われるようになりました。
由来・語源のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。


知りたい項目をクリックして下さい。
| ①意味・読み方 |
| ②由来・語源 |
| ③ 「断腸」漢文の現代語訳・書き下し文 |
| ④例文・使い方 |
| ⑤類語・言い換え |
| ⑥反対語・対義語 |
| ⑦英語表現 |
| ⑧中国語表現 |
| ⑨「断腸」という名前の花「断腸花」 |
| 【断腸の思い】7つの類語・言い換え表現 | |
| 身を切る思い | 胸が張り裂ける思い |
| 悲痛な思い | やり場のない気持ち |
| やりきれない思い | 九腸寸断 |
| 母猿断腸 | |

| 【断腸の思い】5つの反対語・対義語 | |
| 笑壷に入る | 幸福 |
| 至福 | 快楽 |
| 満足 | |

| 【断腸の思い】5つの英語表現 | |
| heartbroken thoughts | |
| feel heartrending grief | |
| overwhelming sorrow | |
| make a heart-rending decision | |
| gut-wrenching feeling |

| 【断腸の思い】2つの中国語表現 | |
| 万分悲痛的 | 断肠的 |


故事成語【断腸の思い】意味・読み方
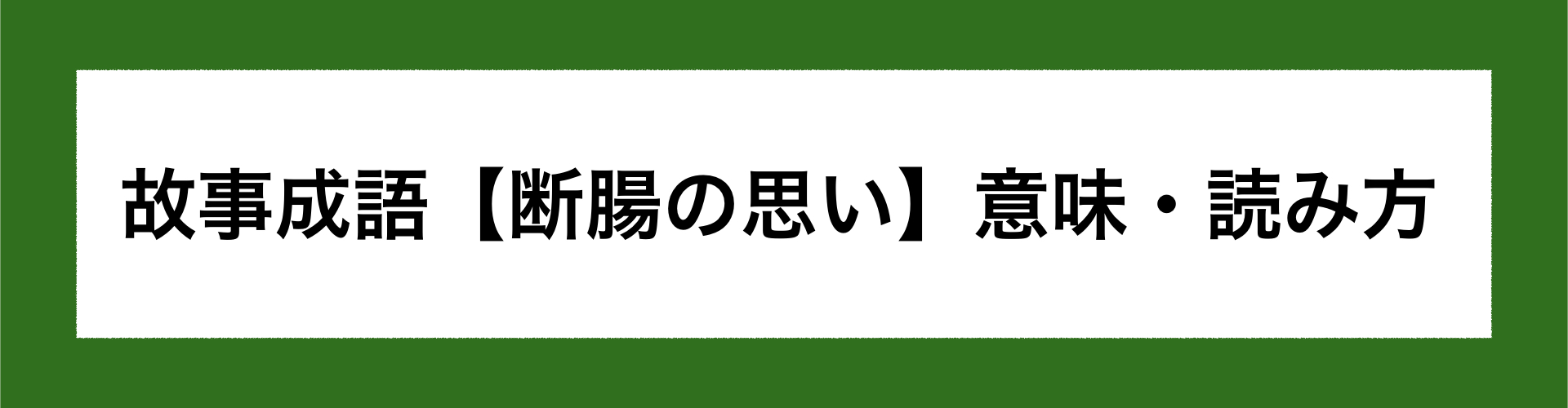
意味・読み方
- ❶【断腸の思い】の意味
- ❷「断腸」の意味
- ❸【断腸の思い】の読み方

【断腸の思い】の意味
【断腸の思い】の意味は、非常につらく悲しい気持ちのことです。
| 【断腸の思い】の意味 |
| はらわたがちぎれるほど、非常につらく悲しい気持ち |
「断腸」の意味
「断腸」の意味は、非常につらく悲しいことです。
| 「断腸」の意味 |
| はらわたがちぎれるほど、非常につらく悲しいこと |
【断腸の思い】の読み方
【断腸の思い】の読み方は「だんちょうのおもい」です。
【断腸の思い】由来・語源は悲しい猿の親子の故事
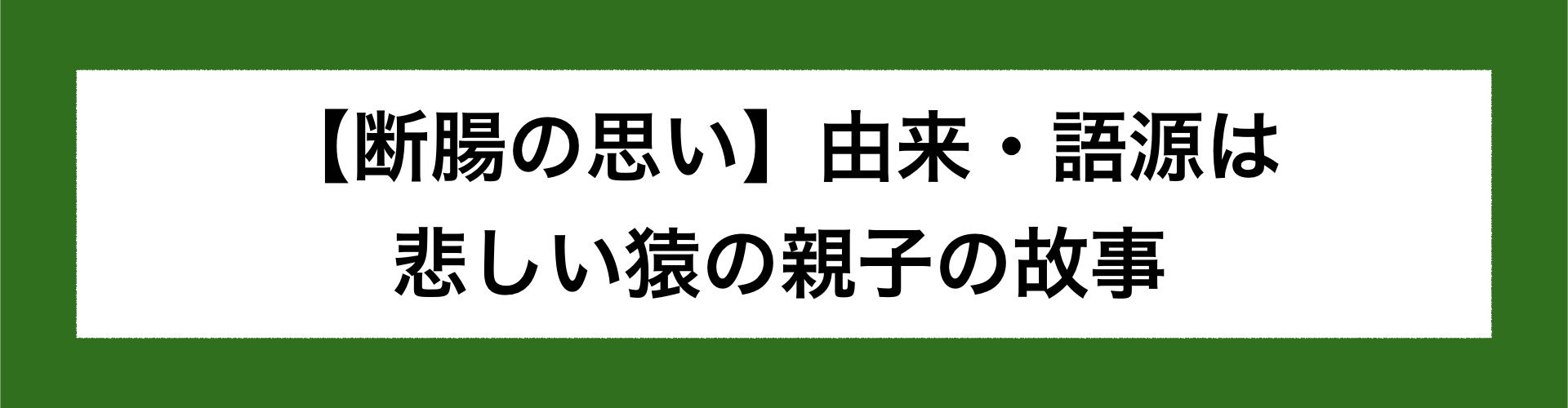
由来・語源
- ❶由来・語源は悲しい猿の親子の故事
- ❷ 悲しい猿の親子の故事/物語の内容
- ❸「世説新語(せせつしんご)」とは
- ❹長江の「三峡(さんきょう)」の場所

【断腸の思い】由来・語源は悲しい猿の親子の故事
【断腸の思い】の由来・語源は、悲しい猿の親子の故事です。
中国南北朝時代の逸話集「世説新語(せせつしんご)」の「黜免(ちゅつめん)」に書かれている物語です。
悲しい猿の親子の故事/物語の内容
中国の南北朝時代、晋国の武将・桓温(かんおん)が、船で蜀(しょく)へ渡っていた時のことです。
長江の「三峡(さんきょう)」という渓谷を通った時に、兵士が猿の子供を捕まえました。
母猿は泣き叫びながら、岸伝いに船を追いかけてきます。
数十キロ行ったところで船が岸につくと、母猿は船に乗り込んできますが、そのまま死んでしまいました。
この母猿のお腹を裂いて見てみると、腸がズタズタに切れていたそうです。
子猿を奪われた悲しみがあまりにも深かったため、母猿の腸はズタズタに切れてしまいました。
このことから、「非常につらく悲しい気持ち」という意味で【断腸の思い】という言葉が使われるようになりました。
「世説新語(せせつしんご)」とは
「世説新語」は、中国の南北朝時代に宋国の王「劉義慶(りゅう ぎけい)」がまとめた逸話集です。
後漢末から東晋までの著名人の逸話が、文学・政治など36のジャンルにまとめられています。
事実とは言い難い、フィクションな逸話も含まれているようです。
長江の「三峡(さんきょう)」の場所
「三峡」は、長江にある3つの峡谷「瞿塘峡(くとうきょう)」「巫峡(ふきょう)」「西陵峡(せいりょうきょう)」の総称です。
| 長江にある三つの峡谷 |
| ①瞿塘峡(くとうきょう) ②巫峡(ふきょう) ③西陵峡(せいりょうきょう) |
雄大な自然が美しく、多くの観光客が訪れる景勝地です。
最も下流にあるのが「西陵峡」です。
猿の親子の故事「断腸」/漢文の現代語訳・書き下し文
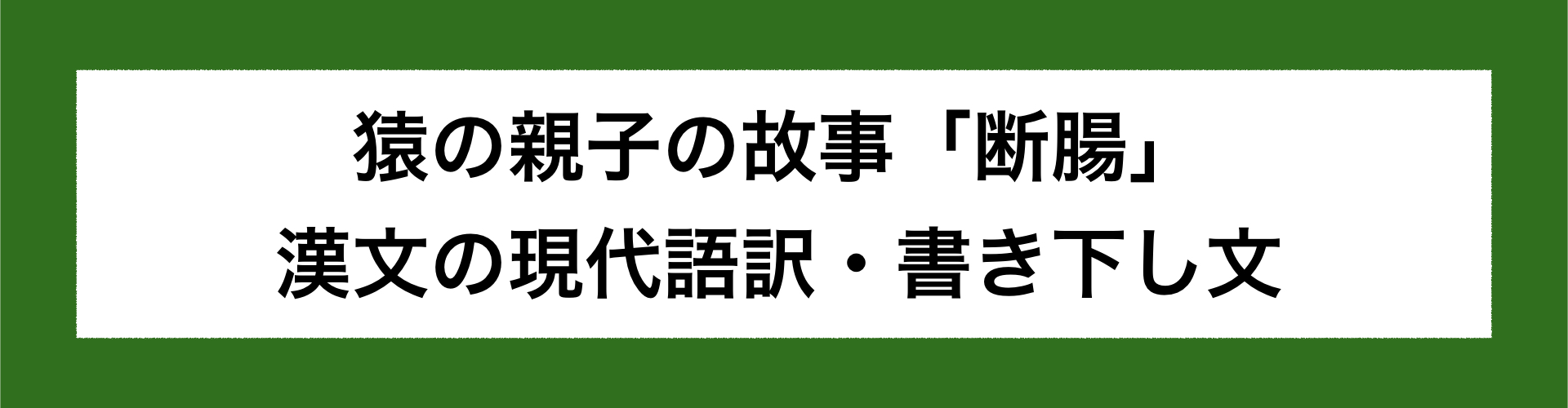

| 原文・白文 | 桓公入蜀、至三峽中。 |
| 読み仮名 | かんこう しょくにいり さんきょうちゅうにいたる。 |
| 書き下し文 | 桓公蜀に入り、三峡の中に至る。 |
| 現代語訳 | 桓公は蜀に入り、三峡にたどり着いた。 |
| 原文・白文 | 部伍中有得猿子者。 |
| 読み仮名 | ぶごのうちに えんしをえるものあり。 |
| 書き下し文 | 部伍の中に猿子を得る者有り。 |
| 現代語訳 | 部隊の中に猿の子供を捕まえた者がいた。 |
| 原文・白文 | 其母緣岸哀號、行百餘里不去。 |
| 読み仮名 | そのははきしによして あいごうし、ゆくこと ひゃくよりなるもさらず。 |
| 書き下し文 | 其の母岸に縁りて哀號し、行くこと百餘里にして去らず。 |
| 現代語訳 | その猿の母は岸沿いに子猿を追いかけながら泣き叫び、百里あまり進んでも後を追いかけ続けた。 |
| 原文・白文 | 遂跳上船、至便即絶。 |
| 読み仮名 | ついにおどりてふねにのり、いたればすなわちたゆ。 |
| 書き下し文 | 遂に跳りて船に上り、至ればすなはち絶ゆ。 |
| 現代語訳 | そのまま跳んで船に乗り込み、子猿のもとやってくるとすぐに死んでしまった。 |
| 原文・白文 | 破視其腹中、腸皆寸寸斷。 |
| 読み仮名 | やぶりてそのはらのなかをみれば、はらわた みなすんすんにたえたり。 |
| 書き下し文 | 破りて其の腹の中を視れば、腸皆寸寸に斷えたり。 |
| 現代語訳 | 母猿の腹を破いて中を見ると、腸がずたずたにちぎれていた。 |
| 原文・白文 | 公聞之怒、命黜其人。 |
| 読み仮名 | こうこれをききていかり、めいじて そのひとを しりぞけしむ。 |
| 書き下し文 | 公之を聞きて怒り、命じて其の人を黜けしむ。 |
| 現代語訳 | 桓公はこのことを聞いて怒り、子猿を捕まえた者を降格させた。 |
【断腸の思い】例文・使い方

例文・使い方
- ❶例文
- ❷使い方

例文
| 例文1 | 断腸の思いだが、不運を悲しんでばかりいられない。 |
| 例文2 | 断腸の思いで叱ったが、後から後悔した。 |
| 例文3 | 断腸の思いで、父を施設に入所せることにした。 |
| 例文4 | お客様の希望に応じることができず、断腸の思いだ。 |
| 例文5 | ドクターストップがかかり、断腸の思いでボクシングを諦めた。 |
使い方
【断腸の思い】は、「断腸の思いで〇〇する」「断腸の思いだ」という言い回しで使われることが多いです。




【断腸の思い】7つの類語・言い換え表現
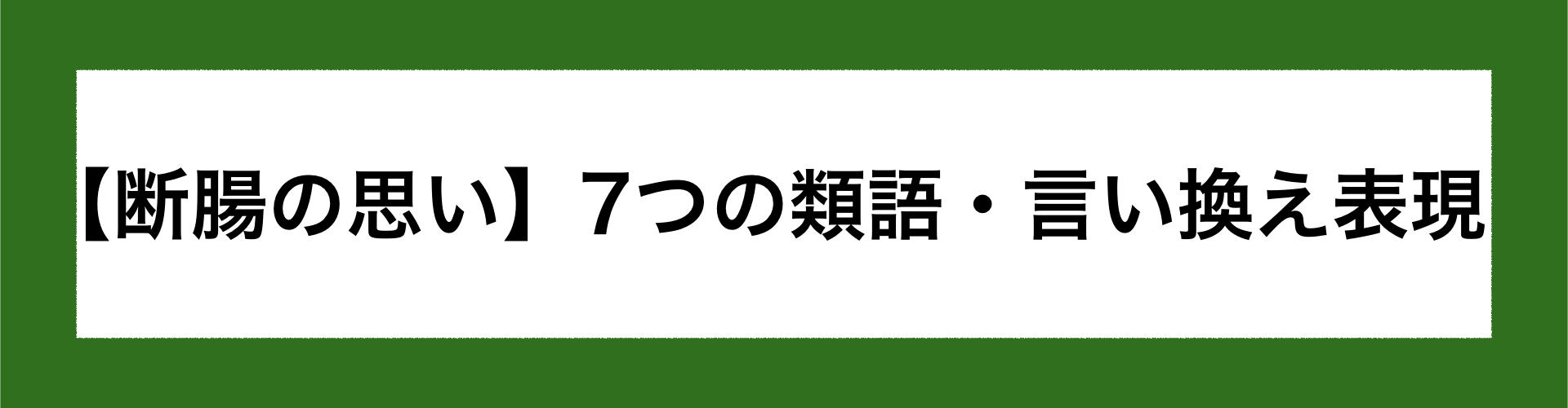

【断腸の思い】の類語・言い換え表現は「身を切る思い」「胸が張り裂ける思い」なのです。
| 【断腸の思い】7つの類語・言い換え表現 | ||
| 1 | 身を切る思い (みをきるおもい) |
どうしようもなく悲しく残念な気持ち |
| 2 | 胸が張り裂ける思い (むねがはりさけるおもい) |
苦しみや悲しみで胸がいっぱいになる |
| 3 | 悲痛な思い (ひつうなおもい) |
つらい思い |
| 4 | やり場のない気持ち (やりばのないきもち) |
解決する手段のない気持ちや思い |
| 5 | やりきれない思い (やりきれないおもい) |
非常につらく苦しく、耐えられない気持ち |
| 6 | 九腸寸断 (きゅうちょうすんだん) |
非常に悲しいこと |
| 7 | 母猿断腸 (ぼえんだんちょう) |
激し苦しみや悲しみ |
【断腸の思い】5つの反対語・対義語
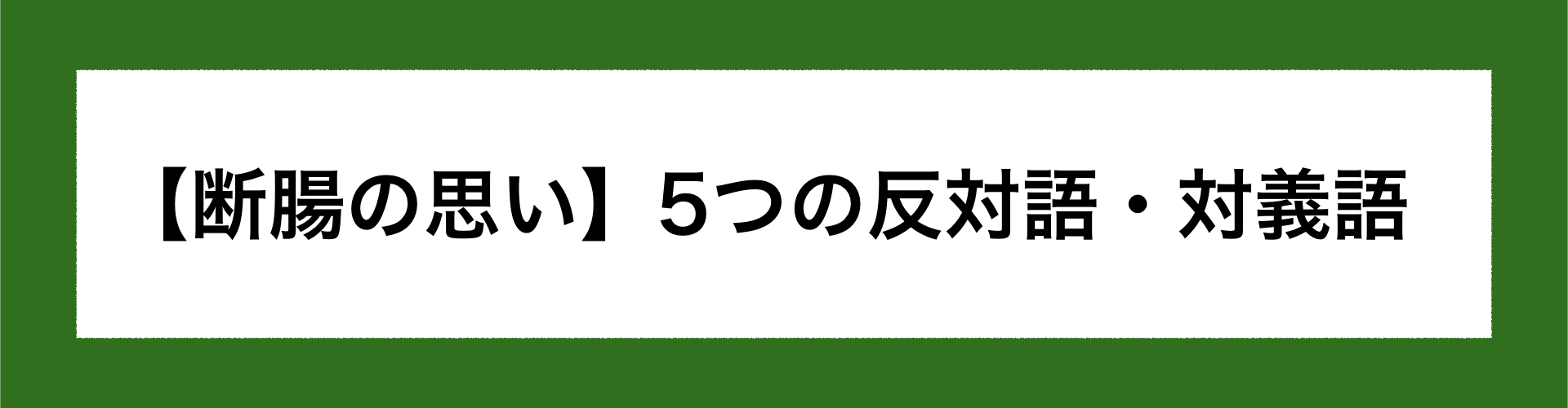

【断腸の思い】の反対語は、「笑壷に入る」「幸福」などがあります。
| 【断腸の思い】5つの反対語・対義語 | ||
| 1 | 笑壷に入る (えつぼにいる) |
思い通りになって大いに喜ぶ |
| 2 | 幸福(こうふく) | 満足できて楽しいこと |
| 3 | 至福(しふく) | この上ない幸せ |
| 4 | 快楽(かいらく) | 気持ちよく楽しいこと |
| 5 | 満足(まんぞく) | 心が満ち足りていること |
【断腸の思い】5つの英語表現
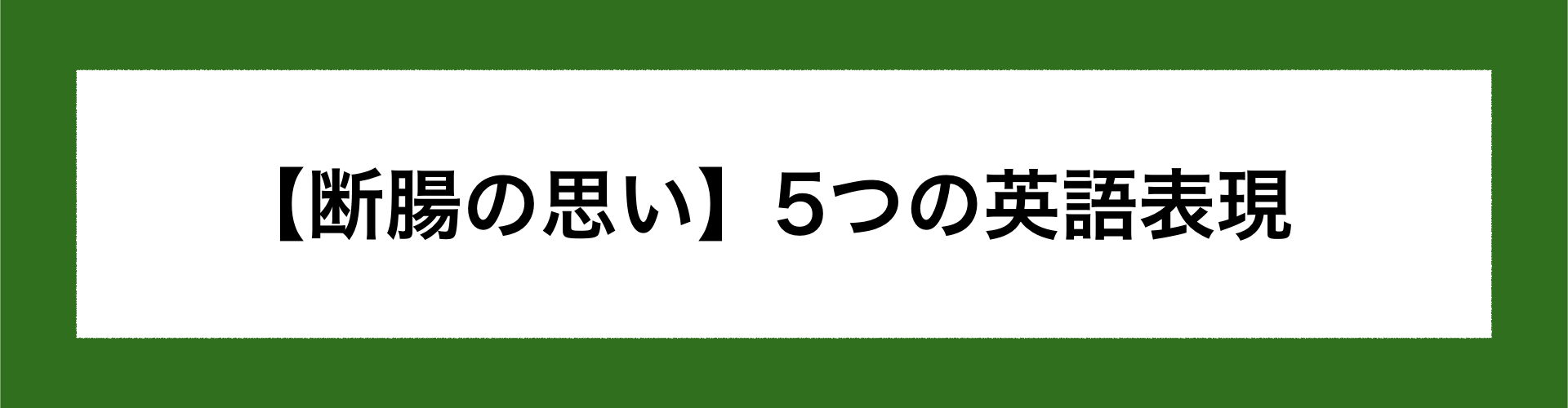

【断腸の思い】の英語表現は次のようになります。
| 【断腸の思い】5つの英語表現 | ||
| 1 | heartbroken thoughts | |
| 心が張り裂けそうな思い | ||
| 2 | feel heartrending grief | |
| 断腸の思いだ | ||
| 3 | overwhelming sorrow | |
| 圧倒的な悲しみ | ||
| 4 | make a heart-rending decision | |
| 悲痛な決断を下す | ||
| 5 | gut-wrenching feeling | |
| 胸が張り裂けそうな感覚 | ||
| She made a heart-rending decision for her family. |
| 彼女は家族のために断腸の思いで決断した。 |
【断腸の思い】2つの中国語表現
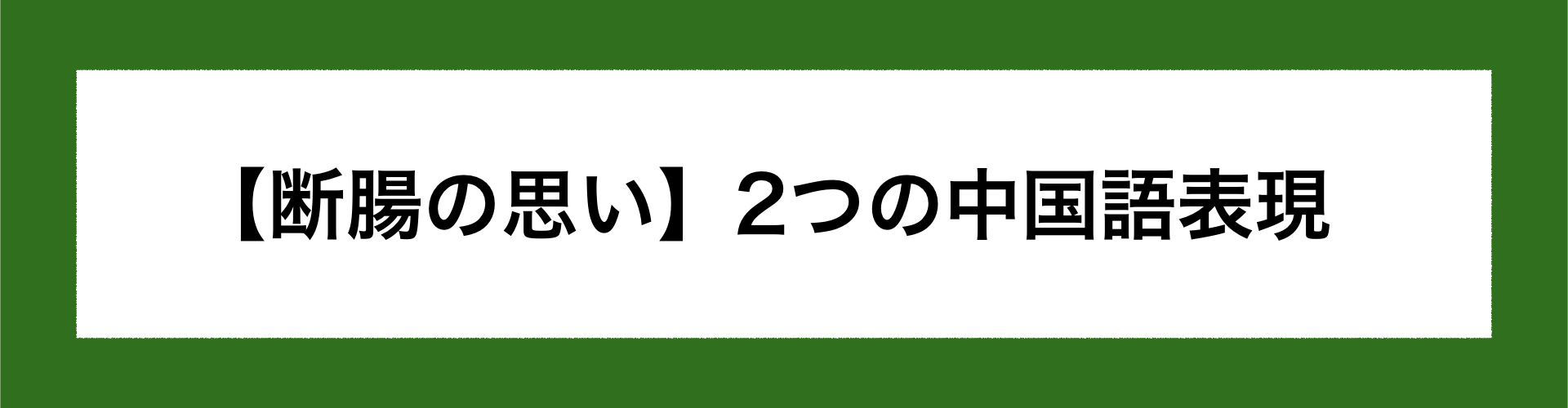

【断腸の思い】の中国語表現は、次のようになります。
| 【断腸の思い】2つの中国語表現 | |
| 万分悲痛的 | 断肠的 |
「断腸」という名前の花「断腸花」
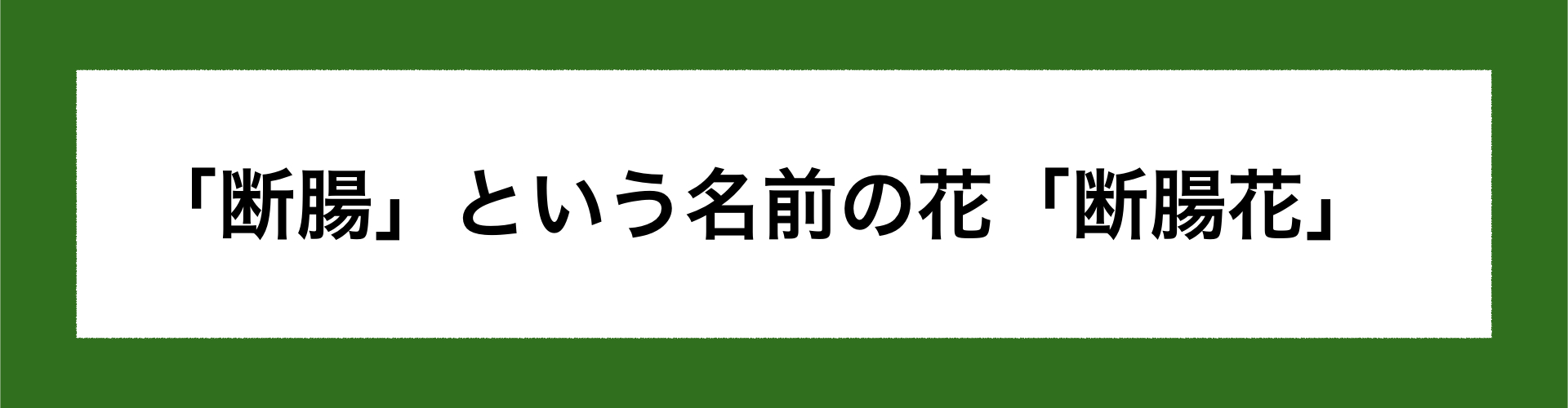

「断腸」という言葉がつく花に「断腸花」があります。
「断腸花」は「秋海棠(しゅうかいどう)」の別名で、シュウカイドウ科の多年草です。
ベゴニアに似た中国原産の花で、高さ約60cm、夏〜秋に紅色の花茎を伸ばし、淡紅色の花を咲かせます。
俳句では秋の季語とされ、松尾芭蕉の俳句にも登場しています。
| 「秋海棠 西瓜の色に 咲きにけり」 松尾芭蕉 |



