


| 【背水の陣】の現在の意味と本来の意味 | |
| 現在の意味 | しっかりと勝つための戦略を立て、その中で、絶体絶命の状況に身をおき、失敗したら後はないと、決死の覚悟で物事に取り組むこと |
| 本当の意味(本来の意味) | しっかりと勝つための戦略を立て、その中で、絶体絶命の状況に身をおき、失敗したら後はないと、決死の覚悟で物事に取り組むこと |
| 現在の意味と本当の意味(本来の意味)の違い | 絶体絶命の状況になってから、覚悟をもって物事に取り組むという無謀なことではなく、緻密な戦略を立てて物事に取り組むところ |
| 【背水の陣】の由来 |
| 「史記」書かれている「井陘の戦い(漢国人と越国人の戦い)」にまつわる故事 川を背にして、逃げ場がない状況に陣をとった漢国軍が、決死の覚悟で戦い、勝利をおさめたことに由来 |
|
【背水の陣】の5つの英語表現 |
||
| burn one’s bridge | burn one’s boat | run out of option |
| have one’s back against the wall | last stand | |
|
【背水の陣】の7つの類義語 |
||
| 絶体絶命 | 孤立無援 | 悪戦苦闘 |
| 崖っぷち | 瀬戸際 | 四面楚歌 |
| 五里霧中 | ||
|
【背水の陣】の似た意味の5つのことわざ |
||
| 井を塞ぎ竈を平らぐ | 前門の虎後門の狼 | 船を沈め釜を破る |
| 釜を破り船を沈む | 糧を捨てて船を沈む | |
【背水の陣(はいすいのじん)】の意味・読み方とは
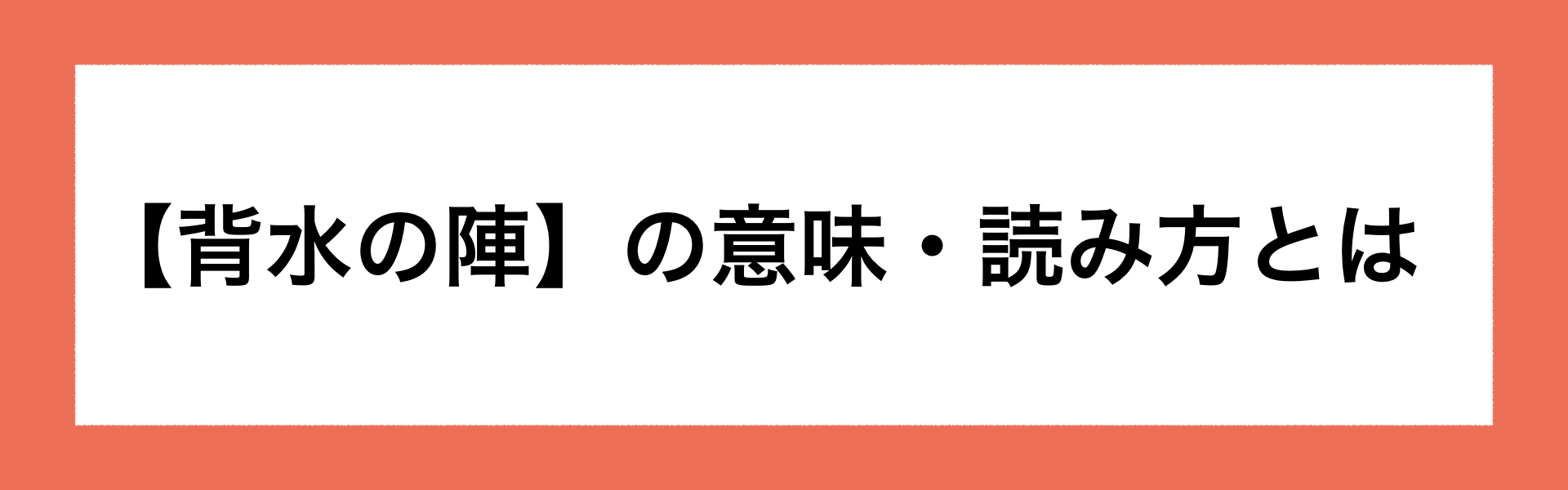
【背水の陣】の意味をわかりやすく解説
「背水の陣」とは、絶体絶命の状況で、決死の覚悟で物事に取り組むことのたとえです。
| 「背水の陣」の意味 |
| 絶体絶命の状況の中で、失敗したら後はないと、決死の覚悟で物事に取り組むこと |
「背水」の意味とは
「背水」とは、背中側に水(川や海)があるという意味です。
| 「背水」の意味 |
| 背中側(後ろ側)に川や海があること |
「陣」の意味とは
「陣」とは、軍の配置という意味です。
| 「陣」の意味 |
| 戦いの時の軍隊の配置 |
【背水の陣】の読み方
「背水の陣」は「はいすいのじん」と読みます。
【背水の陣】の由来・語源は「史記(しき)」書かれている中国の故事
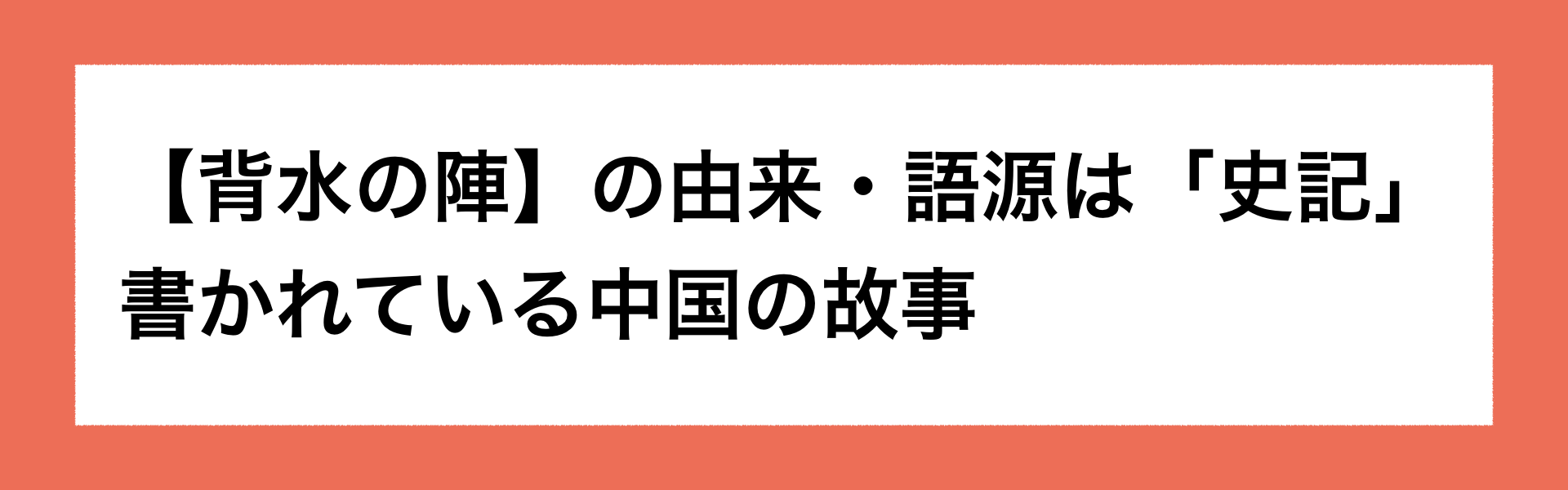
由来・語源は「史記」書かれている中国の故事
「背水の陣」は、中国の歴史書「史記」書かれている故事に由来しています。
「史記」の92巻「淮陰侯伝(わいいんこうでん)」に書かれている、「井陘の戦い(せいけいのたたかい)」にまつわるエピソードです。
「井陘の戦い」は、中国の楚漢戦争の中で行われた、漢と趙の戦いです。
漢は「背水の陣」と言う戦術を使い、勝利をおさめました。
語源は「井陘の戦い」での戦術
兵力の少なかった漢の軍は、あえて川を背にして、逃げ場がない状況に陣をとる作戦をとりました。
逃げ場がなくなった漢の兵士は、決死の覚悟で戦い勝利をおさめたそうです。
このことから、「絶体絶命の状況で、決死の覚悟で物事に取り組むこと」を「水を背にして陣をとる」→「背水の陣」と言うようになりました。
中国の歴史書「史記」とは
「史記」とは、中国の前漢時代に司馬遷(しばせん)によって編纂された歴史書です。
中国王朝の正史である「二十四史」の1つで、黄帝から前漢武帝までの二千数百年の歴史がまとめられています。
「本紀」12篇・「表」10篇・「書」8篇・「世家」30篇・「列伝」70篇の計130編成。
中国の歴史上最高傑作と言われるほど高く評価されている歴史書です。
「淮陰侯伝」は、漢軍の将軍・韓信の伝記です。
「背水の陣」の舞台となった場所と地図
「背水の陣」の舞台であり、「井陘の戦い」の戦場となったのは、現在の中国河北省石家荘市井陘県です。
【背水の陣】のエピソード・物語の内容をわかりやすく解説
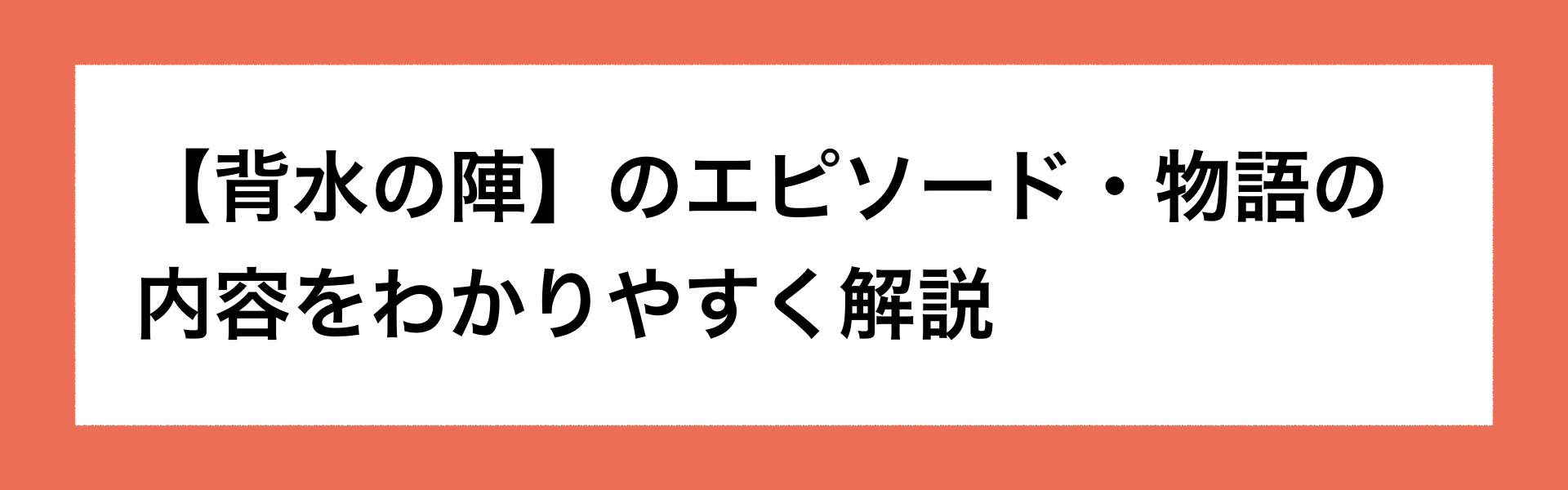
中国の楚漢戦争の中で起きた、漢vs趙の「井陘の戦い(せいけいのたたかい)」でのことです。
兵力が少ない漢軍
漢の兵力は少なく、三万程度。
対する趙の兵力は、二十万という大軍でした。
趙は城に立てこもっていた為、漢はなかなか攻めることができませんでした。
圧倒的な兵力の差がある状況で、無理な戦いをしない漢軍の将軍・韓信は、周到な作戦を立てます。
漢の将軍・韓信の作戦
韓信は、漢軍を二手に分けます。
自分の率いている軍(本隊)は、城を正面に、川を背にして陣をとりました。
もう一方の軍(支隊)は、城の裏側に隠れて陣をとっていました。
趙軍の攻撃
漢軍(本隊)が川を背にして陣をとっている様子を見て、「韓信は兵法の初歩も知らない」と越軍は笑っていました。
城から一気に攻撃をすれば、漢軍には逃げ場がない。
兵力の差もあるため、一気に攻撃して漢軍を打ち倒そうと、趙軍はほぼ全軍を率いて攻撃を開始。
一方、漢軍(本隊)は負けた振りをして越軍をおびき寄せ、川岸で応戦します。
兵力は越軍が優勢でしたが、逃げ場のない漢軍は必死に戦ったため、越軍はなかなか打ち破ることができません。
被害が増えてきたため越軍が一度城へ戻ろうとすると、城は漢軍(支隊)に占領され、漢軍の旗が大量に立てられていました。
漢軍の動き
越軍が漢軍(本隊)を攻撃している隙に、城の裏側に隠れていた漢軍(支隊)は、越軍の城を占領し、漢軍の旗をたくさん立てます。
自分たちの城に漢軍の旗が立っているのを見た越軍は動揺し、混乱状態に。
その隙に、漢軍は本隊・支隊とで両面から越軍を攻め、越軍を打ち倒します。
漢の将軍・韓信の言葉
この戦いになぜ勝てたのかと聞かれた韓信は、このように答えています。
| 兵法書に書いてある通りにしただけだ。兵士を逃げ場のない場に置けば、勇戦力闘する |
この言葉が現在使われている「背水の陣」です。
【背水の陣】の本当の意味(本来の意味)
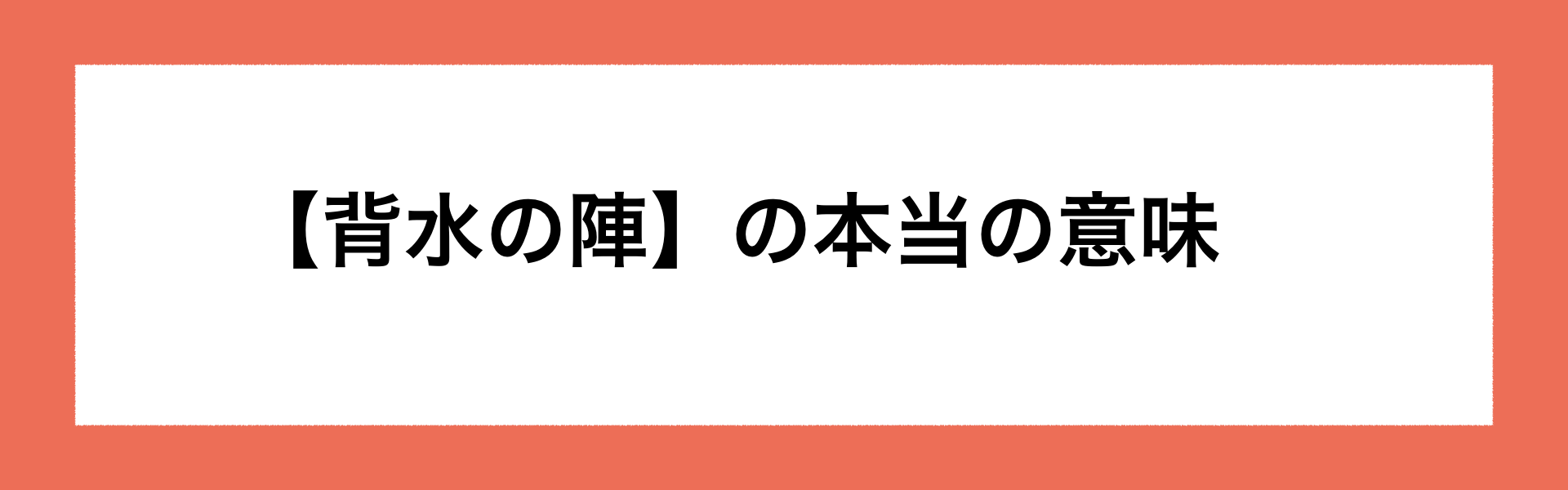
韓信の戦略
「井陘の戦い」で、韓信はこのような戦略を立てました。
| ・あえて川を背にして、逃げ場がない状況に陣をとる作戦をとり、相手を油断させた ・負けたふりをして越軍を川岸におびき寄せ、川の近くまでわざと追い詰められて応戦した ・応戦している隙に、越軍の城を占領した ・城に漢軍の旗を大量に立て、越軍が混乱しているところを両面から攻める |
韓信は、緻密で高度な戦略を立てることで、勝利をおさめることができました。
【背水の陣】の本当の意味(本来の意味)
「背水の陣」の本当の意味(本来の意味)は、緻密な戦略です。
| 「背水の陣」の本当の意味(本来の意味) |
| しっかりと勝つための戦略を立て、その中で、絶体絶命の状況に身をおき、失敗したら後はないと、決死の覚悟で物事に取り組むこと |
ただ単に、絶体絶命の状況になってから、覚悟をもって物事に取り組むという無謀なことではありません。
しっかりと考え、戦略を立てて物事に取り組むことが大切という意味が含まれています。
【背水の陣】漢文の書き下し文・現代語訳
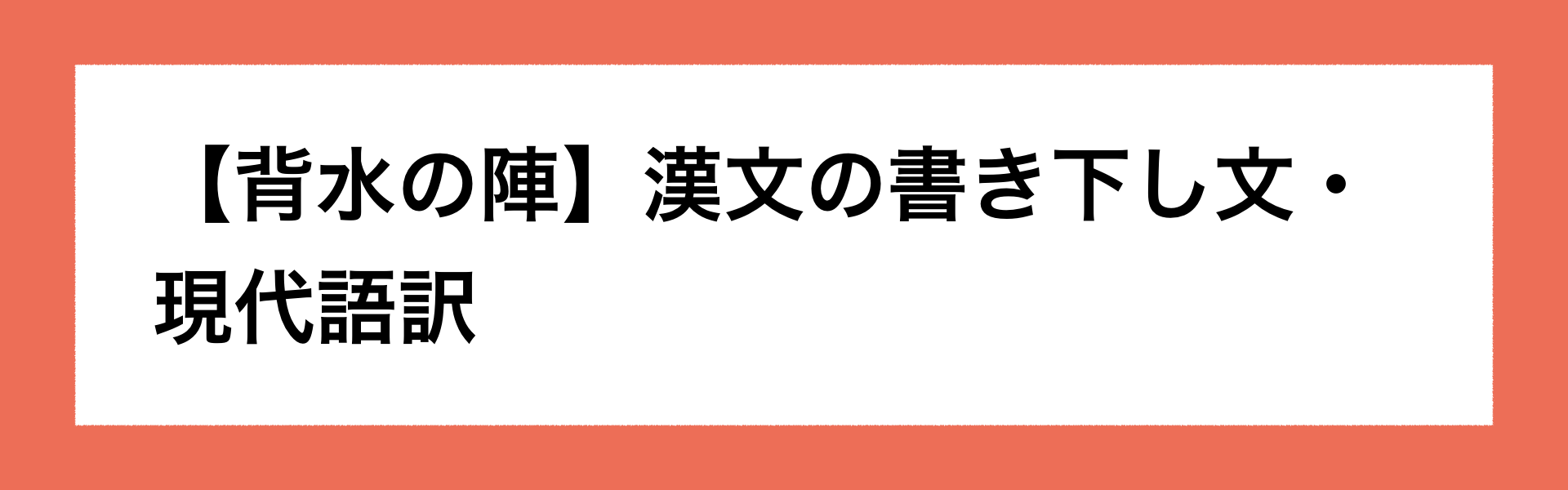
漢軍の兵士二千人が城の裏側へ出陣
| 原文・白文 | 未至井陘口三十里止舎。 |
| 書き下し文 | 未だ井陘(せいけい)の口に至らざること三十里にして止まり舎す。 |
| 現代語訳 | 韓信の軍は、井陘の入り口に至る手前三十里のところで宿営しました。 |
| 原文・白文 | 夜半伝発、選軽騎二千人、人持一赤幟、従間道萆山而望趙軍。 |
| 書き下し文 | 夜半に伝発し、軽騎二千人を選び、人ごとに一赤幟(せきし)を持ち、間道より山に萆(かく)れて趙の軍を望ましむ。 |
| 現代語訳 | 韓信は夜中に伝令をだし、軽装の騎兵二千人を選んで、どの兵にも一つ赤いのぼり旗を持たせて、抜け道を通って山に隠れて趙の軍を遠くから偵察させました。 |
| 原文・白文 | 誡曰、 |
| 書き下し文 | 誡(いまし)めて曰はく、 |
| 現代語訳 | 韓信が兵に戒めて言いました。 |
| 原文・白文 | 「趙見我走、必空壁逐我。 若疾入趙壁、抜趙幟、立漢赤幟。」 |
| 書き下し文 | 「趙我が走(に)ぐるを見るや、必ず壁を空しくして我を逐はん。若疾く趙の壁に入り、趙の幟を抜き、漢の赤幟を立てよ。」と。 |
| 現代語訳 | 「趙の軍は、我々が敗走するのを見たら、必ず砦を空にして我々を追ってくるだろう。 お前たちは素早く趙の砦に入って、趙の旗を抜いて、漢の赤いのぼり旗を立てろ。」と。 |
韓信から兵士への言葉
| 原文・白文 | 令其裨将伝飧曰、「今日破趙会食。」 |
| 書き下し文 | 其の裨将(ひしょう)をして飧を伝へしめて曰はく、「今日趙を破りて会食せん。」と。 |
| 現代語訳 | 韓信は副将軍に軽い食事を配らせて、「今日、趙を打ち破って会食をすることとしよう」と言いました。 |
| 原文・白文 | 諸将皆莫信、詳応曰、「諾。」 |
| 書き下し文 | 諸将皆信ずる莫なし、詳(いつは)り応へて曰はく、「諾。」と。 |
| 現代語訳 | 将軍の中で韓信の言葉を信じる者はいませんでした。「承知しました。」と偽って答えて言いました。 |
| 原文・白文 | 謂軍吏曰、「趙已先拠便地為壁。 |
| 書き下し文 | 軍吏に謂ひて曰はく、「趙已に先に便地に拠りて壁を為(つく)る。 |
| 現代語訳 | 韓信は軍吏に伝えて言いました。「趙はすでに 先に戦うのに有利な土地を占拠して砦を築いている。 |
| 原文・白文 | 且彼未見吾大将旗鼓、未肯撃前行。 |
| 書き下し文 | 且つ彼未だ吾が大将の旗鼓を見ざれば、未だ肯えて前行こうを撃うたざらん。 |
| 現代語訳 | その上、彼らは我が軍の大将の旗や太鼓を見ていないので、まだ先行部隊を攻撃しようとはしないだろう。 |
| 原文・白文 | 恐吾至阻険而還。」 |
| 書き下し文 | 吾の阻険(そけん)に至いたりて還かえらんことを恐おそるればなり。」と。 |
| 現代語訳 | なぜなら私が険しい所にきて逃げ帰ることを恐れているからである」と。 |
韓信軍が川岸へ出陣
| 原文・白文 | 信乃使万人先行、出背水陳。 |
| 書き下し文 | 信乃ち万人をして先行こうせしめ、出でて水を背にして陳じんす。 |
| 現代語訳 | 韓信は、一万の兵を先行させ、(井陘口を)出て、川を背にして陣を構えさせた。 |
| 原文・白文 | 趙軍望見而大笑。 |
| 書き下し文 | 趙軍望み見て大いに笑う。 |
| 現代語訳 | 趙軍はこれを遠くに見て、大いに笑った。 |
| 原文・白文 | 平旦、信建大将之旗鼓、鼓行出井陘口。 |
| 書き下し文 | 平旦、信大将の旗鼓を建て、鼓行して井陘口を出づ。 |
| 現代語訳 | 夜明け頃に、韓信は大将の旗を立て、太鼓を打ち鳴らしながら井陘口を出ました。 |
越軍の出陣
| 原文・白文 | 趙開壁撃之、大戦良久。 |
| 書き下し文 | 趙壁を開きて之を撃ち、大いに戦ふこと良久(ややひさ)し。 |
| 現代語訳 | 趙の軍は砦を開いてこれを迎え撃地、激しい戦いは、しばらく続いた。 |
| 原文・白文 | 於是信・張耳、詳棄鼓旗、走水上軍。 |
| 書き下し文 | 是に於いて信・張耳、詳(いつわ)りて鼓旗を棄て、水上の軍に走ぐ。 |
| 現代語訳 | そこで韓信と張耳は、負けたふりをして太鼓や旗を捨てて、川岸に陣取った軍へと逃げました。 |
| 原文・白文 | 水上軍開入之、復疾戦。 |
| 書き下し文 | 水の上の軍開きて之を入れ、復た疾戦す。 |
| 現代語訳 | 川岸の軍は陣を開いてこれ(韓信・張耳)を迎え入れて、再び激しく戦いました。 |
韓信を追う越軍
| 原文・白文 | 趙果空壁争漢鼓旗、逐韓信・張耳。 |
| 書き下し文 | 趙果たして壁を空しくして漢の鼓旗を争ひ、韓信・張耳を逐(お)ふ。 |
| 現代語訳 | 趙軍は思ったとおり砦を空にして漢軍の太鼓や旗を争奪し、韓信と張耳を追ってきました。 |
| 原文・白文 | 韓信・張耳、已入水上軍、軍皆殊死戦、不可敗。 |
| 書き下し文 | 韓信・張耳、已に水上の軍に入る。軍皆殊死して戦い、敗るべからず。 |
| 現代語訳 | 韓信と張耳は、すでに川岸の軍に入っていた。(韓信の)軍は皆死にものぐるいで戦ったので、打ち破ることができませんでした。 |
越軍の城を占領した漢軍
| 原文・白文 | 信所出奇兵二千騎、共候趙空壁逐利、 |
| 書き下し文 | 信の出だしし所の奇兵二千騎、共に趙の壁を空しくして利を逐ふを候うかがひ、 |
| 現代語訳 | 韓信が先行させた兵二千騎は、そろって趙軍が砦を空にして戦利品を追い求めているのをうかがって、 |
| 原文・白文 | 則馳入趙壁、皆抜趙旗、立漢赤幟二千。 |
| 書き下し文 | 則ち馳せて趙の壁に入り、皆趙の旗を抜きて、漢の赤幟二千を立つ。 |
| 現代語訳 | 馬を走らせて趙軍の砦に入り、趙軍の旗を全て抜いて、漢の赤い旗を二千本を立てた。 |
| 原文・白文 | 趙軍已不勝、不能得信等。 |
| 書き下し文 | 趙の軍已に勝たず、信等を得うる能はず。 |
| 現代語訳 | 趙軍はもはや勝つことはできず、韓信らを捕らえることができませんでした。 |
越軍の敗北
| 原文・白文 | 欲還帰壁。 |
| 書き下し文 | 壁に還帰せんと欲す。 |
| 現代語訳 | 趙軍は(砦に)帰還しようとしました。 |
| 原文・白文 | 壁皆漢赤幟而大驚、以為、漢皆已得趙王将矣。 |
| 書き下し文 | 壁皆漢の赤幟にして大いに驚き、以為へらく、漢皆已に趙の王将を得たるならんと。 |
| 現代語訳 | 砦がすべて漢の赤い旗だったので非常に驚いて、漢軍がすでに趙の王や将軍を皆捕えてしまったのだと思ったのです。 |
| 原文・白文 | 兵遂乱遁走。 |
| 書き下し文 | 兵遂に乱れて遁走(とんそう)す。 |
| 現代語訳 | (趙軍の)兵はとうとう混乱して逃げ出しました。 |
| 原文・白文 | 趙将雖斬之、不能禁也。 |
| 書き下し文 | 趙の将之を斬ると雖も、禁ずる能はざるなり。 |
| 現代語訳 | 趙の将軍は逃げる兵を斬ったのですが、制御することはできませんでした。 |
| 原文・白文 | 於是漢兵夾撃、大破虜趙軍、斬成安君泜水上、禽趙王歇。 |
| 書き下し文 | 是に於いて漢の兵夾撃し、大いに破りて趙の軍を虜にし、成安君を泜水の上に斬り、趙王の歇を禽とらう。 |
| 現代語訳 | こうして漢の兵士たちは(趙軍を)挟み撃ちにし、大いに打ち破って趙軍を捕虜とし、成安君を泜水のほとりで斬首して、趙王の歇を捕虜にしたのです。 |
【背水の陣】の使い方・例文
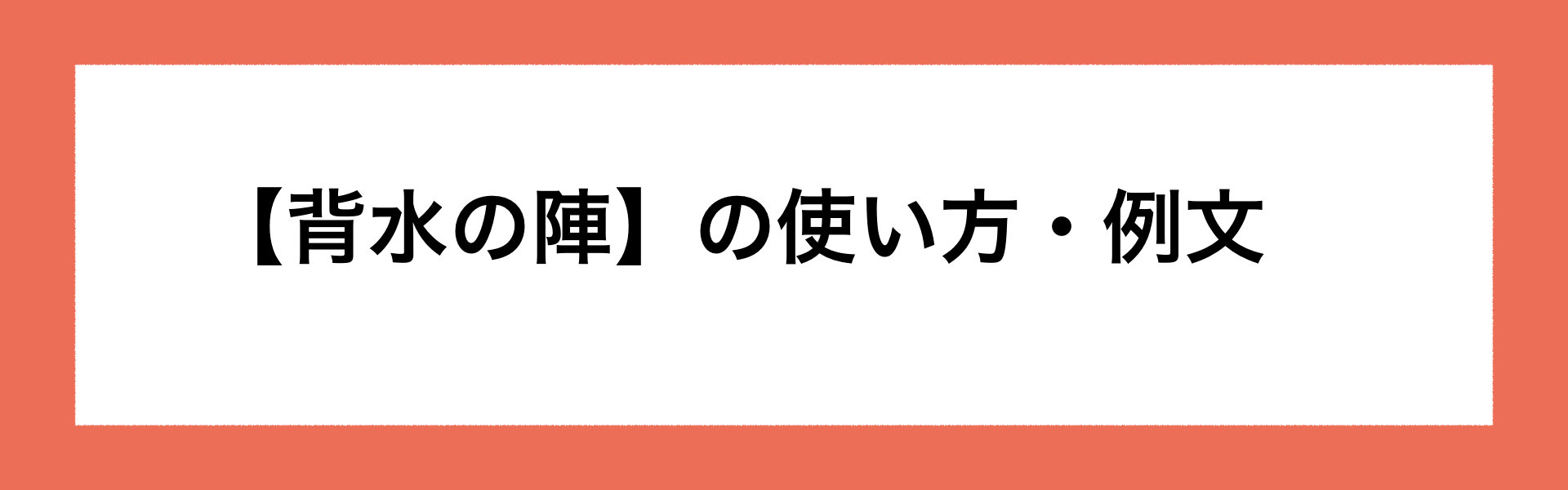
「背水の陣」は、自分の気持ちや覚悟を表現するときに使われます。
「背水の陣を敷く」「背水の陣で臨む」という使い方をすることもあります。
| 例文1 | 背水の陣で臨んだ結果、難関校に合格することができた |
| 例文2 | 甲子園出場がかかった試合に背水の陣を敷く |
| 例文3 | 試験まであと一週間、背水の陣の覚悟で勉強をする |
| 例文4 | 本場でダンスの勉強をしたかったので、背水の陣の思いでアメリカ留学をした |
| 例文5 | 背水の陣で臨んで商品を開発したところ、お店の人気商品となった |
【背水の陣】の英語表現
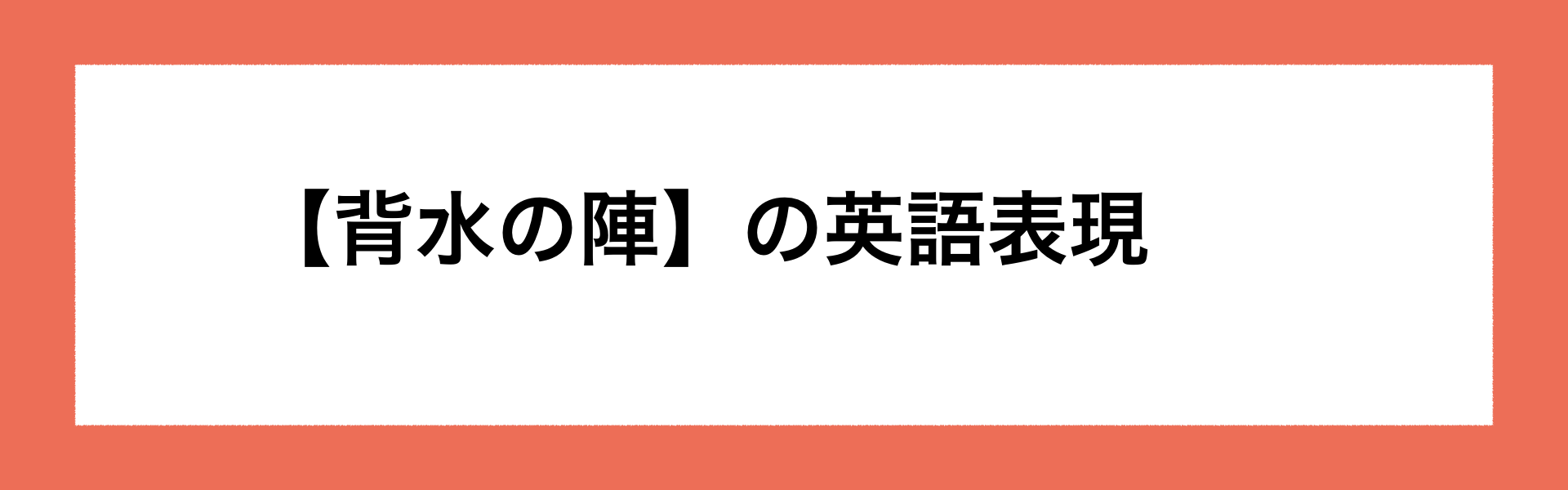
その1(burn one’s bridge)
| 英語 | 日本語 |
| burn | 燃やす |
| bridge | 橋 |
「burn one’s bridge」を直訳すると「橋を燃やす」です。
橋を燃やしてしまい、もう戻れないという意味で、「背水の陣」の英語表現として使うことができます。
| burn one’s bridge |
| ・背水の陣 ・取り返しのつかないことになる |
その2(burn one’s boat)
| 英語 | 日本語 |
| burn | 燃やす |
| boat | ボート・船 |
「burn one’s boat」を直訳すると「ボートを燃やす」です。
ボートを燃やしてしまい、もう戻れないという意味で、「背水の陣」の英語表現として使うことができます。
| burn one’s boat |
| ・背水の陣 ・取り返しのつかないことになる |
その3(run out of option)
| 英語 | 日本語 |
| run out of〜 | 〜を使い果たす・〜を切らす |
| option | 選択 |
「run out of option」で「選択の余地がない」という意味になります。
他にできることはないという意味で、「背水の陣」の英語表現として使うことができます。
| I’ve run out of options |
| 背水の陣だ |
その4(have one’s back against the wall)
| 英語 | 日本語 |
| back | 裏面・背中 |
| against | ぶつかる・当たる |
| wall | 壁 |
「have one’s back against the wall」で「背中が壁に当たっている」という意味になります。
もう後がないという意味で、「背水の陣」の英語表現として使うことができます。
| She has his back against the wall. |
| 彼女は背水の陣を敷いている |
その5(last stand)
「last stand」で「最後の砦・背水の陣・最後の抵抗」という意味です。
| This project is our last stand |
| このプロジェクトは背水の陣だ |
【背水の陣】の類義語・言い換え
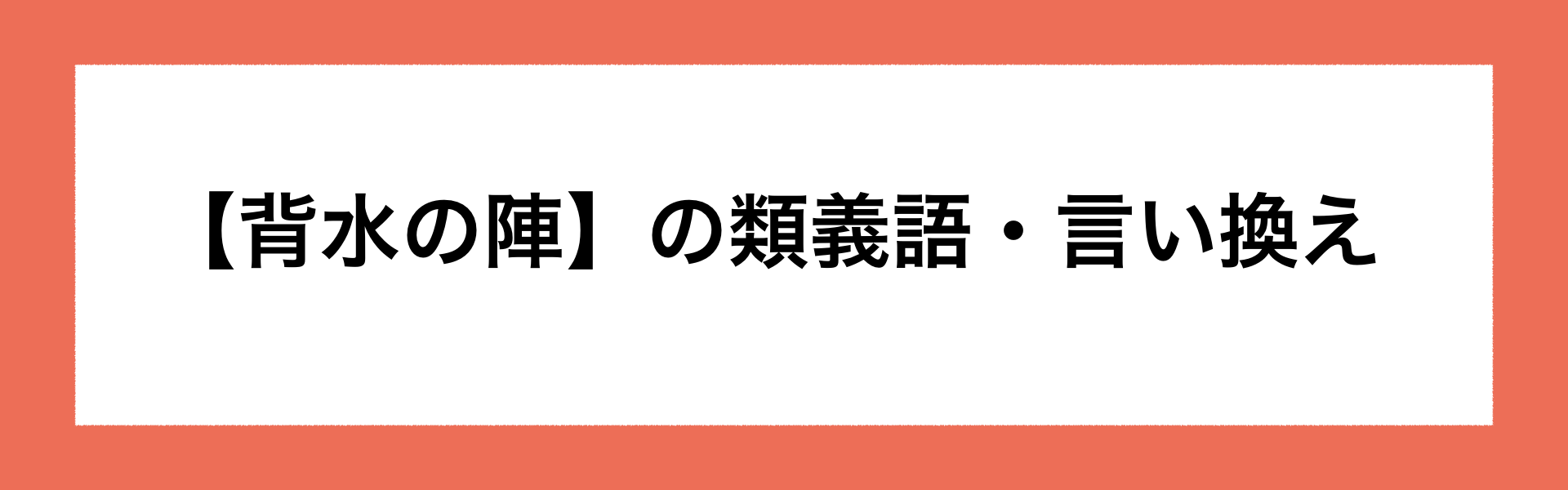
その1(絶体絶命・ぜったいぜつめい)
「絶体絶命」とは、苦境に立たされることです。
| 「絶体絶命」の意味 |
| 危機や困難から逃げることができないこと |
「背水の陣」の、どうしようもない状況という意味と共通しています。
その2(孤立無援・こりつむえん)
「孤立無援」とは、助けてくれる人がいないという意味です。
| 「孤立無援」の意味 |
| 仲間や味方、助けてくれる人が誰もいないこと |
「背水の陣」の、どうしようもない状況という意味と共通しています。
その3(悪戦苦闘・あくせんくとう)
「悪戦苦闘」とは、困難な状況でも努力することです。
| 「悪戦苦闘」の意味 |
| 困難な状況の中でも、苦しみながら一生懸命に努力すること |
「背水の陣」の、不利な状況で戦うという意味と共通しています。
その4(崖っぷち・がけっぷち)
「崖っぷち」とは、ギリギリの状況という意味です。
| 「崖っぷち」の意味 |
| 限界のギリギリの状況 |
「背水の陣」の、どうしようもない状況という意味と共通しています。
その5(瀬戸際・せとぎわ)
「瀬戸際」とは、運命の分かれ目意味しています。
| 「瀬戸際」の意味 |
| 勝つか負けるか、成功するか失敗するかなどの運命の分かれ目 |
その6(四面楚歌・しめんそか)
「四面楚歌」とは、周りに味方がいないことです。
| 「四面楚歌」の意味 |
| 周りに味方がなく、敵や反対者ばかりのこと |
「背水の陣」の、どうしようもない状況という意味と共通しています。
その7(五里霧中・ごりむちゅう)
「五里霧中」とは、現在の状況がわからず判断に迷うことです。
| 「五里霧中」の意味 |
| 物事の状況がわからず、どうしたらいいか判断に迷うこと |
「背水の陣」の、どうしようもない状況という意味と共通しています。
【背水の陣】と似た意味のことわざ
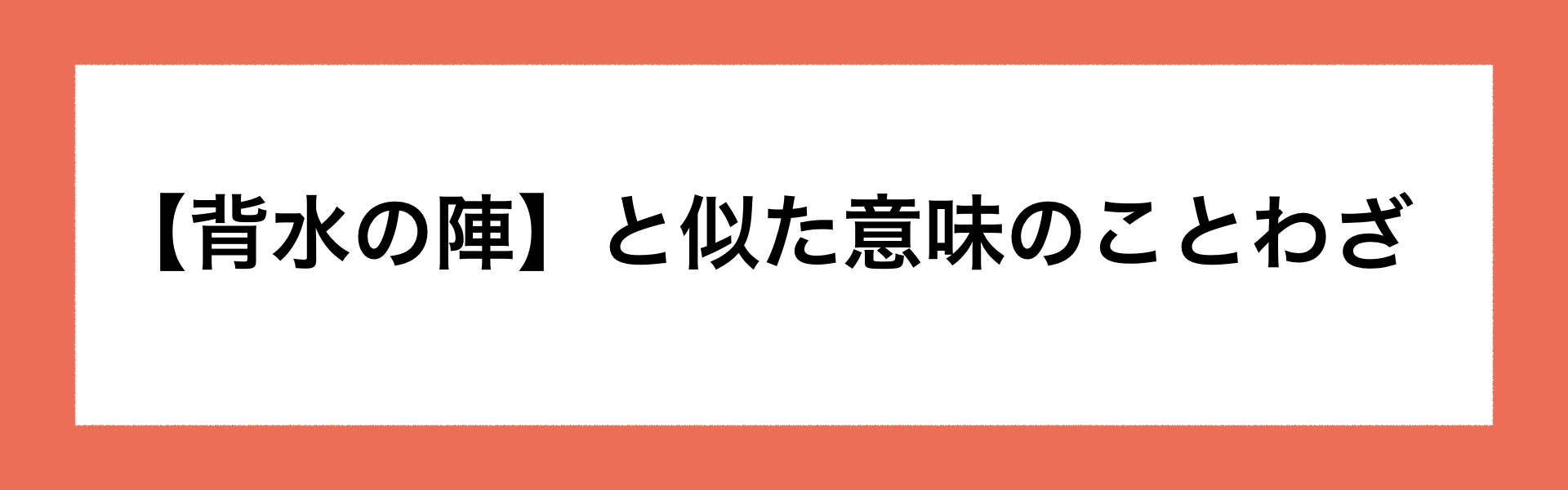
その1(井を塞ぎ竈を平らぐ)
「井を塞ぎ竈を平らぐ」とは、このような意味です。
| 「井を塞ぎ竈を平らぐ」の意味 |
| 決死の覚悟を表すときのことば |
その2(前門の虎後門の狼)
「前門の虎後門の狼」とは、このような意味です。
| 「前門の虎後門の狼」の意味 |
| 1つの災難を逃れても、別の災難にあうというたとえ |
その3(船を沈め釜を破る)
「船を沈め釜を破る」とは、船を沈め、釜を壊して退路を断つことです。
| 「船を沈め釜を破る」の意味 |
| 決死の覚悟で物事に取り組むこと |
その4(釜を破り船を沈む)
「釜を破り船を沈む」とは、釜を壊し、船を沈め退路を断つことです。
| 「釜を破り船を沈む」の意味 |
| 決死の覚悟で物事に取り組むこと |
その5(糧を捨てて船を沈む)
「糧を捨てて船を沈む」とは、食糧を捨て、生きて帰らない覚悟で戦うことです。
| 「糧を捨てて船を沈む」の意味 |
| 決死の覚悟で物事に取り組むこと |
