

| 【本末転倒】の意味 |
| ・物事の大切なことと、些細なことが逆転すること ・どうでもよいことにこだわり、大切なことを疎かにしてしまうこと |
| 【本末転倒】の由来 |
| 鎌倉時代、仏教が一般庶民に広まったことで「本山の寺院」と「末端の寺院」の力関係の立場が逆転したことに由来 |
| 【本末転倒】の5つの類語 | ||
| 冠履転倒 | 釈根灌枝 | 捨根注枝 |
| 舎本逐末 | 主客転倒 | 削足適履 |
| 【本末転倒】と似た意味の4つのことわざ | |||
| 木を見て森を見ず | 靴を度りて足を削る | 角を矯めて牛を殺す | 葉を欠いて根を断つ |
| 【本末転倒】の5つの対義語・反対語 | ||
| 徹頭徹尾 | 首尾一貫 | 終始一貫 |
| 脈絡通徹 | 初志貫徹 | |

四字熟語【本末転倒】の意味・読み方とは/わかりやすく解説
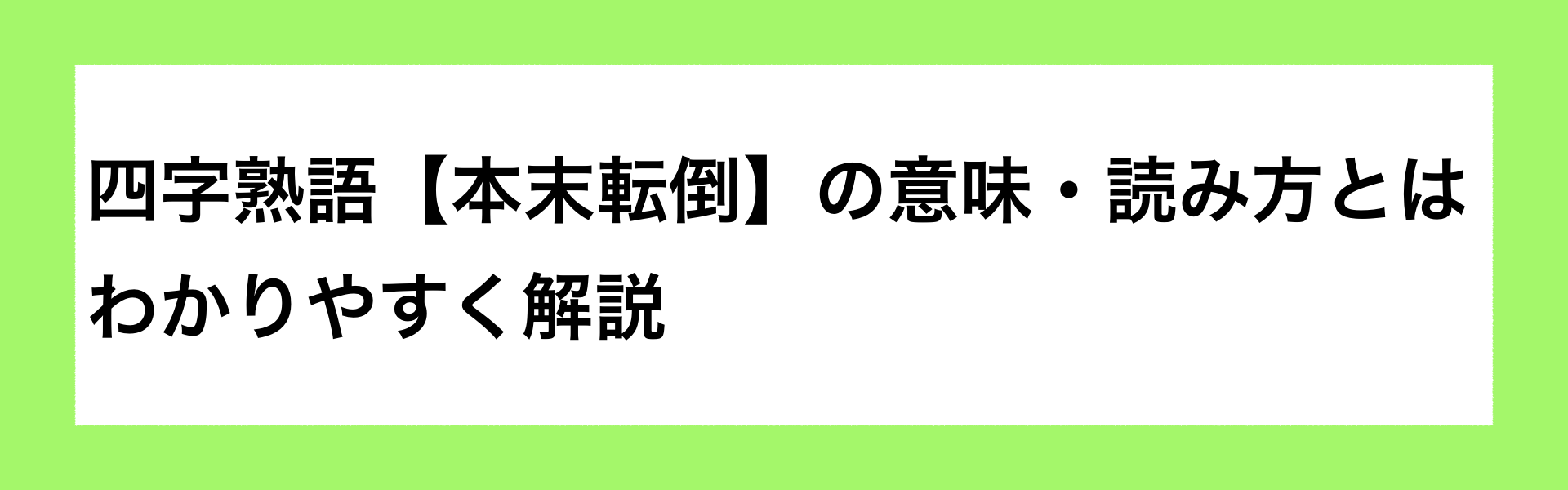
【本末転倒】の意味とは/わかりやすく解説
【本末転倒】とは、物事の大切なことと、些細なことが逆転することです。
| ・物事の大切なことと、些細なことが逆転すること ・どうでもよいことにこだわり、大切なことを疎かにしてしまうこと |
「本末」の意味とは
【本末転倒】の「本末」とはこのような意味です。
| 大切なことと、些細なこと |
「転倒」の意味とは
【本末転倒】の「転倒」とはこのような意味です。
| ・ひっくり返すこと ・逆さまになること |
【本末転倒】の読み方とは
「本末転倒」は「ほんまつてんとう」と読みます。
「転」を「顛」とし、「本末顛倒」と書かれることがありますが、正しい表現です。
【本末転倒】の語源は鎌倉時代の仏教寺院に由来している
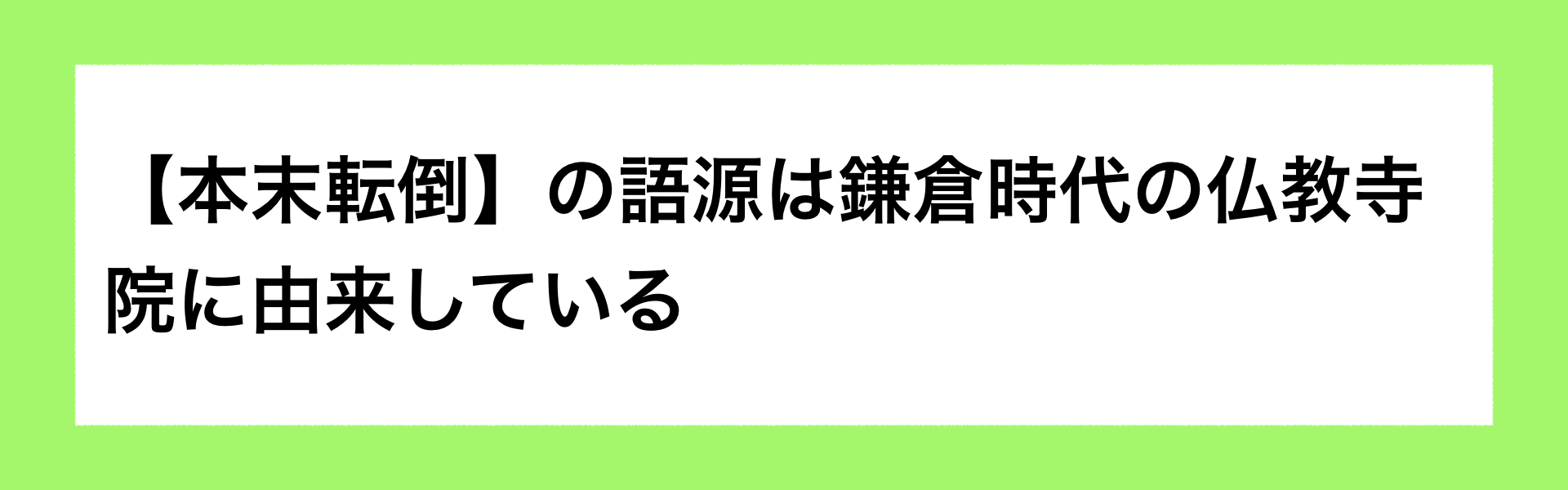
仏教の寺院制度
宗派にもよりますが、仏教寺院には、本山の寺院と末端の寺院が存在します。
寺院を統制するために江戸時代に作られた「本末制度」では、「本山の寺院」が「末端の寺院」を取り締まります。
| 本山の寺院 | 宗派の中心となって、末端の寺院を取り締まる寺院 |
| 末端の寺院 | 本山の支配下にある寺院 |
語源は寺院の立場の逆転
鎌倉時代まで寺院の力関係は、「本山の寺院>末端の寺院」
仏教は、天皇や貴族など高貴な身分の者のために存在し、「本山の寺院」は、天皇や貴族によって権力を維持していました。
鎌倉時代になると一般庶民にも仏教が広まり、「末端の寺院」も力を持つようになります。
その結果、力関係が「本山の寺院<末端の寺院」と変化します。
このように寺院の立場が変わったことが転じて、「大切なことと、些細なことが逆転する」という意味で「本末転倒」が使われるようになりました。
| 本末転倒: 本山の寺院と 末端の寺院の力関係が逆転する | |
| 鎌倉時代以前 | 鎌倉時代以降 |
| 本山の寺院が末端の寺院を支配する | 本山の寺院よりも末端の寺院が力を持つ |
| 本山の寺院>末端の寺院 | 本山の寺院 <末端の寺院 |
【本末転倒】の使い方・例文
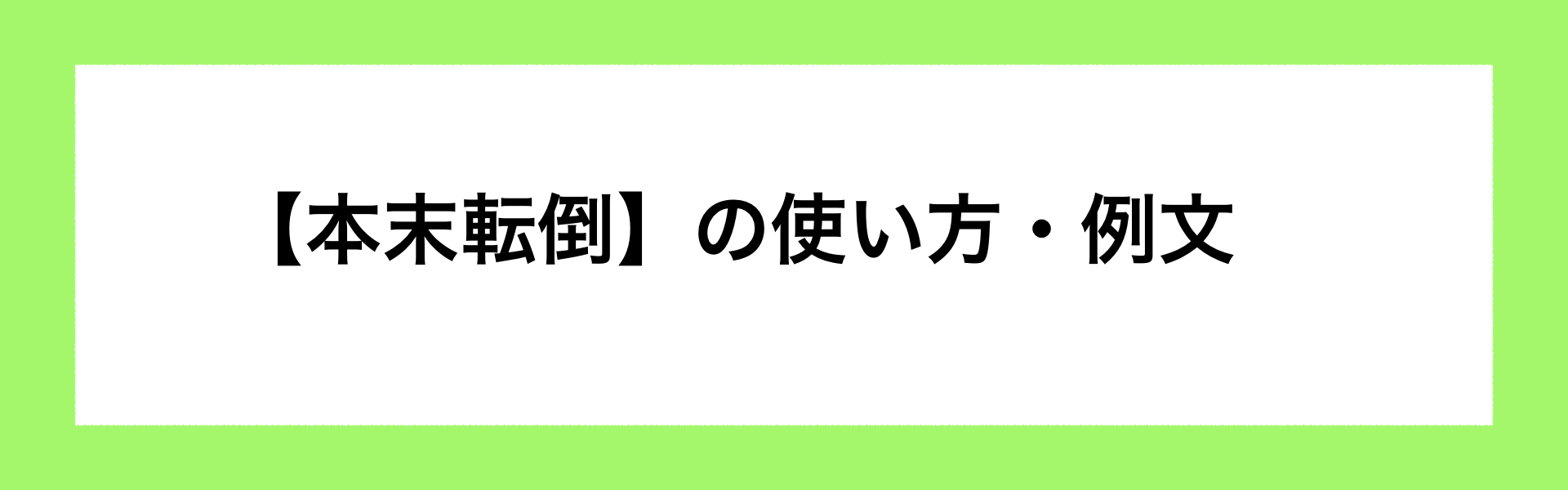
使い方
「本末転倒」は、このようなときに使われます。
| ・行ったことが逆効果だったり、よくない結果になってしまったとき ・どうでもよいことにこだわり、大切なことを疎かにしてしまったとき |
物事を間違えてしまったときなど、ネガティブな場面で使われることが多いです。
例文
| 例文1 | 大学に入学したのに、勉強を疎かにアルバイトばかりしているとは、本末転倒だ |
| 例文2 | 健康のためにランニングを始めたが、膝を痛めてしまっては本末転倒だ |
| 例文3 | ダイエットで食事の量を減らしているのに、スイーツを食べては本末転倒だ |
| 例文4 | 身体を休めるために休暇を取ったのに、自宅で仕事をしていては本末転倒だ |
| 例文5 | 業務の効率化のために新しい機械を導入したが、トラブルが頻繁に起きているようでは本末転倒だ |
【本末転倒】の類語・言い換え

その1(冠履転倒・かんりてんとう)
「冠履転倒」とは、このような意味です。
| 地位や立場などの、上下の順番が乱れること、逆になること |
「冠履」はかんむりと靴という意味があり、転じて、地位や立場の上位・下位を表します。
その2(釈根灌枝・しゃくこんかんし)
「釈根灌枝」とは、とは、このような意味です。
| 物事の些細なことに気を取られて、大切なことを忘れること |
「釈根」は根を捨てる、「灌枝」は枝に水を注ぎかけるという意味があります。
枝の根に水をやらず、枝に注ぎかけるという意味が転じたものです。
その3(捨根注枝・しゃこんちゅうし)
「捨根注枝」とは、とは、このような意味です。
| 物事の些細なことに気を取られて、大切なことを忘れること |
「捨根」は根を捨てる、「注枝」は枝に水を注ぎかけるという意味があります。
「釈根灌枝」と同じ意味です。
その4(舎本逐末・しゃほんちくまつ)
「舎本逐末」とは、とは、このような意味です。
| 物事の根本となる大切なことを疎かにして、必要ないことを大切にすること |
「舎」は捨てる、「本」は根本、「逐末」はつまらないものを追い求めるという意味があります。
「本もとを舎すてて末すえを逐おう」と訓読をすることもあります。
その5(主客転倒・しゅかくてんとう)
「主客転倒」とは、とは、このような意味です。
| ・主要な事と従属的な物事の立場が逆になること ・物事の順序や立場が逆になること |
「主客」の主人と客人の意味が転じて、主要な物事と従属的な物事という意味になります。
「主客が入れ替わる」と訓読をすることもあります。
その6(削足適履・さくそくてきり)
「削足適履」とは、とは、このような意味です。
| ・些細なことに気を取られて、大切なことを忘れること ・根本となる大切なことと、些細なことを取り違えて、無理に折り合いをつけること |
靴の大きさに合わせて自分の足を削るという意味が転じて、根本となる大切なことを忘れるという意味になります。
「足あしを削けずりて履くつに適てきせしむ」と訓読をすることもあります。
【本末転倒】と似た意味のことわざ
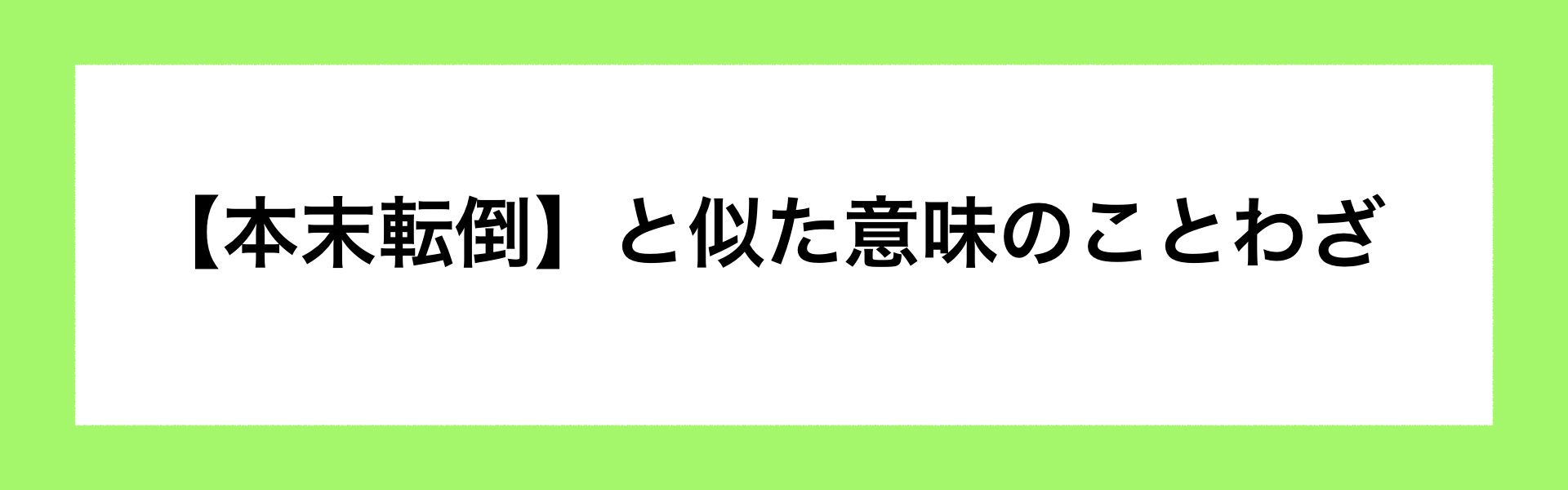
その1(木を見て森を見ず・きをみてもりをみず)
「木を見て森を見ず」とは、とは、このような意味です。
| 些細なことにこだわりすぎて、物事の本質や全体を見失うこと |
一本一本の木だけを見ていても、森全体は見えないことから転じています。
その2(靴を度りて足を削る・くつをはかりてあしをけずる)
「靴を度りて足を削る」とは、とは、このような意味です。
| ・些細なことに気を取られて、大切なことを忘れること ・根本となる大切なことと、些細なことを取り違えて、無理に折り合いをつけること |
靴の大きさに合わせて自分の足を削るという意味が転じて、根本となる大切なことを忘れるという意味になります。
「削足適履」と四字熟語で表記することもあります。
その3(角を矯めて牛を殺す・つのをためてうしをころす)
「角を矯めて牛を殺す」とは、とは、このような意味です。
| 小さな欠点を直そうとして、結果的に全体を駄目にしてしまうこと |
曲がった牛の角をまっすぐにしようとすると、牛が死んでしまうことがあることから転じています。
その4(葉を欠いて根を断つ・はをかいてねをたつ)
「葉を欠いて根を断つ」とは、とは、このような意味です。
| 小さな欠点を除こうとして、結果的に根本の大切なことを駄目にしてしまうこと |
余分は枝葉を取り除こうとして、大切な根を駄目にしてしまうことから転じています。
【本末転倒】の英語表現
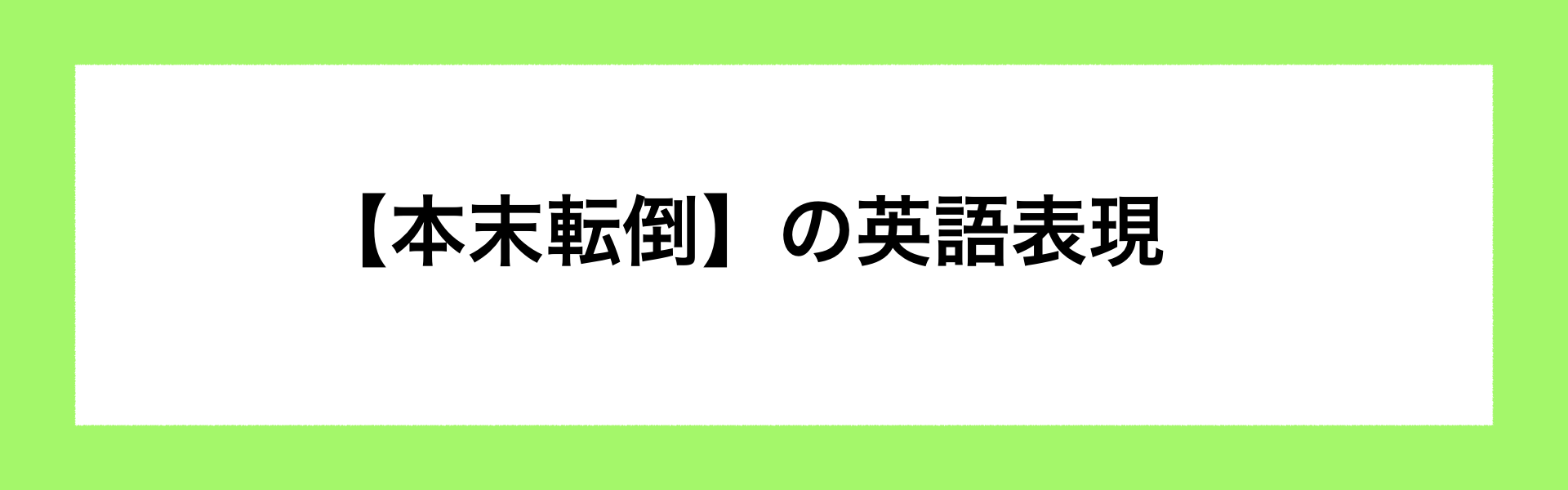
その1(put the cart before the horse)
| 英語 | 日本語 |
| cart | 荷馬車 |
| put | 置く |
「put the cart before the horse」を直訳すると「馬の前に荷馬車を置く」です。
馬と荷馬車の順が逆になっていることから「本末転倒」の英語表現として使うことができます。
その2(misplace his priorities)
| 英語 | 日本語 |
| misplace | 置き間違える・置き忘れる |
| priorities | 優先事項・優先順位 |
「misplace his priorities」を直訳すると「優先事項を置き間違える」となります。
優先事項を間違えるという意味から「本末転倒」の英語表現として使うことができます。
その3(have one’s priorities wrong)
| 英語 | 日本語 |
| priorities | 優先事項・優先順位 |
| wrong | 間違い |
「have one’s priorities wrong」で「優先事項を置き間違える」という意味になります。
「本末転倒」の英語表現として使うことができます。
その4(get his priorities backwards)
| 英語 | 日本語 |
| priorities | 優先事項・優先順位 |
| backwards | 後方・後ろ |
「get his priorities backwards」で「優先事項が逆」という意味になります。
「本末転倒」の英語表現として使うことができます。
その5(be not doing what he is supposed to do)
「be not doing what he is supposed to do」で「やるべきことをやっていない」という意味になります。
「本末転倒」の英語表現として使うことができます。
【本末転倒】の対義語・反対語

最初から最後まで大切なことを忘れずに、物事を続けるという意味合いの言葉です。
その1(徹頭徹尾・てっとうてつび)
「徹頭徹尾」とは、とは、このような意味です。
| 最初から最後まで考えを貫くこと |
その2(首尾一貫・しゅびいっかん)
「首尾一貫」とは、とは、このような意味です。
| 最初から最後まで1つの考えや態度を貫くこと |
その3(終始一貫・しゅうしいっかん)
「終始一貫」とは、とは、このような意味です。
| 最初から最後まで変わらないこと |
その4(脈絡通徹・みゃくらくつうてつ)
「脈絡通徹」とは、とは、このような意味です。
| 最初から最後まで一貫していて、食い違いがなく意味が理解しやすいこと |
その5(初志貫徹・しょしかんてつ)
「初志貫徹」とは、とは、このような意味です。
| 最初に決めた志を、最後まで貫き通すこと |
