「おはぎ」の表面に小豆の皮が浮かぶ様子が、萩の花に似ていることから名前がつけられました。

| 【おはぎ】の由来・語源 |
| 秋の七草の一つである「萩の花」に由来。 「おはぎ」の表面に小豆の皮が浮かぶ様子が、萩の花に似ていることから名前がつけられた。 |

| 【おはぎ】の意味 |
| もち米とうるち米を混ぜて炊いて丸めたものに、餡をまぶしたもの |

| 【おはぎ】の漢字表記 |
| 御萩 |

| 【おはぎ】と「ぼた餅」の違い |
| 「おはぎ」と「ぼた餅」は同じものである。 作る時期によって季節の花の名前がつけられたため、呼び名が違う。 |

| 【おはぎ】3つの別名 | ||
| ぼた餅 | 夜船 | 北窓 |

| 【おはぎ】をお盆やお彼岸に食べる理由 |
| 魔除けや五穀豊穣の効果があると考えられていたため |


【おはぎ】の由来・語源


【おはぎ】は、秋の七草の一つ「萩の花」に由来しています。
「おはぎ」の表面に小豆の皮が浮かぶ様子が、萩の花に似ていることから「萩餅」と呼ばれるようになりました。
「萩餅」→丁寧になり「お萩餅」→「おはぎ」と呼び名が変化していきました。

これが「萩の花」ね。


【おはぎ】の意味と漢字表記
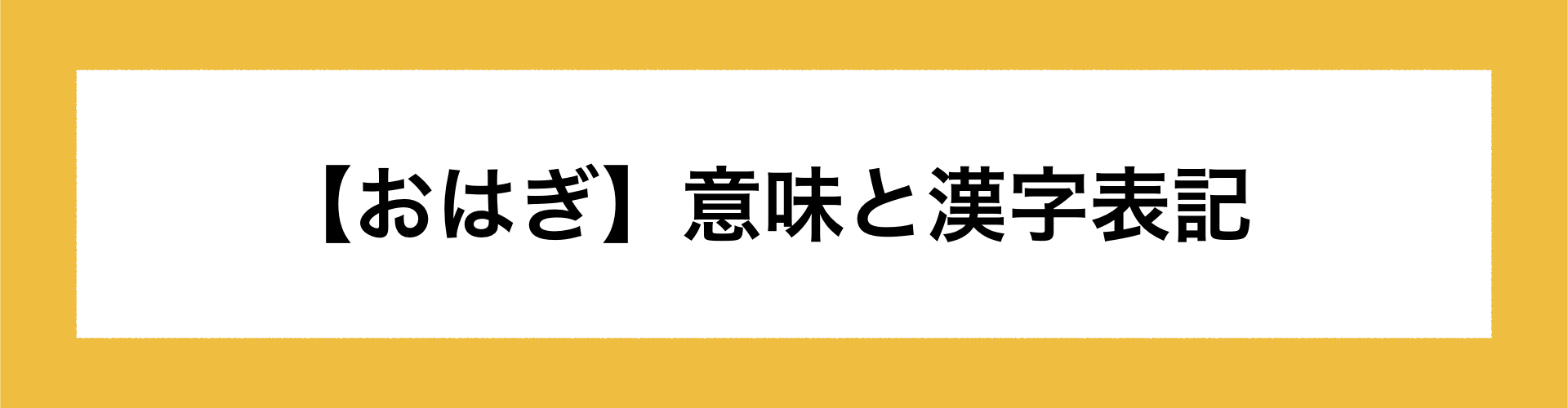
意味と漢字表記
- ❶意味
- ❷漢字表記

【おはぎ】の意味
「おはぎ」は、もち米とうるち米を混ぜて炊いて丸めたものに、餡をまぶしたものです。
| 【おはぎ】の意味 |
| もち米とうるち米を混ぜて炊いて丸めたものに、餡をまぶしたもの |
「おはぎ」は、秋に食べられる物です。
秋に収穫したばかりで皮まで柔らかい小豆で作られるため、粒餡になります。
「おはぎ」は女房詞(にょうぼうことば)で、室町時代初期頃から宮中に使える女官が使い始めた隠語表現です。
【おはぎ】の漢字表記
「おはぎ」を漢字で書くと「御萩」です。
| 【おはぎ】の漢字表記 |
| 御萩 |
正しい使い方ではありませんが、文学作品では「牡丹餅」が「おはぎ」として使われています。
例えば、泉鏡花(いずみきょうか)の小説(婦系図・おんなけいず)などでです。
【おはぎ】と「ぼた餅」の違い
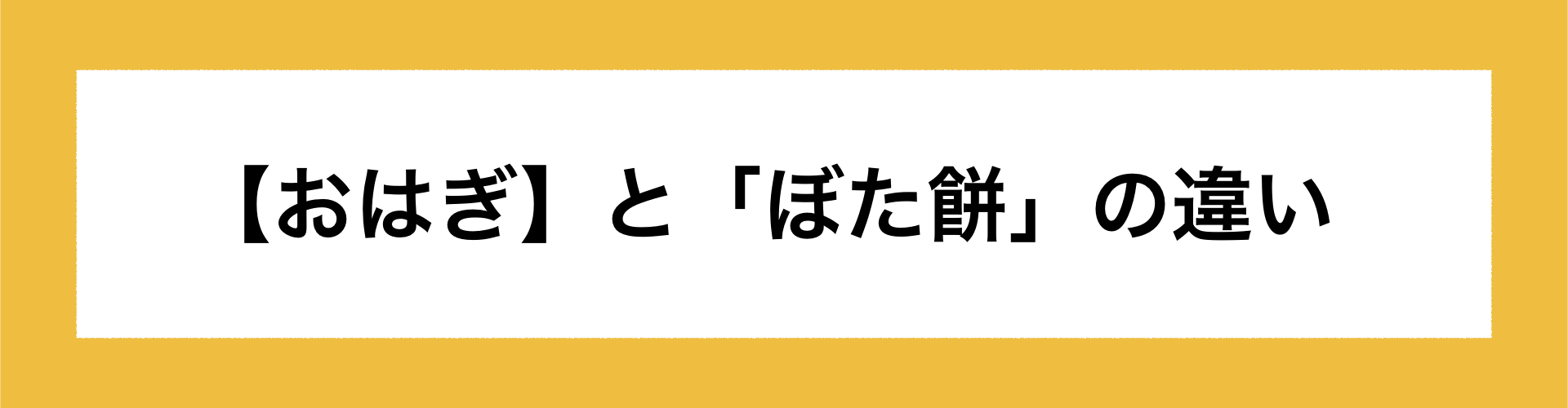
【おはぎ】と「ぼた餅」の違い
- ❶【おはぎ】と「ぼた餅」の違い
- ❷きな粉の【おはぎ】
- ❸地域で異なる「おはぎ」の種類
【おはぎ】と「ぼた餅」の違い
「おはぎ」と「ぼた餅」は、同じものです。
なぜ呼び名が違うのかというと、作る季節が違うからです。
昔から、小豆の赤は魔除けの効果があり縁起が良いとされ、「おはぎ(ぼた餅)」はお彼岸で供えていました。
お彼岸は春と秋の年に2回あります。
春は「牡丹」、秋は「萩の花」と、それぞれの季節の花に見立てたため「おはぎ」「ぼた餅」と名前が違うのです。

きな粉の【おはぎ】
本来「おはぎ」とは、もち米とうるち米を混ぜて炊いて丸めたものに、餡をまぶした物のことです。
現在では「きな粉」をまぶしたものも「おはぎ」と呼ばれています。
「おはぎ」の定番は、「小豆ときな粉」というのが一般的です。
地域で異なる「おはぎ」の種類
一般的には「小豆・きな粉」で作られたものを「おはぎ」と言いますが、地域により種類は様々です。
地域によっては、「黒ごま」なども定番となっています。
| 東日本 | 黒ごま |
| 西日本 | 青のり |
| 東北 | ずんだ |
【おはぎ】3つの別名と名前の由来
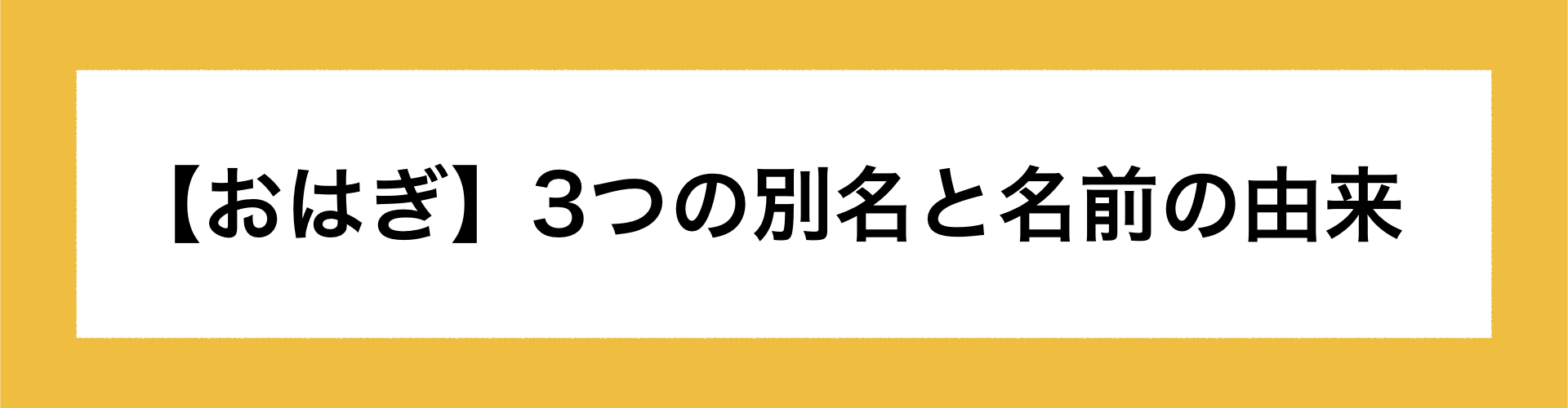
3つの別名と名前の由来
- ❶ぼた餅
- ❷夜船
- ❸北窓

「おはぎ」には、3つの別名があり、季節によって呼び方が違います。
その1(ぼた餅・牡丹餅)
「ぼた餅」は「おはぎ」と同様の食べ物です。
春に食べられる物を「ぼた餅」と言います。
「ぼたもち」の表面の小豆の粒が、牡丹の花に似ていることから「ぼたんもち」と呼ばれていました。
それが次第に「ぼたん餅」→「ぼた餅」と変化しました。
その2(夜船・よふね)
「夜船」も「おはぎ」と同様の食べ物です。
夏に食べられる物を「夜船」と言います。
「おはぎ」はお米とうるち米を、すりこぎで潰して作ります。
つまり、お餅のように杵と臼を使って搗くのではないので「搗き(つき)知らず」です。
夜は暗いので船がいつ着いたのか分からない「着き知らず」に似ていることから「夜船」と呼ばれるようになりました。
その3(北窓・きたまど)
「北窓」も「おはぎ」と同様の食べ物です。
冬に食べられる物を「北窓」と言います。
北側の窓からは月が見えないので「月知らず」です。
搗くことをしない「搗き(つき)知らず」が「月知らず」に似ていることから「北窓」と呼ばれるようになりました。
【おはぎ】はいつ食べるのか/お盆やお彼岸に食べる理由とは
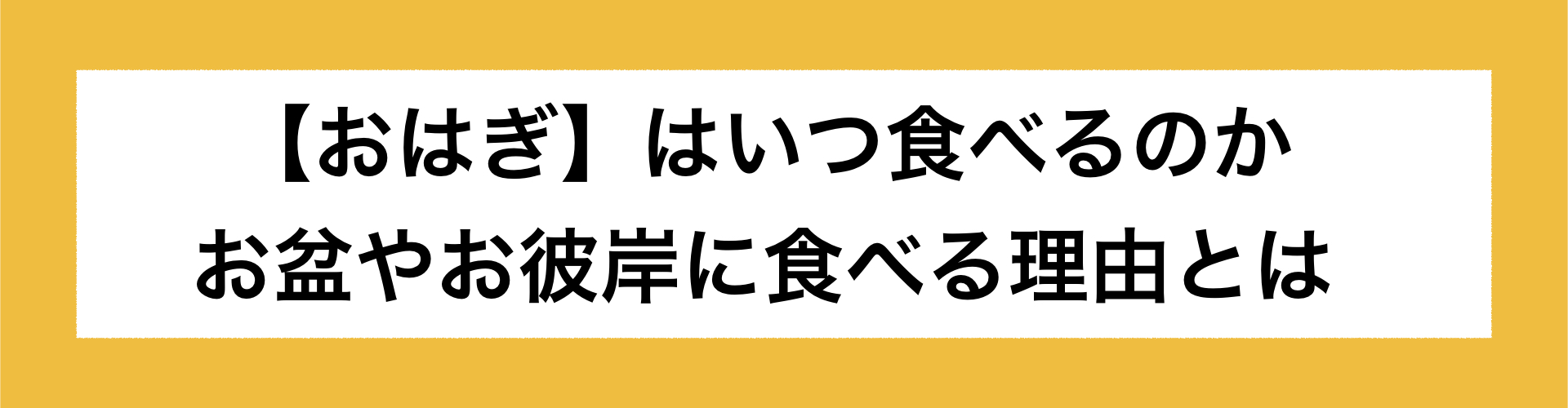
お盆やお彼岸に【おはぎ】を食べる理由とは
- ❶【おはぎ】をお盆やお彼岸に食べる理由とは
- ❷お盆の期間
- ❸彼岸の期間

【おはぎ】をお盆やお彼岸に食べる理由とは
「おはぎ」をお盆やお彼岸に食べるのは、魔除けや五穀豊穣が理由です。
昔から、赤色には魔除け効果が、米には五穀豊穣の効果があると考えられていました。
その両方を兼ね備えた「おはぎ」は、お盆やお彼岸にご先祖様にお供えされるようになりました。
また、「お米・小豆」2つのものを合わせることで、ご先祖様と自分たちの心を合わせるという意味も込められているそうです。
お盆の期間
お盆の時期は、一般的に8月13日~16日の4日間ですが、地域によって少し異なります。
| 7月13日~16日 (新盆) |
東京都、静岡県、石川県 |
| 8月13日~16日 (旧盆・月遅れ盆) |
上記以外の地域 |
お彼岸の期間
お彼岸は「春彼岸」と「秋彼岸」の年2回です。
それぞれ「春分の日」と「秋分の日」の前後3日を合わせた7日間です。
「春分の日」「秋分の日」を「彼岸の中日」と言い、3日前を「彼岸入り」、3日後を「彼岸明け」と言います。
| 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 |
| 彼岸入り | (春分の日) 彼岸の中日 |
彼岸明け |
【おはぎ】の有名店
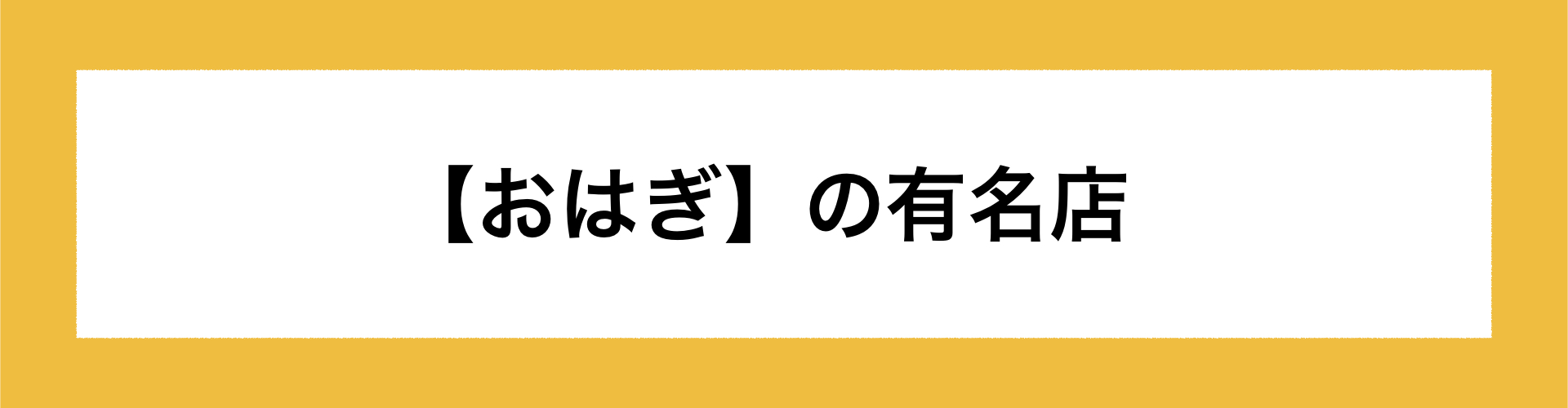

ヤオコー
ヤオコーは埼玉県を中心に展開しているスーパーマーケットです。
ヤオコーの「おはぎ」は人気で「マツコの知らない世界」などテレビでも度々紹介されています。
おはぎは、小豆の美味しさを感じられるよう甘さは控えめ。
ひとつひとつ手で握って作られていて、社内の資格試験をクリアした人でなければ、おはぎを握ることはできないそうです。
おはぎの丹波屋
おはぎの丹波屋は、大阪を中心に展開しているお店です。
おはぎやお饅頭など、ひとつひとつて手作りしている懐かしい味わいが人気の秘密です。
原材料もこだわり、北海道十勝産の大粒小豆と、国産の一級品のもち米を使っているそうです。
サザエ食品株式会社
サザエ食品株式会社は、札幌に本社があり、北海道に展開しているお店です。
おはぎを中心に、和菓子やスイーツ・おにぎりなどを販売しています。
おはぎの餡は十勝産の小豆と日高山脈の札内川の水を使用し、職人さんが丹精込めて作っています。
餡のみの販売もあり、お取り寄せも可能です。
タケノとおはぎ(桜新町)
タケノとおはぎは、東京都世田谷区桜新町にある、行列のできる人気店です。
彩り豊かで見た目が美しく、上生菓子と融合したおはぎは上品です。
わっぱや桐箱におはぎを入れてくれたり、ココナッツレモンピール、ナップなど、珍しい食材を使っているのも楽しいです。
おはぎと大福
おはぎと大福は、東京都の神楽坂にある、おはぎと大福のお店です。
シンプルで上品な甘さのおはぎで、もち米の中にシソが練り込まれています。
粒餡やきな粉などの定番から、日によってはくるみや落花生、玄米茶など珍しい餡も!
小ぶりで可愛らしく上品な見た目なので、手土産にもぴったりです。



