
知りたい項目をクリックして下さい。
| ①名前の由来・語源 |
| ②別名 |
| ③昔の名前 |
| ④沖縄の珍しい苗字 |
| ⑤沖縄の読み方が難しい地名 |
| ⑥沖縄の美味しい食べ物 |
| ⑦沖縄の方言 |
| ⑧沖縄のシンボル |
| 【沖縄県】由来・語源の有力説 |
| 「沖合いの漁場」説 沖縄の「おき」は、岸から遠く離れた海上。「なわ」は、魚場という意味。 この2つの言葉から、沖縄県という地名がつけられた。 |

| 【沖縄県】3つの別名 | ||
| 琉球 | 大琉球 | うちなー |

| 【沖縄県】昔の名前 | ||
| オキナパ | オキナファ | オキナハ |
| 阿児奈波島(あこなはしま) | 琉球(りゅうきゅう) | |

| 【沖縄県】美味しい食べ物 | ||
| 沖縄そば/ソーキそば | タコライス | ゴーヤーチャンプルー |
| 沖縄天ぷら | 沖縄ぜんざい | A&W・エンダー |

| 【沖縄県】のシンボル | |
| 沖縄県の木 | 琉球松(りゅうきゅうまつ) |
| 沖縄県の花 | デイゴ |
| 沖縄県の鳥 | ノグチゲラ |
| 沖縄県の魚 | タカサゴ(グルクン) |


【沖縄県】3つの由来・語源
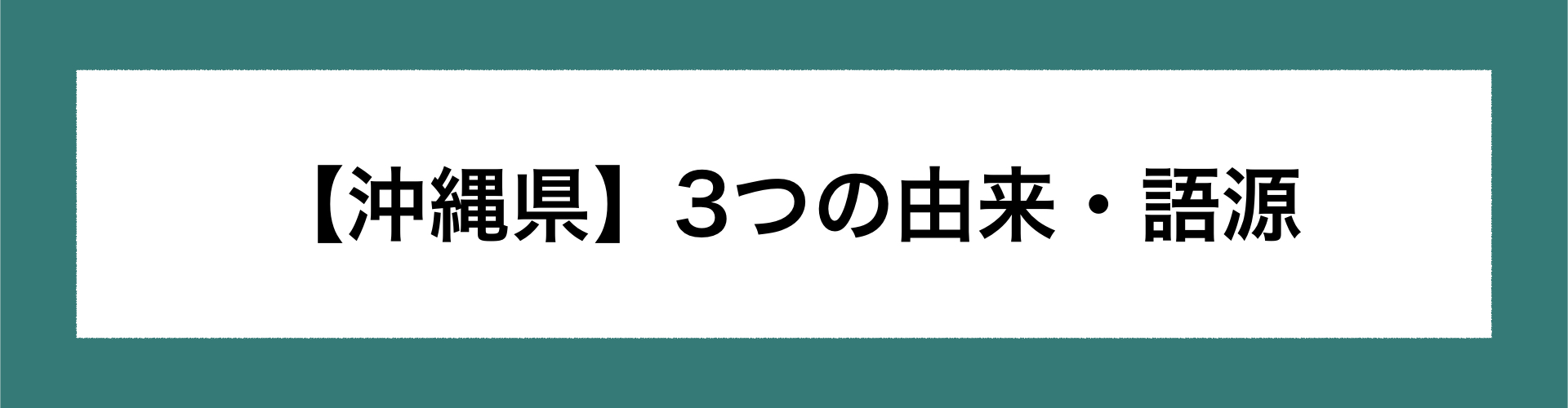

由来・語源
- ❶「沖合いの漁場」説
- ❷「沖にある場所」説
- ❸「釣り縄を置いた場所」説
【沖縄県】の名前には、3つの由来・語源がありますが、定説はありません。
「沖合いの漁場」説が有力とされています。
その1(「沖合いの漁場」説)
「沖縄県」の名前の語源は、「沖合いの漁場」の意味に由来する説です。
「おき」「なは(なわ)」は、それぞれ次のような意味があります。
| 沖(おき) | 岸から遠く離れた海上・湖上 |
| な | 魚 |
| は | 場 |
| なは(なわ) | 魚場(漁場) |
このような意味の言葉から「沖縄県」という名前になりました。
沖縄の「なわ」と、県庁所在地である「那覇」の語源は同じだと言われています。
そのため、「沖合いの漁場」説が有力とされています。
その2(「沖にある場所」説)
「沖縄県」の名前の語源は、「沖にある場所」の意味に由来する説です。
「おき」「なは(なわ)」は、それぞれ次のような意味があります。
| 沖(おき) | 岸から遠く離れた海上・湖上 |
| なは | 場所・島 |
このような意味の言葉から「沖縄県」という名前になりました。
その3(「釣り縄を置いた場所」説)
「沖縄県」の名前の語源は、「釣り縄を置いた場所」の意味に由来する説です。
1470年~76年の尚円王の時代、泊村に大安里という者がいました。
大安里は、那覇の浮縄御嶽(おきなわうたき・うちなーうたき)近くの川岸に漁のため縄を仕掛け、それを置縄と呼んでいました。
それが御嶽の名前となり(浮縄)、島の名前(沖縄)にもなりました。
【沖縄県】3つの別名
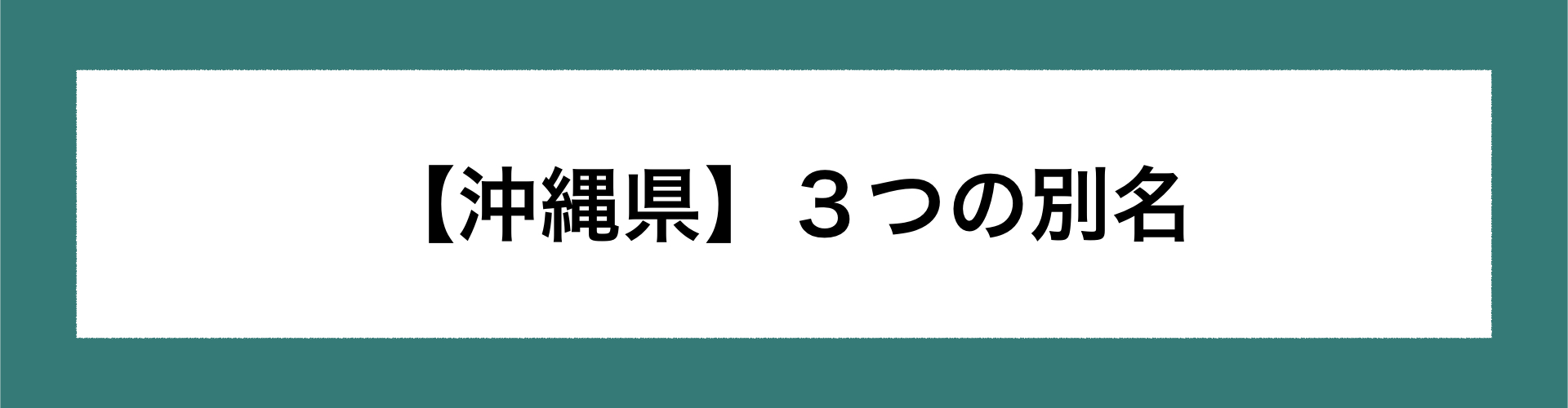

3つの別名
| 琉球 | 大琉球 | うちなー |
「沖縄県」には、3つの別名があります。
| 琉球 (りゅうきゅう) |
琉球は沖縄の昔の呼び名だが、別名としても使われる |
| 大琉球 (だいりゅうきゅう) |
中国の呼び名で、沖縄を大琉球、台湾を小琉球と区別している |
| うちなー | 沖縄の方言で「沖縄県」の意味 |
【沖縄県】の昔の名前
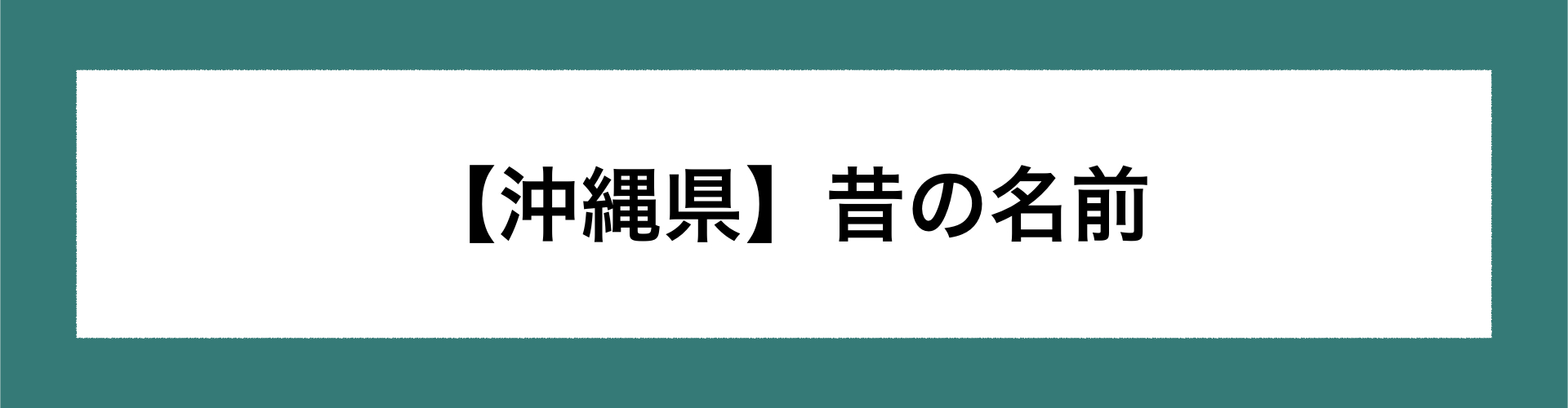

昔の名前
- ❶オキナパ・オキナファ・オキナハ
- ❷阿児奈波嶋(あこなはしま)
- ❸琉球(りゅうきゅう)
- ❹【沖縄県】の離島の昔の名前
その1(オキナパ・オキナファ・オキナハ)
縄文時代・弥生時代は、「オキナパ・オキナファ・オキナハ」という呼び名が使われていました。
その後、琉球など別の名前が使われますが、一般庶民の間では「オキナパ・オキナファ・オキナハ・ウチナー」がずっと使われていたそうです。
その2(阿児奈波嶋・あこなはしま/あこなわじま)
779年(奈良時代)に成立した鑑真 (がんじん) の「唐大和上東征伝(とうだいわじょうとうせいでん)」という伝記があります。
唐大和上東征伝には、753年(天平勝宝5年)に遣唐使が「阿児奈波島(あこなはしま/あこなわじま)」に到着したという記載があります。
この「阿児奈波嶋」というのは、沖縄県のことを指していたとされています。
その3(琉球・りゅうきゅう)
「琉球(流求)」は中国での呼称です。
656年に書かれた中国の歴史書「隋書(ずいしょ)」では、「琉求(りゅうきゅう)」という名前が使われています。
日本でも沖縄の正式名称として、1429年から1879年まで使われていました。
明治時代以降は、「沖縄」という名称が一般的に使われるようになりました。
【沖縄県】の離島の昔の名前
沖縄県には100を超える離島がありますが、昔は違う名前で呼ばれていたと考えられています。
例えば、石垣島や久米島、宮古島です。
| 現在の名前 | 昔の名前 |
| 石垣島 | 信覚(しがき) |
| 久米島 | 球美(くみ) |
| 宮古島 | 庇郎喇(ひらら) |
「琉球」の2つの由来・語源
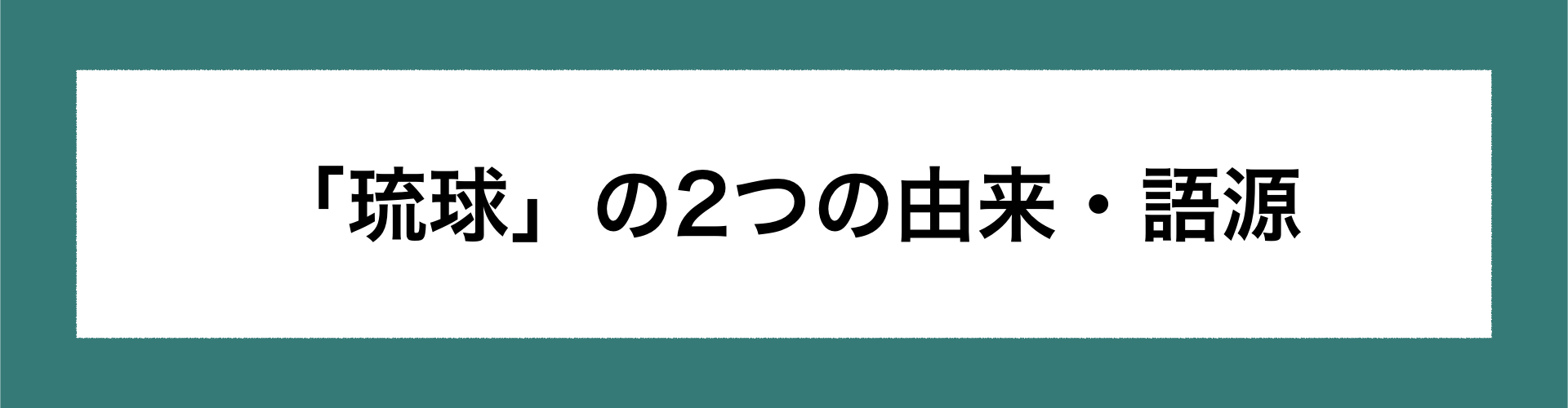

「琉球」の2つの由来・語源
- ❶「蛟(みずち)」説
- ❷「魚(うお)の国」説
その1(「蛟(みずち)」説)
「琉球」は、「蛟(みずち)」に由来するという説です。
「蛟」は、水中に住む伝説上の生物で、体は蛇に似て長く、角と4本の足があります。
島の形が「蛟」に似ていたため、「琉蛟(りうこう)」と名が付けられました。
それが更に変化して「琉球(りゅうきゅう)」となりました。
その2(「魚(うお)の国」説)
沖縄県は海に囲まれているため、魚がたくさん取れる、とてもいい漁場があります。
その為、「魚(うお)の国」と呼ばれていました。
「魚(うお)の国」を中国人が聞いたときに「りゅうきゅう」と聞き間違えたため、そのまま「琉球」となりました。
【沖縄県】に多い珍しい苗字
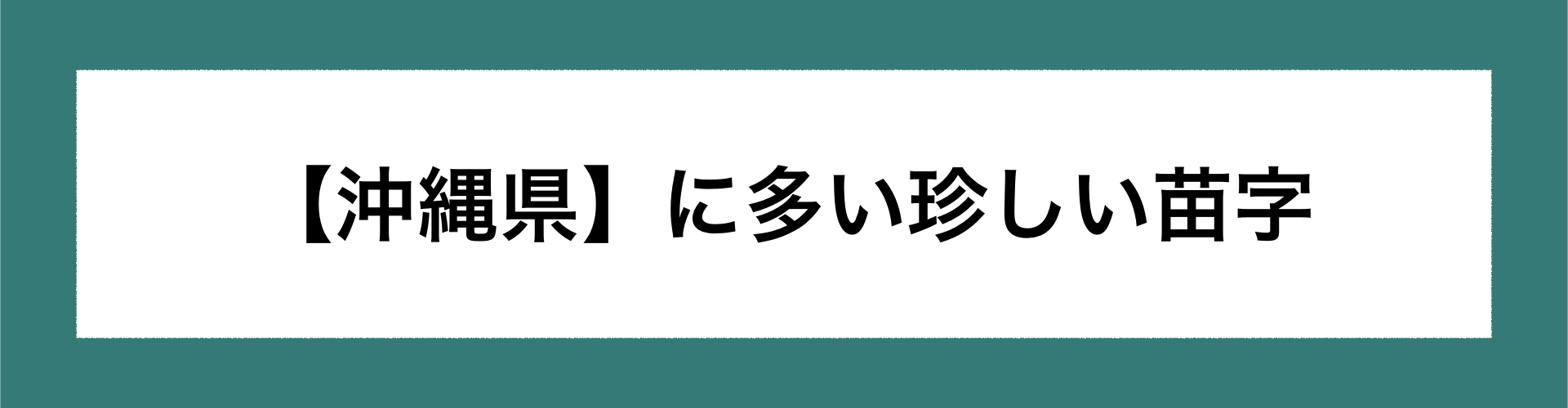

珍しい名字
- ❶珍しい苗字
- ❷珍しい苗字が多い理由
【沖縄県】珍しい苗字
沖縄県には、読み方が難しく珍しい苗字が多いです。
| 沖縄県に多い苗字 | |
| 1位 | 比嘉(ひが/ひか/ひよし/ひき/びか/ひよい) |
| 2位 | 金城(きんじょう/かねしろ/かなしろ/かなき/かねぎ/かなぐすく/きんしょう/きんき/こんじょう/かなうすく/かなぐしこ/かなじょう/なぐしく/かねき/かねくすく/かねぐすく/かねじょう/かなぐす/かなくすく/かなぎ) |
| 3位 | 大城(おおしろ/おおき/おおぎ/だいじょう/おしろ/おうしろ/だいき/たいき/たいせい/おおぐすく/おぐすく) |
| 4位 | 宮城(みやぎ/みやしろ/みやき/みやぐすく/みやじょう/みやんじょう/みやのじょう) |
| 5位 | 新垣(あらかき/しんがき/あらがき/にいがき/しんかき/あらかち) |
珍しい苗字が多い理由
沖縄県に珍しい苗字が多いのは、薩摩藩によって苗字を強制的に変えさせられたからです。
沖縄が琉球王国という独立国だった頃、薩摩藩に侵攻されていた時代がありました。
薩摩藩は1624年に、琉球に「大和めきたる名字の禁止令」を出し、日本らしい苗字の改名や文字の変更をさせました。
例えば「前田」→「真栄田」、「船越」は「富名腰」などです。
【沖縄県】の読みづらい地名
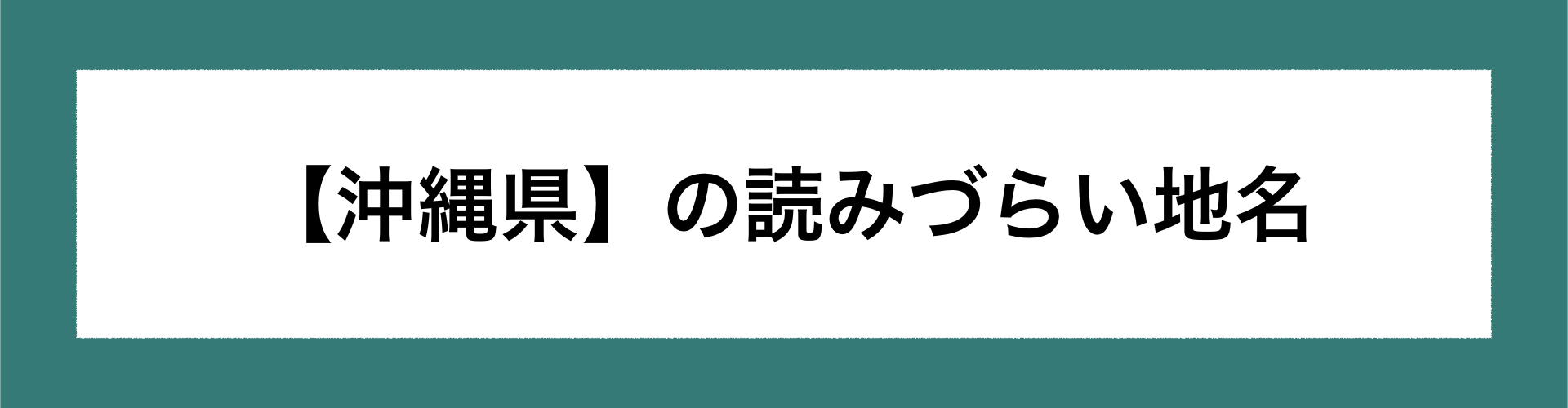

読みづらい地名
- ❶読みづらい地名
- ❷読みづらい地名が多い理由
【沖縄県】の読みづらい地名
| 沖縄県の読み方が難しい漢字 | ||
| 喜屋武(きゃん) | 北谷(ちゃたん) | 国頭村(くにがみそん) |
| 桃原(とうばる) | 具志頭(ぐしちゃん) | 世名城(よなぐすく) |
| 砂川(うるか) | 勢理客(じっちゃく) | 小谷(おこく) |
| 久得(くどう) | 真地(まあじ) | 為又(びいまた) |
| 勝連平安名(かつれんへんな) | 保栄茂(びん) | 東風平(こちんだ) |
読みづらい地名が多い理由
沖縄が琉球王国だった頃は、一般的に平仮名が使われていました。
1609年の侵攻で薩摩藩が沖縄を支配するようになり、漢字が使われるようになりました。
元々は平仮名表記の地名だったものに、意味を無視して漢字を当てはめたため、読み方が難しくなったようです。
【沖縄県】の美味しい食べ物(6選)


美味しい食べ物
| 沖縄そば/ソーキそば | タコライス | ゴーヤーチャンプルー |
| 沖縄天ぷら | 沖縄ぜんざい | A&W・エンダー |
その1(沖縄そば/ソーキそば)
「沖縄そば/ソーキそば」は、豚骨と鰹がベースのスープと、小麦粉を使った麺が特徴です。
トッピングは、三枚肉・スペアリブ・かまぼこ・紅生姜・ねぎが一般的です。
お店や地域によって、出汁やトッピングが少し異なるので、食べ比べするのがオススメです。
| 「沖縄そば」と「ソーキそば」の違い | |
| 沖縄そば | 三枚肉の煮込みがトッピングされている |
| ソーキそば | スペアリブ(ソーキ)がトッピングされている |
その2(タコライス)
「タコライス」は沖縄発祥の食べ物です。
メキシコ料理のタコスの具材を、ご飯にのせたものが「タコライス」。
スパイシーなひき肉・チーズ・野菜・サルサソースをのせた、沖縄を代表するB級グルメです。
その3(ゴーヤーチャンプルー)
「ゴーヤーチャンプルー」は、ゴーヤ・豆腐・豚肉・卵などを炒めたものです。
「チャンプルー」とは、沖縄の方言で「ごちゃまぜ」という意味。
沖縄料理の定番の一品です。
その4(沖縄天ぷら)
「沖縄天ぷら」は、味付きで厚めの衣が特徴です。
そのまま食べられるので、おやつやおつまみとして食べられることが多いです。
コンビニやスーパーはもちろん、天ぷらの専門店もあるほど、ソウルフードとして親しまれています。
その5(沖縄ぜんざい)
「沖縄ぜんざい」は、かき氷に、甘く煮た金時豆がトッピングされたスイーツです。
「ぜんざい」だと、お汁粉のような温かいものがイメージされますが、沖縄のぜんざいはちょっと違います。
南の島である、沖縄ならではのスイーツです。
その6(A&W・エンダー)
「エンダー」の愛称で親しまれる「A&W」は、国内では沖縄にしかないファストフード店です。
正式名称は「エイアンドダブリュ」
定番商品は「モッツァバーガー」とオリジナルドリンクの「ルートビア」ですが、他にもサンドウィッチやスイーツなどメニューが多いのが特徴です。
レトロなアメリカの雰囲気が感じられる、観光客にも人気のお店です。
【沖縄県】の方言
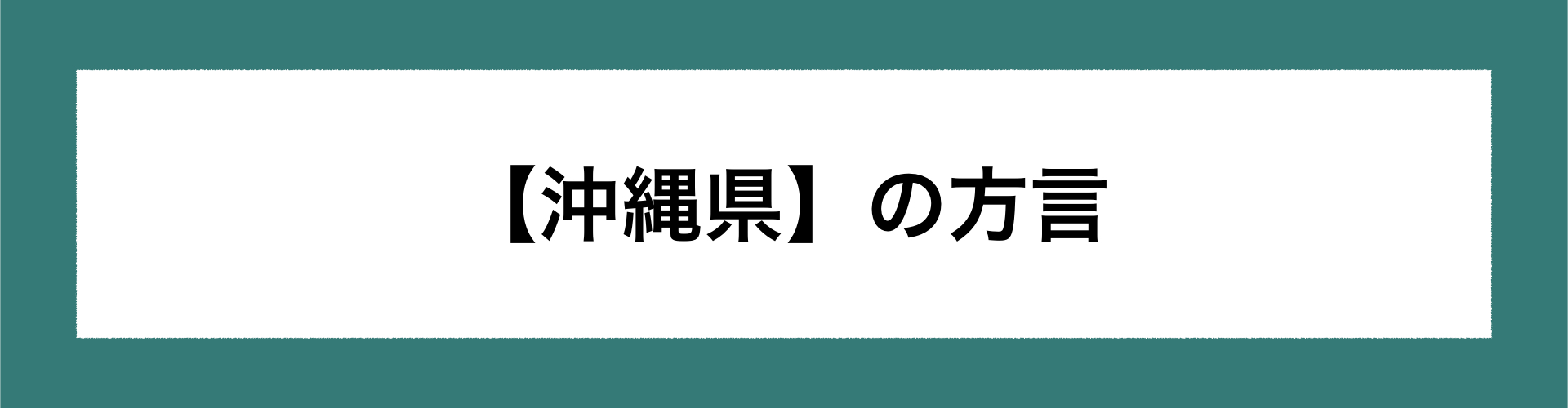

沖縄の方言は、面白いもの、かわいいものが多いです。
| なんくるないさ | なんとかなるさ |
| めんそーれ | ようこそ、いらっしゃい |
| ちばりよー | がんばれ! |
| ちゅらかーぎー | かわいい、美人 |
| ちむどんどん | 胸がドキドキする |
| ぬー | 何? |
| にふぇーでーびる | ありがとうございます |
| あちこーこー | 熱い、暑い |
| まーさん | 美味しい |
【沖縄県】のシンボル


【沖縄県】のシンボル
| 沖縄県の木 | 琉球松(りゅうきゅうまつ) |
| 沖縄県の花 | デイゴ |
| 沖縄県の鳥 | ノグチゲラ |
| 沖縄県の魚 | タカサゴ(グルクン) |
沖縄県の木「琉球松(りゅうきゅうまつ)」
沖縄の県木は「琉球松(りゅうきゅうまつ)」です。
琉球松はマツ科の針葉樹で、九州・沖縄に自生しています。
「琉球赤松・沖縄赤松」とも呼ばれ、沖縄の方言で「マーチ・マチ」、八重山の方言では「マチィ」と言います。
正月飾りなどの縁起ものに使われたり、島唄にもよく登場します。
沖縄県の花「デイゴ」
沖縄の県花は「デイゴ」です。
「デイゴ」はマメ科の植物で、インドやマレー半島が原産です。
日本では沖縄や奄美諸島、小笠原諸島に自生し、春から初夏にかけて赤い花を咲かせます。
THE BOOMの「島唄」の中で、「デイゴの花が咲き 風を呼び 嵐が来た」という歌詞があります。
因果関係は不明なのですが、デイゴはその年の台風を占う花となっていて、「デイゴが良く咲く年は、台風が多い」と言われています。
沖縄県の鳥「ノグチゲラ」
沖縄の県鳥は「ノグチゲラ」です。
「ノグチゲラ」はキツツキ科の沖縄島固有種で、沖縄本島北部の山原(やんばる)に生息しています。
国の特別天然記念物に指定され、沖縄県の東村では「ノグチゲラ保護条例」が制定されています。
沖縄県の魚「タカサゴ(グルクン)」
沖縄の県魚は「タカサゴ(グルクン)」です。
グルクンはタカサゴ科の魚で、正式名称が「タカサゴ」で、沖縄では「グルクン」という別名で呼ばれるのが一般的です。
食卓によく登場する安くて美味しい魚で、代表的な食べ方は、唐揚げです。











