| 【桜】10の語源・由来 | |
| ① | 「農耕の神様」説 |
| ② | 「花が咲き群がる」説 |
| ③ | 「木花咲耶姫・このはなさくやひめ」説 |
| ④ | 「咲麗・さきうら」説 |
| ⑤ | 「咲光映・さきはや」説 |
| ⑥ | 「割開・さけひらく」説 |
| ⑦ | 「裂くる・さくる」説 |
| ⑧ | 「サキクモル」説 |
| ⑨ | 「灼燦・しゃくしゃく」説 |
| ⑩ | 「咲くらむ」説 |
語源・由来のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。

| 【桜】3つの意味 | ||
| 桜 | 馬肉 | 偽客 |

| 【桜】漢字の読み方 | |
| 音読み | さくら |
| 訓読み | オウ |

| 【桜】の英語表現 |
| cherry blossom |

| 【桜】の花言葉 |
| 精神の美・優美な女性 |


【桜】10の語源・由来

語源・由来
| ① | 「農耕の神様」説 |
| ② | 「花が咲き群がる」説 |
| ③ | 「木花咲耶姫・このはなさくやひめ」説 |
| ④ | 「咲麗・さきうら」説 |
| ⑤ | 「咲光映・さきはや」説 |
| ⑥ | 「割開・さけひらく」説 |
| ⑦ | 「裂くる・さくる」説 |
| ⑧ | 「サキクモル」説 |
| ⑨ | 「灼燦・しゃくしゃく」説 |
| ⑩ | 「咲くらむ」説 |

【桜】の語源には、定説はありません。
ここでは、【桜】の10の語源をお伝えします。
その1(「農耕の神様」説)
【桜】の語源は、「農耕の神様」に由来する説です。
桜は農耕の神様が降臨する花とされ、桜の咲き具合でその年の豊作が占われていました。
「さくら」の「さ」は「農耕の神様」、「くら」は「磐座」という意味です。
| 「さ」の意味 | 農耕の神様 |
| 「くら」の意味 | 磐座(神様がとどまる場所) |
この二つの言葉を合わせて「桜」と呼ばれるようになりました。
この説は、和歌森太郎博士の「花と日本人」という著書にも書かれています。
その2(「花が咲き群がる」説)
【桜】の語源は、「花が咲き群がる」ことに由来する説です。
桜は、小さな花が複数まとまって、樹に束になって一斉に咲くのが特徴です。
動詞「咲く」に、複数を表す接尾語の「ら」が付き、「桜」という名詞になりました。
その3(「木花咲耶姫・このはなさくやひめ」説)
【桜】の語源は、「木花咲耶姫(このはなさくやひめ)」に由来する説です。
「木花咲耶姫」は、「古事記」にも登場する桜の女神様で、桜のような美女だったそうです。
桜の種を初めて日本に蒔いたのは、木花咲耶姫とも言われています。
女神様の「さくや」が訛って、「さくら(桜)」と呼ばれるようになりました。
木花咲耶姫が祀られている富士山本宮浅間大社は、桜の名所としても有名です。
「木花咲耶姫」は、他に、木花開耶姫(このはなのさくやひめ)、木花咲弥姫命(このはさくやひめのみこと)、木花之佐久夜毘売(このはなのさくやひめ)と呼ばれることがあります。
その4(「咲麗・さきうら」説)
【桜】の語源は、「咲麗(さきうら)」に由来する説です。
「咲麗」とは、花が華麗に咲く様子を表す言葉です。
| 「咲麗(さきうら)」の意味 |
| 花が華麗に咲く様子 |
華麗な花の代表格である桜。
この「咲麗(さきうら)」が略されて「さくら(桜)」と呼ばれるようになりました。
その5(「咲光映・さきはや」説)
【桜】の語源は、「咲光映(さきはや)」に由来する説です。
「咲光映」とは、花の中でも勝れて美しいという意味です。
| 「咲光映(さきはや)」の意味 |
| 花の中でも勝れて美しいこと |
桜の美しさから、「咲光映(さきはや)」が略されて「さくら(桜)」と呼ばれるようになりました。
その6(「割開・さけひらく」説)
【桜】の語源は、「割開(さけひらく)」に由来する説です。
「割開」とは、桜の樹皮が裂けて剥がれる様子を表す言葉です。
| 「咲光映(さきはや)」の意味 |
| 桜の樹皮が裂けて剥がれる様子 |
「割開(さけひらく)」が転じて、「さくら(桜)」と呼ばれるようになりました。
その7(「裂くる・さくる」説)
【桜】の語源は、「裂くる(さくる)」に由来する説です。
「裂くる」は「裂ける」の古語です。
桜は樹皮が裂けることから、「裂くる(さくる)」→「さくら(桜)」と呼ばれるようになりました。
その8(「サキクモル」説)
【桜】の語源は、「サキクモル」に由来する説です。
桜が咲く春の季節の天候は独特で、高気圧と低気圧の間隔が短く曇りの日(花曇り)が多いです。
この独特な春の天候を、「咲くと曇る」ことから「サキクモル」と言うようになりました。
次第に「サキモクル→さくら」と名前が変化し、天候ではなく「桜」そのものを意味するようになりました。
その9(「灼燦・しゃくしゃく」説)
【桜】の語源は、「灼燦(しゃくしゃく)」に由来する説です。
「灼燦」は、美しく光り輝くことです。
| 「灼燦・しゃくしゃく」の意味 |
| 美しく光り輝くこと |
「灼燦」の別音は「さくら(sakura)」です。
桜の花の美しさから、「さくら(桜)」と呼ばれるようになりました。
その10(「咲くらむ」説)
【桜】の語源は、「咲くらむ」に由来する説です。
「咲くらむ」は、「咲く」に物事の推量を表す「らむ」が重なった言葉です。
「咲くらむ」が「さくら」に転化し、「桜」という意味を持つようになりました。
【桜】3つの意味
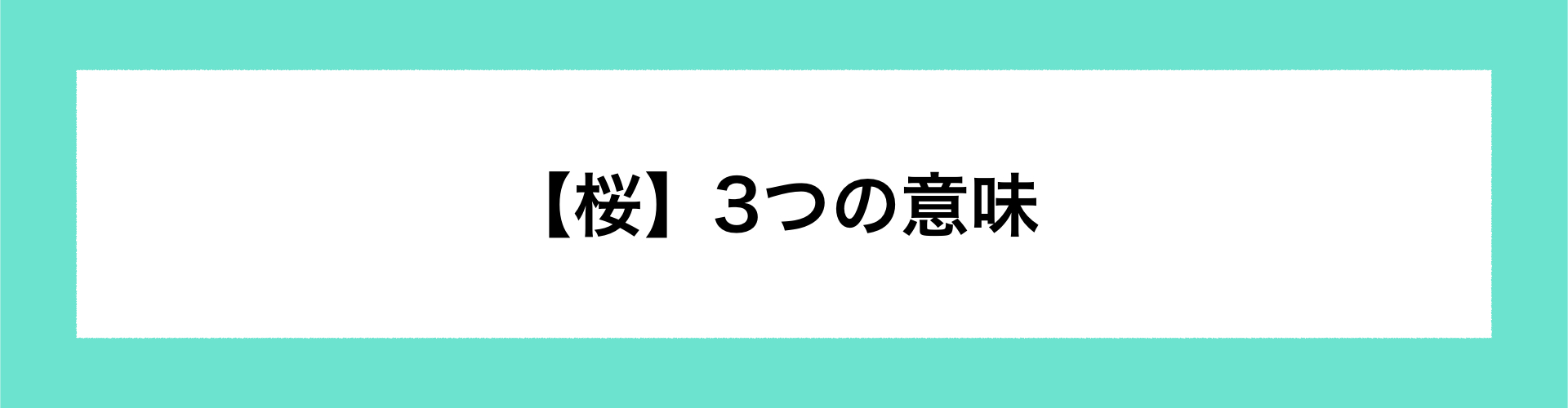
意味
- ❶桜
- ❷馬肉
- ❸偽客

その1(桜)
【桜】の1つ目の意味は、バラ科サクラ属の落葉高木の総称です。
| 【桜】の意味① |
| ・バラ科サクラ属の落葉高木の総称 ・日本の国花で代表的な品種はソメイヨシノ |
春になると一斉に咲く、お花見でお馴染みの「桜」です。
桜の花を「桜花(おうか)」、樹木を「桜樹(おうじゅ)」、樹皮を「桜皮(おうひ)」と言います。
その2(馬肉)
【桜】の2つ目の意味は、馬肉です。
| 【桜】の意味② |
| 馬肉 |
日本では、675年(飛鳥時代)から江戸時代まで「肉食禁止令」が出されていたため、罰せられることを恐れて、猪肉を「牡丹(ボタン)」、鹿肉を「紅葉(もみじ)」と植物の名前で呼んでいました。
馬肉は桜の色に似ていたことから、「桜(さくら)」と呼ばれるようになったそうです。
他にも、千葉県佐倉市にある幕府の牧場に、馬がたくさんいたから。
桜が咲く時期になると、馬肉に脂がのって美味しくなるから、という都市伝説的な説があります。
その3(偽客)
【桜】の3つ目の意味は、偽客です。
| 【桜】の意味③ |
| ・偽客 ・客のふりをして、客や行列の中に紛れ込み会場を盛り上げたりする者 |
【桜】漢字の読み方
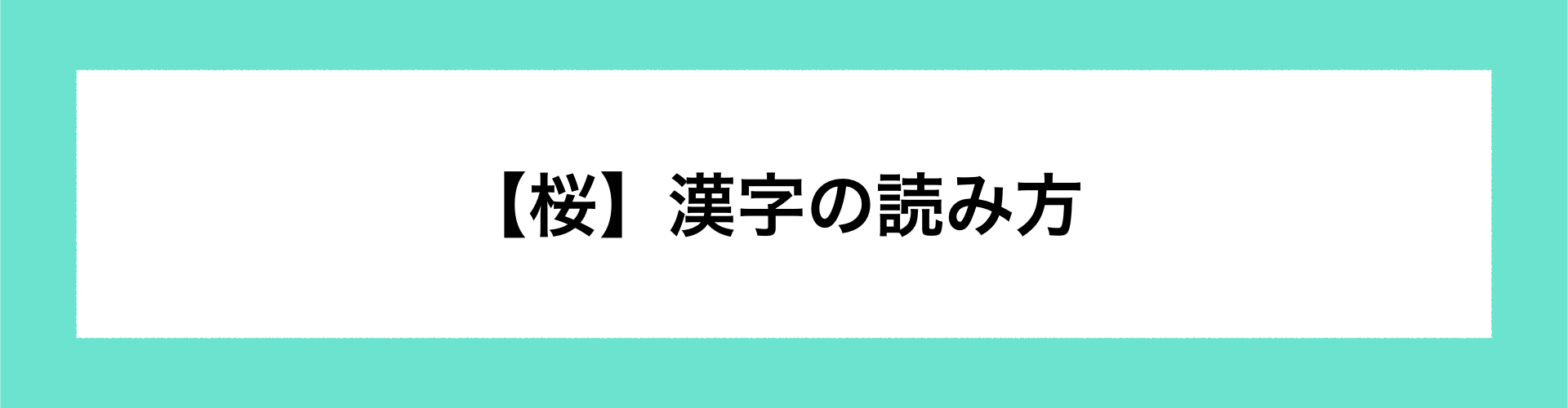

【桜】は音読みで「さくら」、訓読みで「オウ」と読みます。
| 音読み | さくら |
| 訓読み | オウ |
「桜」は新体字で、旧字体では「櫻」と書きます。
【桜】の英語表現
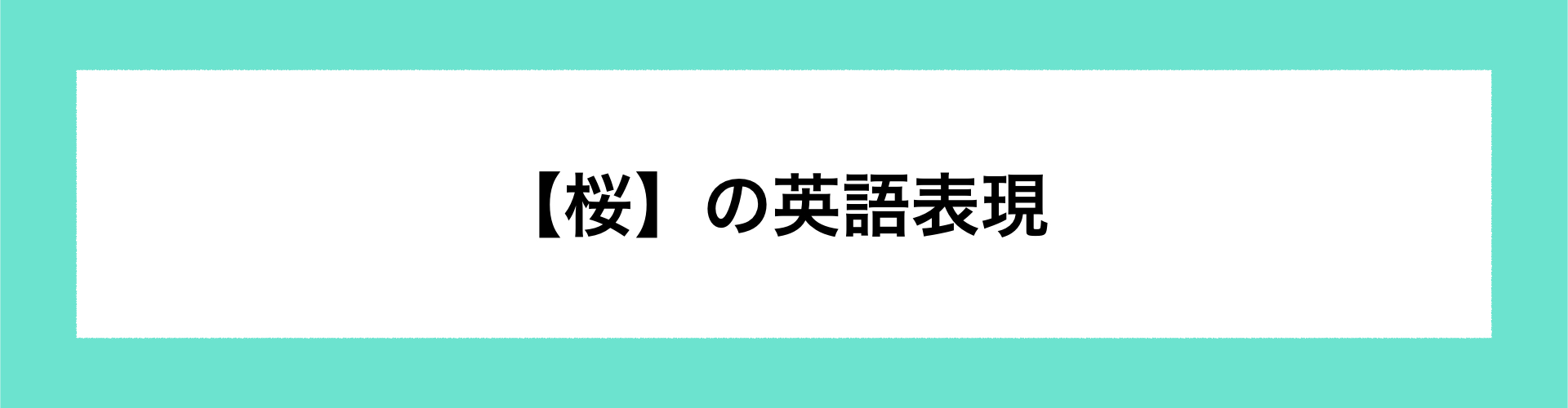
英語表現
- ❶【桜】の英語表現
- ❷「桜の種類」の英語表現
- ❸【桜】にまつわる英語表現

【桜】の英語表現
【桜】の英語表現は「cherry blossom」です。
| 【桜】の英語表現 |
| cherry blossom |
「cherry」は「さくらんぼ」、「blossom」は「花」という意味です。
「桜の種類」の英語表現
桜の代表的な品種は「ソメイヨシノ」です。
アメリカのワシントンのポトマック川には、桜並木があり、桜の名所となっています。
| ソメイヨシノ | the Yoshino cherry blossoms |
| 八重桜 | double cherry blossoms |
| 寒桜 | winter cherry blossoms |
| 枝垂桜 | weeping cherry blossoms |
【桜】の花言葉
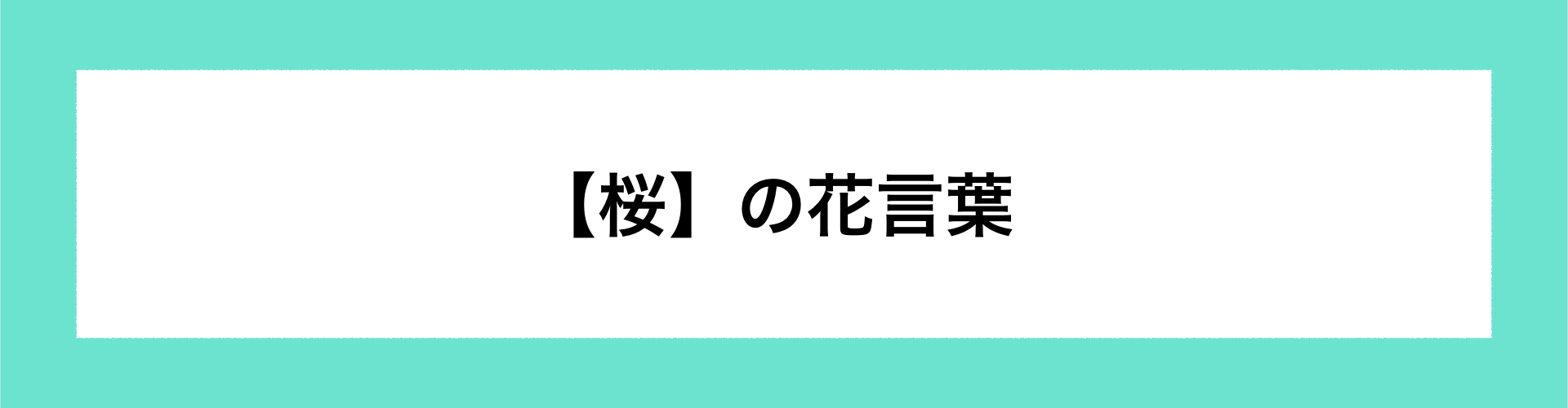
【桜】の花言葉
- ❶日本での花言葉
- ❷海外での花言葉

日本での桜の花言葉
桜全体の花言葉は「精神の美・優美な女性」です。
桜には、種類ごとに花言葉があります。
| 桜全体 | 精神の美・優美な女性 |
| ソメイヨシノ | 純潔・優れた美人 |
| 枝垂れ桜 | 優美・ごまかし・円熟した美人 |
| 八重桜 | 豊かな教養・理知に富んだ教育・しとやか |
| 寒桜 | 気まぐれ |
| 山桜 | あなたに微笑む・純潔・高尚・淡泊・美麗 |
| 冬桜 | 冷静 |
海外での桜の花言葉
| 英語 | 精神の美・優れた教育 |
| フランス | 私を忘れないで |
| 韓国 | 心の美しさ |
| スペイン | 心の美しさ・成功・潔白 |
【桜】にまつわる英語表現
| お花見 | cherry blossom viewing |
| 満開 | in full bloom |
| 三分咲 | one-third in bloom |
| 五分咲 | half in bloom |
| 七分咲 | three-quarter in bloom |
【桜】の外国語表現
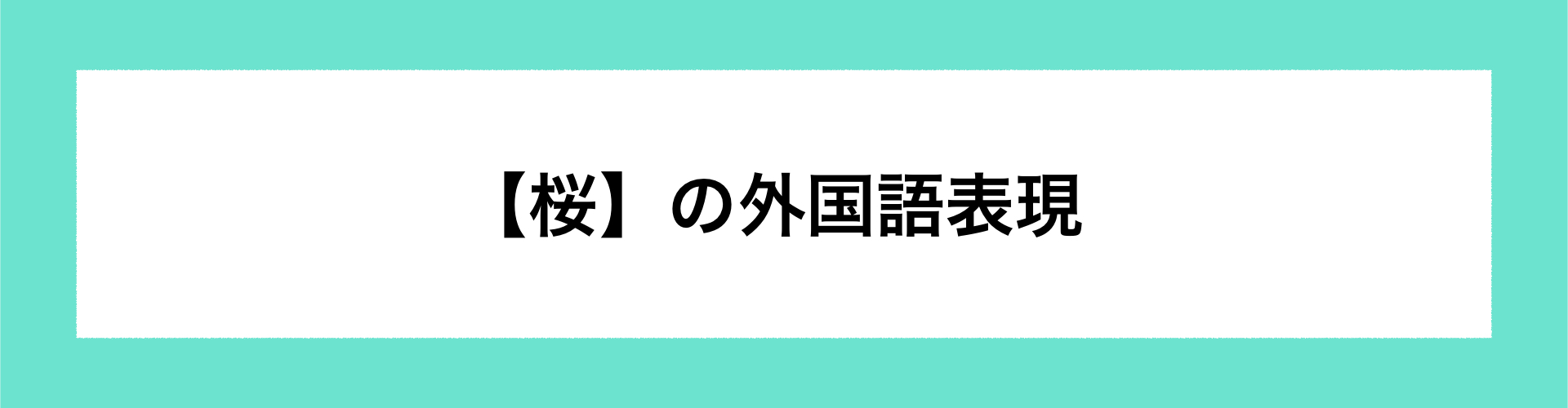

| フランス語 | fleur de cerisier(フルール ドゥ スリズィエ) |
| イタリア語 | Fiori di ciliegio(フィオーリ ディ チリーェジオ) |
| スペイン語 | flor de cerezo(フロール・デ・セレッソ) |
| 中国語 | 樱花(yīnghuā) |
| ベトナム語 | hoa anh đào |
| タイ語 | ซากุระ(サクラ) |
| ロシア語 | сакура |
| 韓国語 | 벚꽃 ポッコッ |
お花見の始まり/歴史
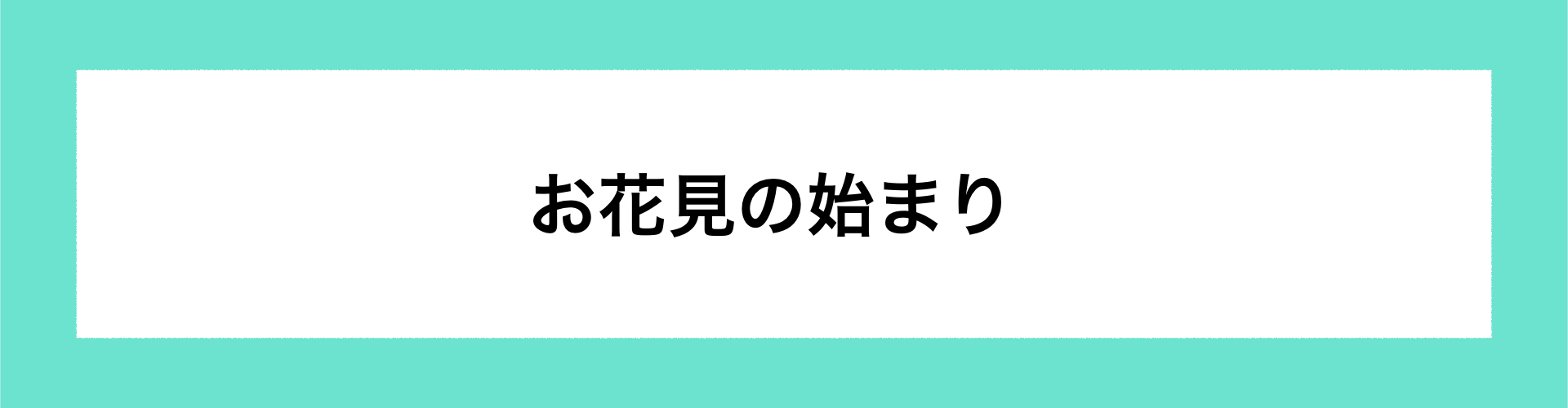

日本で初めてお花見が行われたのは、奈良時代です。
お花見は中国から日本に伝わり、当初は梅の花を鑑賞するのが「花見」でした。
平安時代になると、鑑賞する花が梅から桜に変わっていきます。
812年(平安時代)には、嵯峨天皇が神泉苑でお花見を開催しています。
1598年(安土桃山時代)には、豊臣秀吉が醍醐寺で盛大なお花見(醍醐の花見)開催しました。
その後、江戸時代になると、庶民にもお花見が広がりました。
「さくらの日」とは
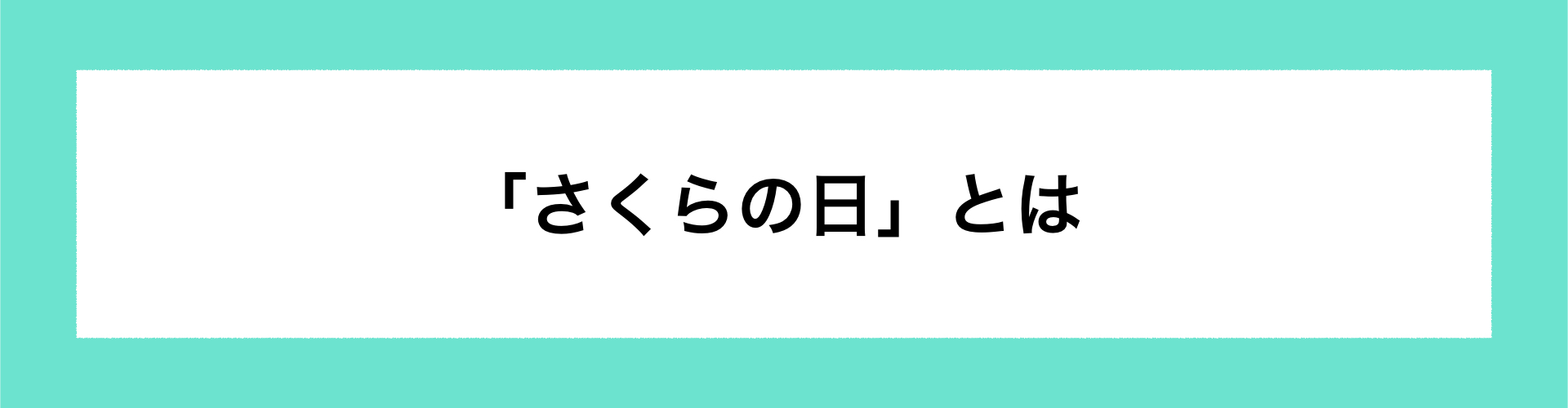
「さくらの日」とは
- ❶「さくらの日」とは
- ❷七十二候の「桜始開」とは

「さくらの日」とは
3月27日は「さくらの日」です。
「日本さくらの会」によって1992年(平成4年)に制定されました。
「3×9(さくら)=27」の語呂合わせと、七十二候(しちじゅうにこう)の「桜始開(さくらはじめてひらく)」の時期が重なることが由来とされています。
七十二候の「桜始開」とは
「七十二候(しちじゅうにこう)」とは、古代中国の季節の表し方です。
季節の移り変わりを細かく感じられるように、1年を5日ごとに、72の季節に分けています。
このうち、春分の次候が「桜始開(さくらはじめてひらく)」で、「桜が咲き始めるころ」を表しています。




