「楊柳」の「枝」から作られ、先の尖った見た目から、「物の先端」を意味する「爪」がつけられました。


| 【爪楊枝】の語源 |
| 語源は中国の「楊柳(ようりゅう)」という植物。 原料に「楊柳」の枝が使われ、先の尖った見た目から、「物の先端」を意味する「爪」がつけられた。 |

| 【爪楊枝】の由来 |
| 爪楊枝は仏教に由来。 お釈迦様が弟子に「木の枝」で歯を磨くことを教え、それが中国を経由して日本に伝わった。 |

| 【爪楊枝 】2つの漢字表記 | |
| 爪楊枝 | 妻楊枝 |

| 【爪楊枝】3つの別名 | ||
| 楊枝 | 小楊枝(こようじ) | 黒文字(くろもじ) |

| 【爪楊枝】の英語表現 |
| toothpick |

| 【爪楊枝】に溝・くぼみがある理由 |
| 爪楊枝は、製造過程で端の部分が焦げてしまう。 焦げを「こけし」の頭に見立ててデザインしたために、溝がつけられた。 |


【爪楊枝】の語源は植物の〇〇に由来
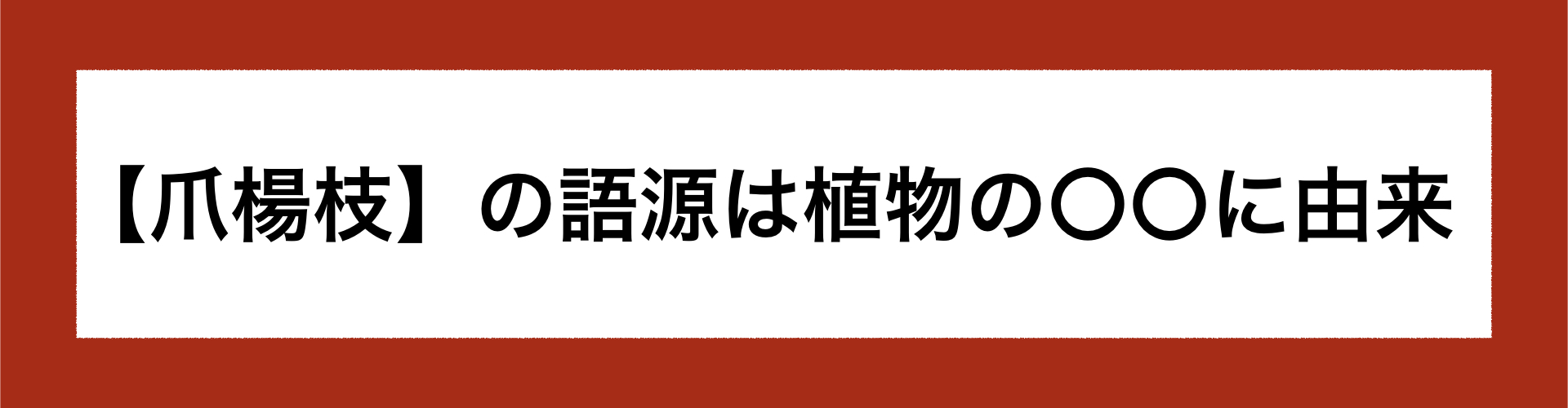
語源
- ❶【爪楊枝】の語源は植物の〇〇に由来
- ❷「楊柳(ようりゅう)」とは

【爪楊枝】の語源は植物の〇〇に由来
【爪楊枝】の語源は、中国の「楊柳(ようりゅう)」という植物に由来します。
「楊枝」は、元々「総楊枝・房楊枝(ふさようじ)」と呼ばれ、歯垢を取るために僧侶が使っていた道具でした。
「総楊枝」という名前がついたのは、「楊柳」という植物の枝を叩き、先端をふさ状にしていた為です。
「総楊枝」の形が「ふさ状」から「先の尖った形」に変化したことで、「物の先端」を意味する「爪」がつけられ、「爪楊枝」となりました。
「楊柳(ようりゅう)」とは
「楊柳(ようりゅう)」とは、ヤナギ科ヤナギ属の樹木の「柳」のことです。
柳の樹皮には、解熱鎮痛薬として使われる「アスピリン」が含まれています。
現在は「柳」が一般的ですが、「楊」「楊柳」と表記することもあります。
「楊」は「カワヤナギ」、「柳」は「シダレヤナギ」という意味があります。
【爪楊枝】は仏教に由来
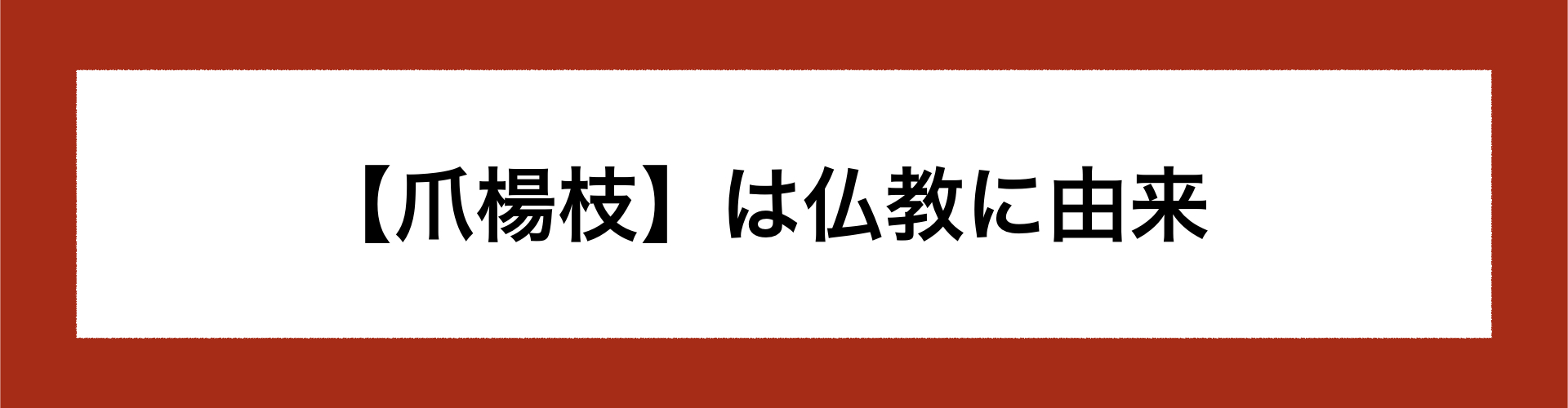

爪楊枝の始まりは紀元前500年頃、お釈迦様が弟子に、木の枝で歯を磨くことを教えたことです。
これが、爪楊枝・歯ブラシの始まりと言われています。
古代インドでは、歯を磨くのに、ニームの木から作られた「ダンタカシュータ」と呼ばれる道具が使われていました。
それが「歯木(しもく・しぼく)」という名前で中国に伝わり、楊柳の木で作られたため「楊枝」となりました。
日本に伝えられたのは奈良時代、仏教徒ともに中国から伝わりました。
【爪楊枝】の2つの漢字表記
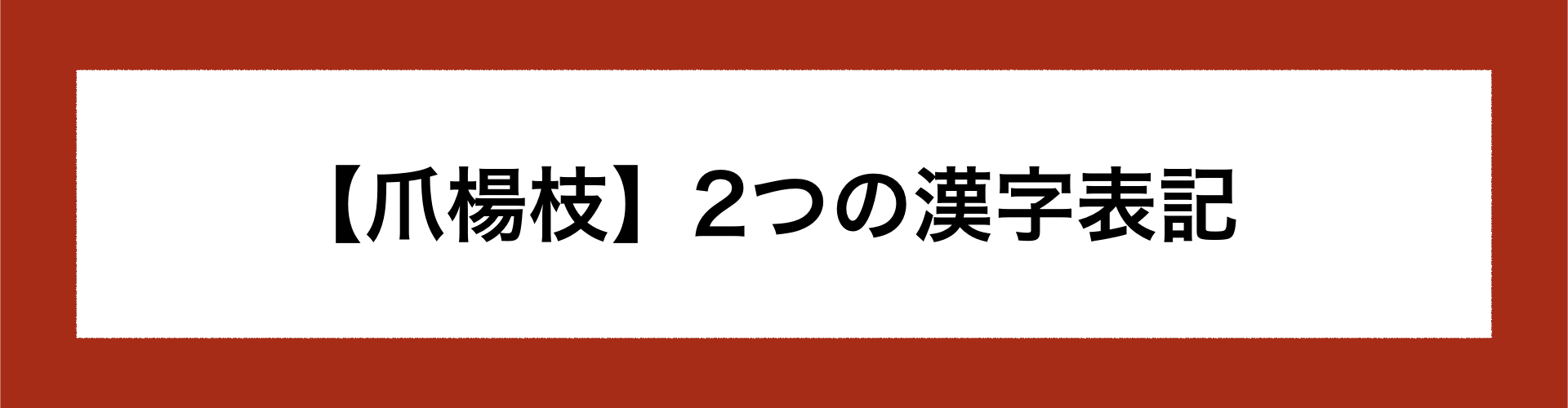
漢字表記
- ❶2つの漢字表記
- ❷「妻楊枝」と「爪楊枝」の違い

2つの漢字表記
爪楊枝には、2つの漢字表記があります。
| 【爪楊枝】2つの漢字表記 |
| ・爪楊枝 ・妻楊枝 |
一般的には「爪楊枝」が使われることが多いです。
「妻楊枝」と「爪楊枝」の違い
「妻楊枝」の「妻」は当て字と考えられています。
「爪楊枝」と「妻楊枝」は、どちらも同じものを指していますが、「爪楊枝」が一般的です。
辞書によっては「妻楊枝」の記載もありますが、「爪楊枝」を使った方が無難です。
【爪楊枝】の3つの別名
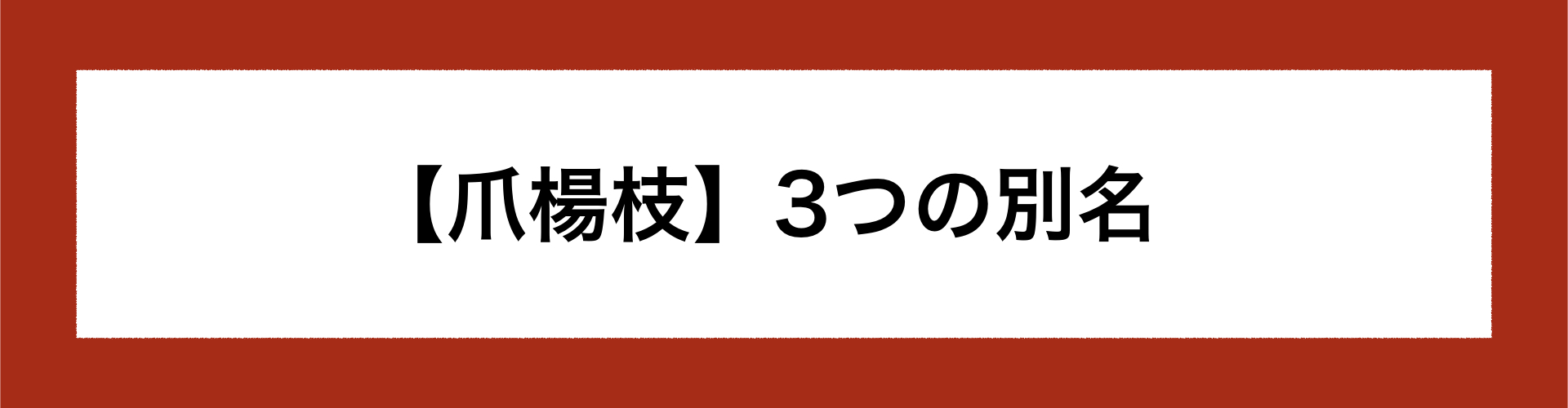
別名
- ❶3つの別名
- ❷「黒文字」とは

3つの別名
爪楊枝には3つの別名があります。
| 【爪楊枝】3つの別名 |
| ・楊枝 ・小楊枝(こようじ) ・黒文字(くろもじ) |
「楊枝」という呼び方は、よく使われます。
「黒文字」とは
「黒文字」とは、お茶の席で、和菓子をいただくときに使われる楊枝です。
クスノキ科の樹木である「黒文字の枝」から作られていて、柑橘系のいい香りがします。
【爪楊枝】の英語表現(toothpick)
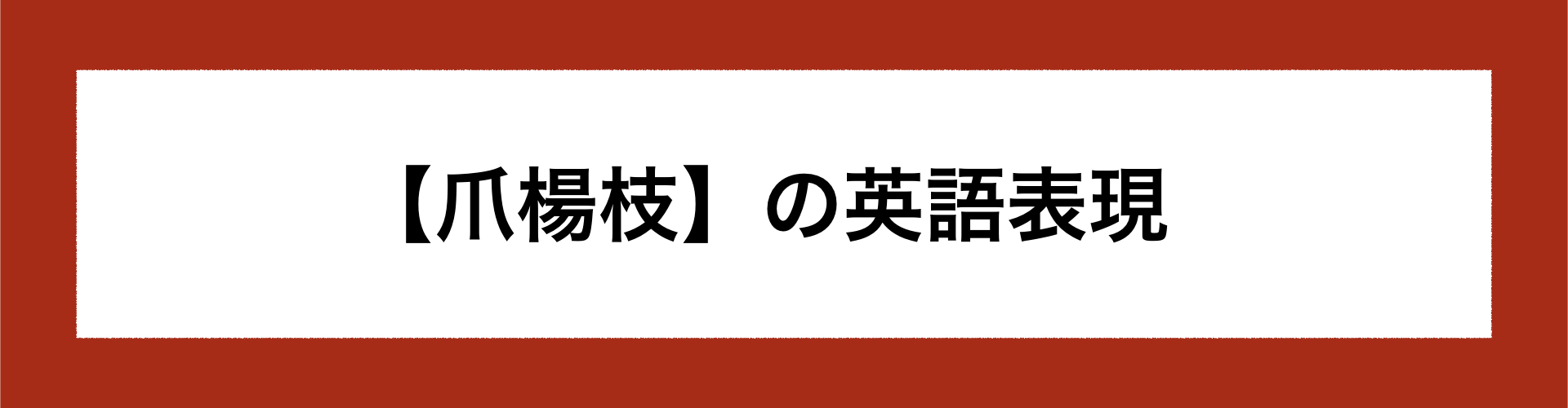

「爪楊枝」の英語表現は「toothpick」です。
| 【爪楊枝】の英語表現 |
| toothpick |
「tooth」は「歯」、「pick」は「ほじる、つつく」という意味の単語です。
| 英語 | 日本語 |
| tooth | 歯 |
| pick | ほじる・つつく |
| I use toothpicks after dinner. |
| 夕食の後につまようじを使います。 |
【爪楊枝】のくぼみ/溝がある2つの理由
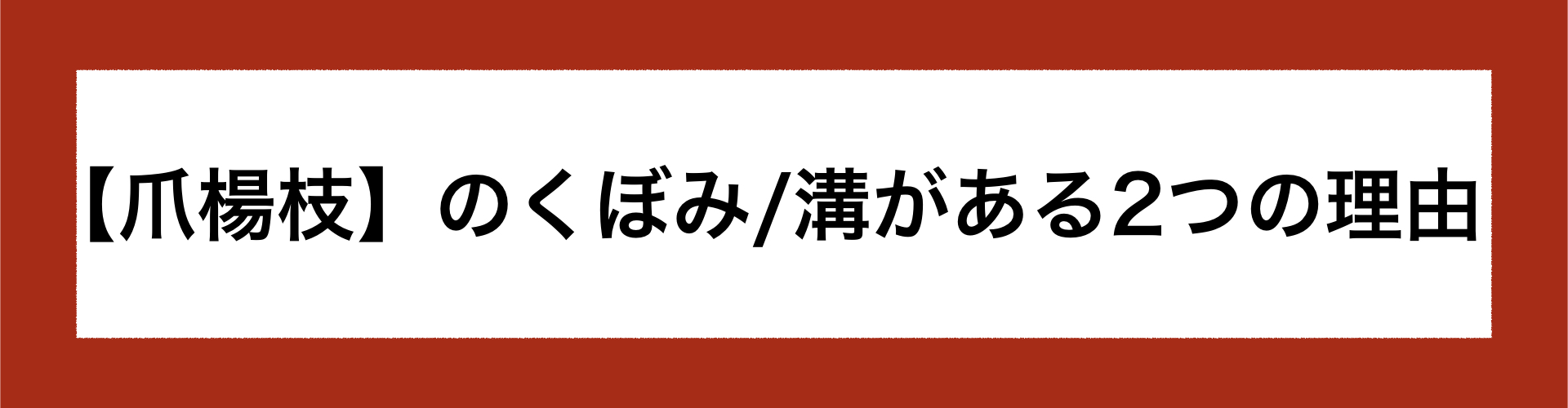
溝がある理由
- ❶「こけしを模したデザイン」説
- ❷都市伝説的な「爪楊枝置き」説

その1(「こけしを模したデザイン」説)
爪楊枝のくぼみは、「こけし」を模したデザインです。
爪楊枝は、製造過程で研磨をするときに、摩擦で端の部分が焦げてしまいます。
この黒く焦げた部分は、あまり見栄えがよくありません。
これをどうにかできないかと考えた結果が、溝を掘り「こけし」のようにデザインすることだったのです。
ちなみに、この溝は、メーカーによってデザインが異なるそうです。
この理由は、NHKの番組「チコちゃんに叱られる」でも紹介されました。
その2(都市伝説的な「爪楊枝置き」説)
爪楊枝にくぼみがある理由の都市伝説的な理由は、爪楊枝置きです。
溝の部分でポキっと折り、折った部分を箸置きのようにして、使いかけの爪楊枝を上に置くいうものです。
とても小さな爪楊枝置きとなりますし、使いづらいでしょうね。
【爪楊枝】の使い方
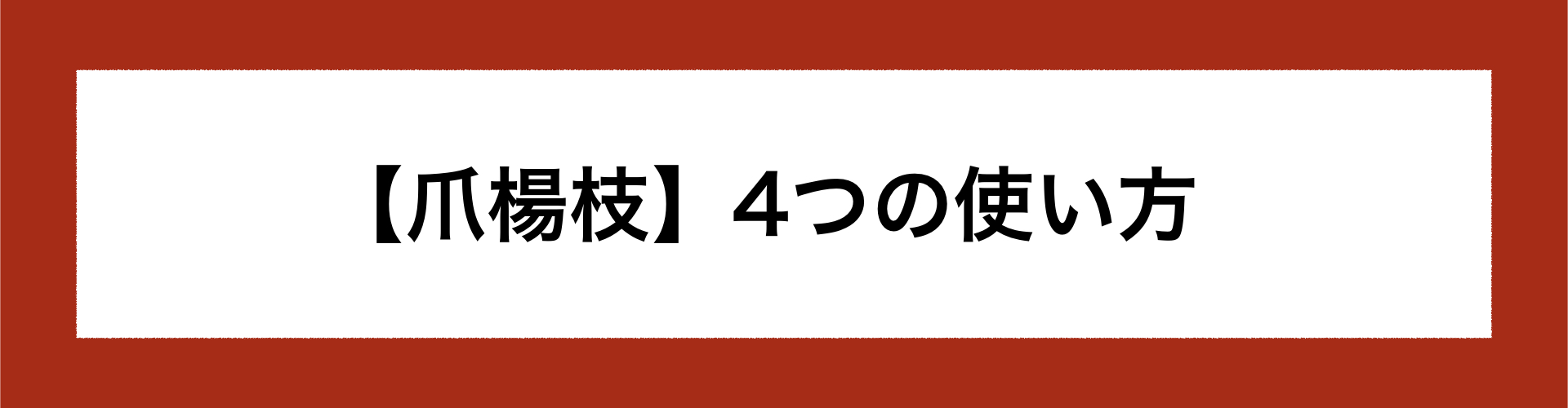

爪楊枝は身近な存在であり、様々なことに使われています。
その1(歯に詰まった食べ物を取る)
もっとも一般的な使い方は、歯に詰まった食べ物を取ることです。
日本では、居酒屋さんなどのテーブルに爪楊枝が置かれていることが多いです。
マナーとしてはテーブルでの使用は賛否が分かれますが、年配の方にとっては必需品かもしれません。
その2(食べ物を口に運ぶ)
食べ物を口に運ぶときも、爪楊枝は良く使われます。
例えばフルーツやチーズなど、ちょっとした食べ物をつまむときに使われます。
その3(食べ物をまとめる)
サンドウィッチやピンチョスなど、食べ物をまとめるときに使われます。
爪楊枝でまとめられていると食べやすいですし、爪楊枝に装飾をすれば、とてもオシャレです。
その4(料理の装飾)
お子様ランチの国旗のように、料理の装飾として使われます。
変わった素材やデザインの爪楊枝を使うだけで、料理がオシャレになります。
シンプルな爪楊枝も、マスキングテープで装飾するだけで、可愛いピックになります。
【爪楊枝】の原料
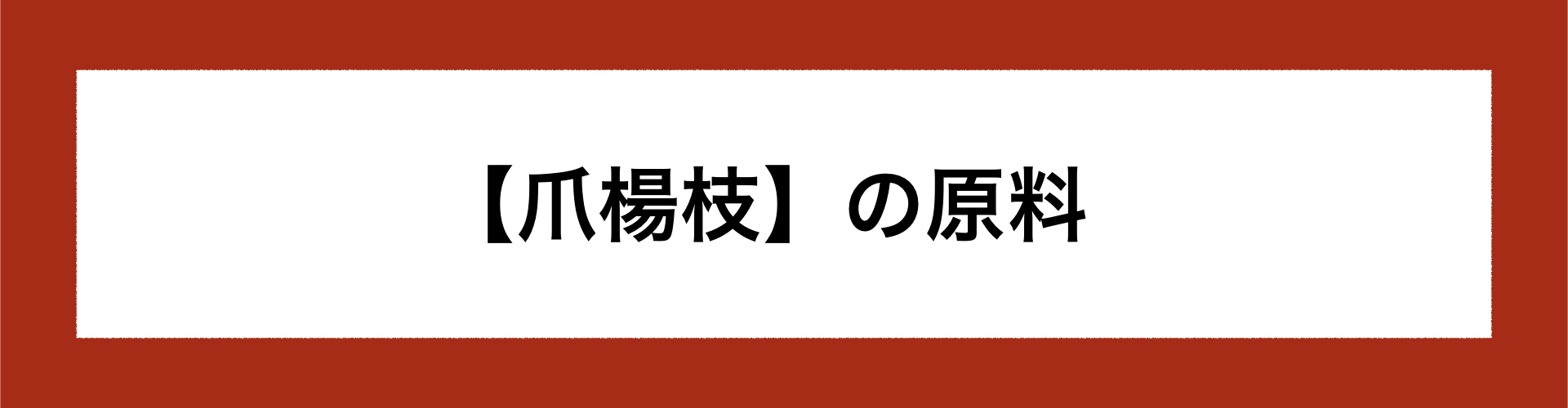
原料
- ❶【爪楊枝】の現在の原料
- ❷【爪楊枝】の昔の原料

【爪楊枝】の現在の原料
爪楊枝には、主に白樺の木が使われています。
成長が早く自生する植物なので手入れが簡単。
柔らかい木材なので、歯ぐきを傷つけにくく、爪楊枝に適しています。
また、白樺からは虫歯予防で知られるキシリトールが取れます。
薬木であることも、爪楊枝に使われる理由の1つです。
他、黒文字やプラスチックで作られているものもあります。
【爪楊枝】の昔の原料
爪楊枝の発祥は、お釈迦様が弟子に口を清潔にすることを勧めたことです。
古代インドでは、ニームという植物の枝で作られた「ダンタカシュータ」という道具で歯を磨いていました。
それが中国に伝わり、「歯木」と呼ばれ、鎮静作用のある楊柳の枝が使われるようになりました。
このように、昔から爪楊枝には、薬となる木が使われていました。
世界の【爪楊枝】
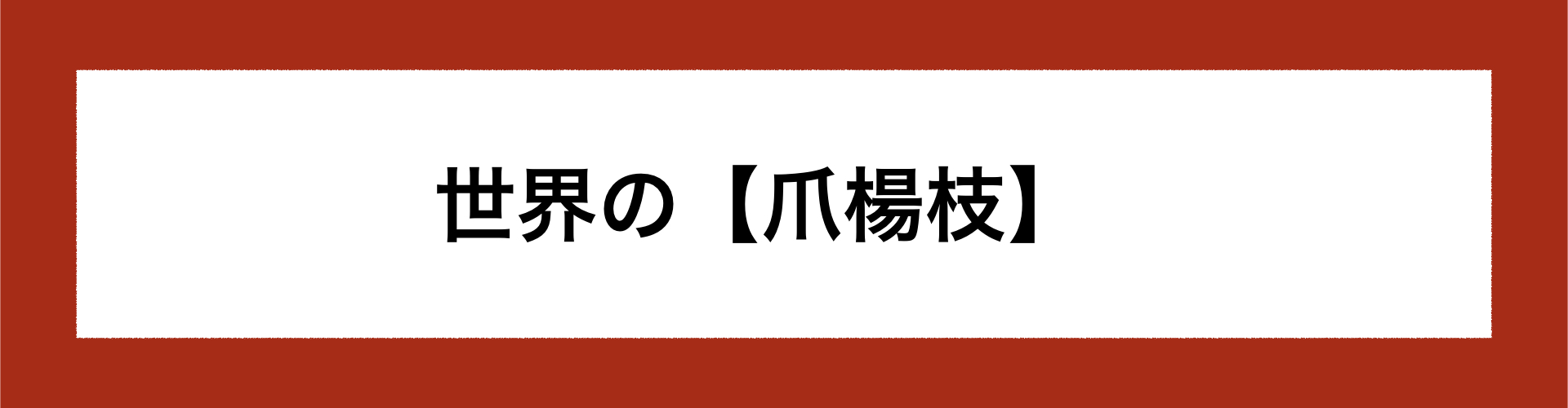
世界の爪楊枝
- ❶アメリカの爪楊枝
- ❷スペインの爪楊枝
- ❸イタリアの爪楊枝

海外にも爪楊枝はありますが、日本の物とは少し異なるようです。
アメリカの爪楊枝
アメリカの爪楊枝は、フレーバーがついているものが多いです。
ガムや飴に近いような感覚で使われています。
スペインの爪楊枝
スペインの爪楊枝は、主にピンチョスをつまむ為に使われます。
中央が幅広になっているので、見た目もオシャレだし、ホールド力も高いです。
イタリアの爪楊枝
イタリアの爪楊枝は、両端がピック状になっています。
イタリアでは、爪楊枝の商品名に日本語が使われていることが多いのが特徴です。
| イタリアの爪楊枝の商品名 |
| ・samurai(サムライ) ・sayonara(サヨナラ) ・kimono(着物) ・karate(空手) ・bonsai(盆栽) |


