

【杜撰】の「杜」は、宋の詩人、杜黙(ともく)のこと。
「撰」は、詩を作ることです。
杜黙が定型詩の規則を無視して詩を作った「野客叢書」の故事が由来です。
この故事が元になって、「詩や文章に、典拠の確かでないことを書くこと。また、その詩文。」を意味する言葉として【杜撰】が使われるようになりました。
それが転じて、「物事がいいかげんで、誤りが多いこと」という意味で使われるようになりました。
由来・語源のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。
| 【杜撰】の読み方 |
| ずさん |

| 【杜撰】言い換え表現/同じ意味の四字熟語 | |
| 杜黙詩撰 | 杜撰脱漏 |

| 【杜撰】7つの類語・類義語 | |
| ぞんざい | 生半可 |
| 与太 | 粗漏・疎漏 |
| 大雑把 | 出鱈目 |
| おざなり | |

| 【杜撰】5つの反対語・対義語 | |
| 緻密 | 綿密 |
| 丁寧 | 入念 |
| 精密 | |

| 【杜撰】5つの英語表現 | |
| sloppy | careless |
| slipshod | slovenly |
| loose | |

| 【杜撰】4つの中国語表現 | |
| 杜撰 | 稀松 |
| 草率 | 粗劣 |


故事成語【杜撰】意味・読み方

意味・読み方
- ❶【杜撰・ずさん】の意味
- ❷「杜」の意味
- ❸「撰」の意味
- ❹【杜撰】の読み方

【杜撰・ずさん】の意味
【杜撰】の意味は、物事がいい加減で誤りが多いことです。
| 【杜撰】の意味 |
| ・物事がいい加減なこと ・書物などで誤りが多いこと |
「杜」の意味
「杜」の意味は、木のたくさん生い茂っているところです。
| 杜」の意味 |
| 木のたくさん生い茂っているところ |
音読みで「ト」「ズ」
訓読みで「ふさぐ」「もり」と読みます。
「撰」の意味
「撰」の意味は、文章や詩を作ることです。
| 「撰」の意味 |
| 文章や詩を作ること |
音読みで「セン」、訓読みで「えらぶ」と読みます。
【杜撰】の読み方
【杜撰】の読み方は「ずさん」です。
| 【杜撰】の読み方 |
| ずさん |
元々は濁音で発音されていた言葉なので、「ずざん」と読むこともあります。
「とせん」と読まれることがありますが、間違いです。
「撰」の読み方は「セン」「えらぶ」で、「さん」と読むのは珍しいです。
読めそうで読めない、難しい漢字です。
【杜撰】3つの由来・語源
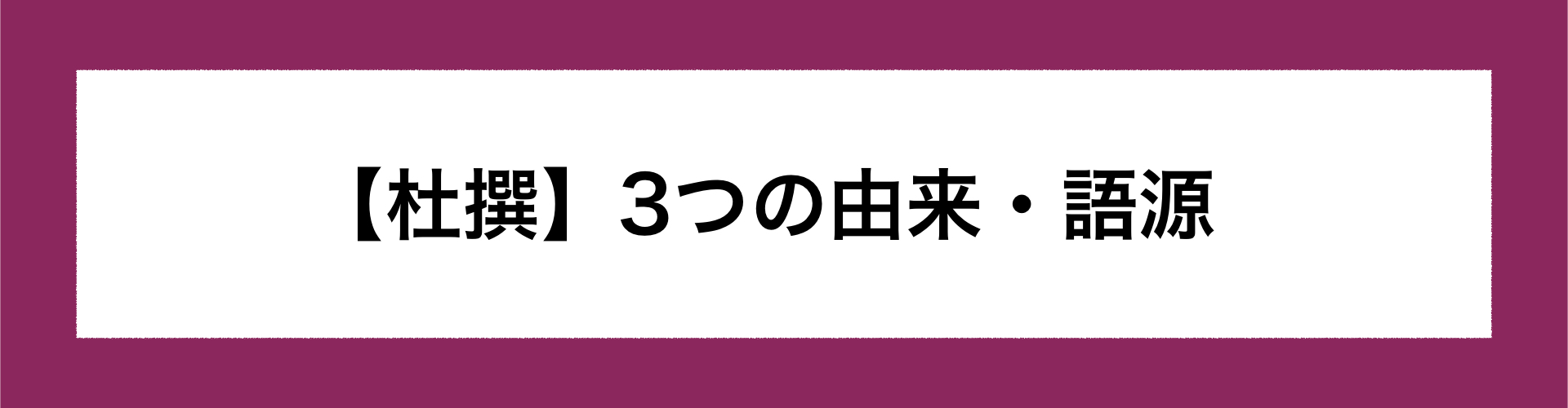
由来・語源
- ❶「詩人」説
- ❷「易経の学者」説
- ❸「道士」説

【杜撰】には3つの由来・語源があります。
有力説は「詩人」説です。
その1(「詩人」説)
中国・宋時代に杜黙(ともく)という詩人がいました。
杜黙の作る詩は独特で、律(詩の様式)を無視した、個性的で斬新なものが多かったそうです。
この故事は、宋時代に王楙(おうぼう)によって書かれた「野客叢書(やかくそうしょ)」に書かれています。
杜黙の作る詩が、詩のルールを破っていたことから「詩や文章に、典拠の確かでないことを書くこと」の意味で【杜撰】という言葉が使われるようになりました。
更にこれが転じて、「いい加減なこと、誤りの多いこと」という意味で使われるようになりました。
その2(「易経の学者」説)
中国・前漢時代に「杜田生」という易経の学者がいました。
前漢時代は思想や学問などが弾圧されていたので、書物が不足していました。
そのため、杜田生の書いた書物は、根拠のないいい加減な書物とレッテルを貼られてしまいました。
このことから、「いい加減なこと、誤りの多いこと」の意味で【杜撰】という言葉が使われるようになりました。
その3(「道士」説)
中国・唐時代末期から五代十国時代に「杜光庭(とこうてい)」という道士がいました。
杜光庭は、偽作された仏教経典「老子化胡経(ろうしけこきょう)」を書いた人物です。
「老子化胡経」には、道教の優位を主張するために、仏教は老子が説いた教えであるという虚構の説が書かれています。
「杜光庭の書いた書物(杜光庭撰)は、根拠のないいい加減な書物」なので、「いい加減なこと、誤りの多いこと」の意味で【杜撰】という言葉が使われるようになりました。
【杜撰】使い方・例文
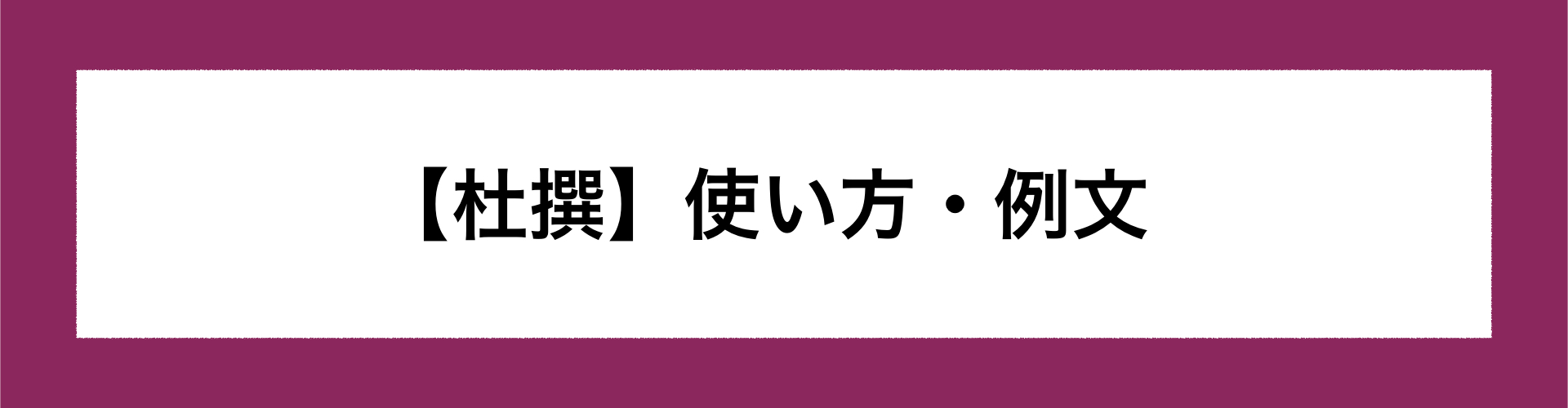
使い方・例文
- ❶使い方
- ❷例文

使い方
【杜撰】は、物事の状態や進め方に問題がある場合、書類などに誤りが多い時に使われる言葉です。
悪い意味で使われます。
いい加減なやり方をしていることに使われる言葉で、人の人間性に使われる言葉ではありません。
「杜撰な性格」という言い回しで使われることがありますが、適切ではありません。
よく使われる言い回しとして、「杜撰な管理」「杜撰な対応」「杜撰な仕事」などがあります。



例文
| 例文1 | 杜撰な登山計画だったので、道に迷いそうになった。 |
| 例文2 | 型紙の切り方が杜撰だったため、いびつな形のバッグが完成した。 |
| 例文3 | 杜撰な資料を参考にしていたため、レポートが再提出となった。 |
【杜撰】言い換え表現/同じ意味の四字熟語
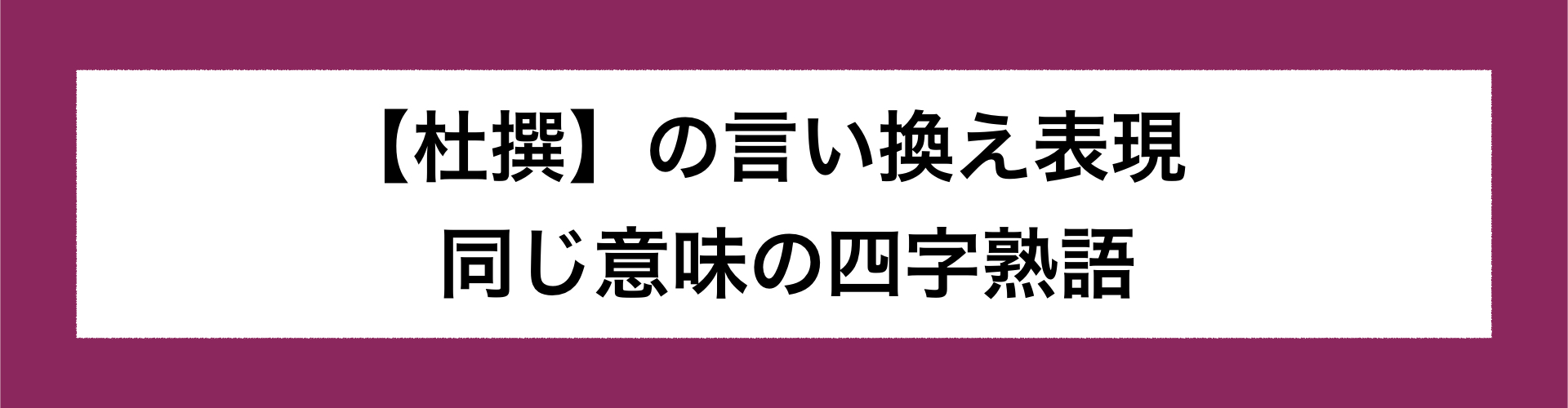

【杜撰】と同じ意味の四字熟語に「杜黙詩撰」「杜撰脱漏」があります。
| 【杜撰】同じ意味の四字熟語 |
| ・杜黙詩撰(ともくしせん) ・杜撰脱漏(ずさんだつろう) |
どれも「物事がいい加減なこと、誤りが多いこと」という意味なので、言い換えることができます。
【杜撰】7つの類語・類義語
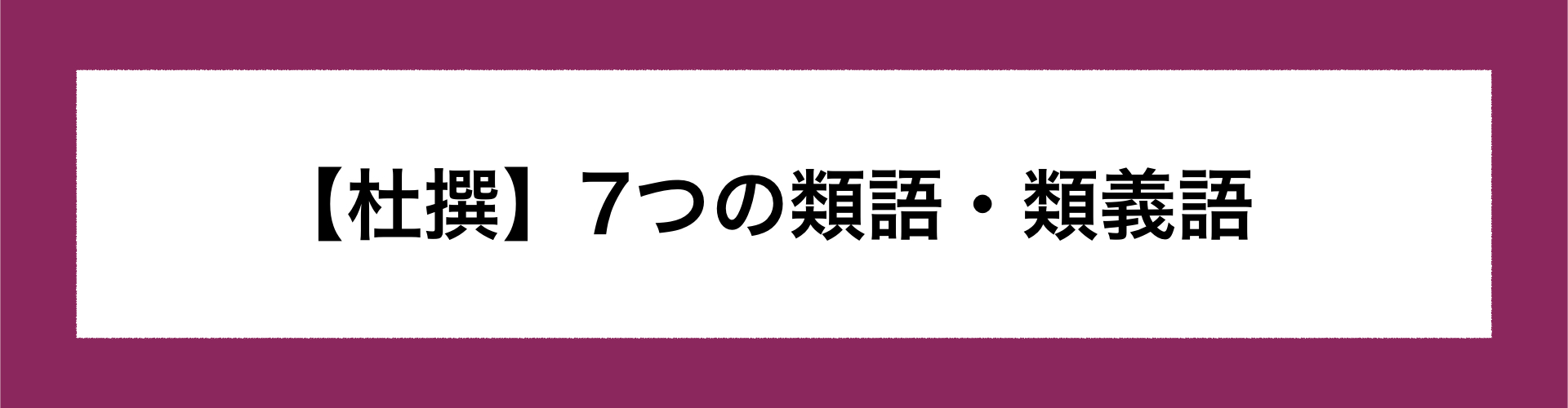

【杜撰】の類語・類義語には「ぞんざい」「生半可」などがあります。
| 【杜撰】7つの類語・類義語 | ||
| 1 | ぞんざい | 物事の扱いが雑でいい加減なこと |
| 2 | 生半可 (なまはんか) |
中途半端で十分でないこと |
| 3 | 与太 (よた) |
いい加減でデタラメなこと |
| 4 | 粗漏・疎漏 (そろう) |
物事の扱いかいい加減で、不十分な点があること |
| 5 | 大雑把 (おおざっぱ) |
細部までこだわらず、大まかなこと |
| 6 | 出鱈目 (でたらめ) |
いい加減なこと |
| 7 | おざなり | いい加減に物事を済ませること |
【杜撰】5つの反対語・対義語
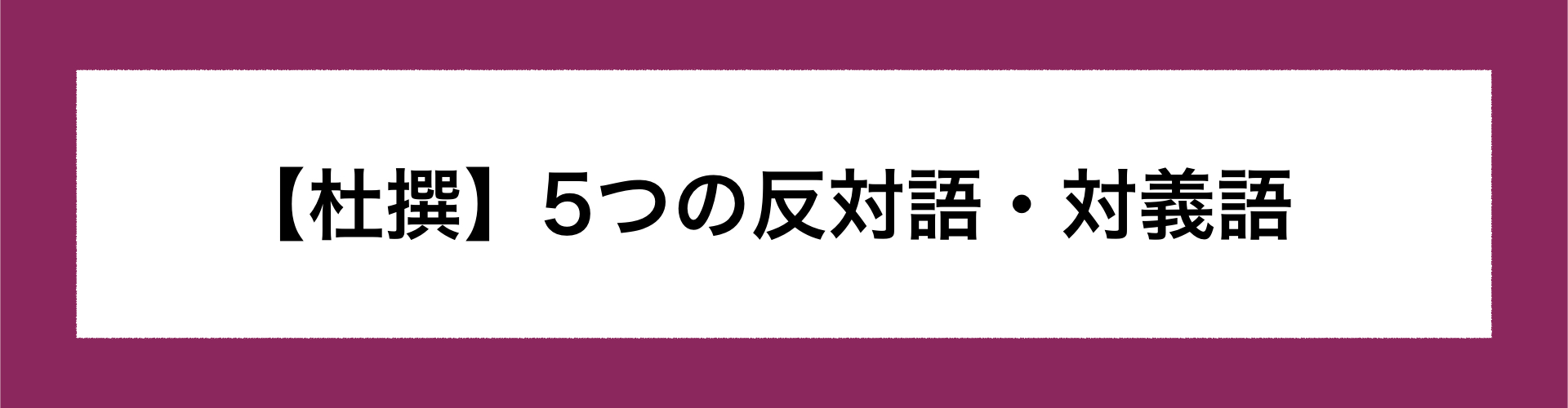

【杜撰】の反対語・対義語には「緻密」「綿密」などがあります。
| 【杜撰】5つの反対語・対義語 | ||
| 1 | 緻密 (ちみつ) |
きめ細かく、細部まで行き届いていること |
| 2 | 綿密 (めんみつ) |
細かく注意が行き届いていること |
| 3 | 丁寧 (ていねい) |
注意深く念入りで、細部まで注意の行き届いていること |
| 4 | 入念 (にゅうねん) |
細かい点にもよく注意すること |
| 5 | 精密 (せいみつ) |
細部まで巧みに作られていること、細部まで注意の行き届いていること |
【杜撰】5つの英語表現
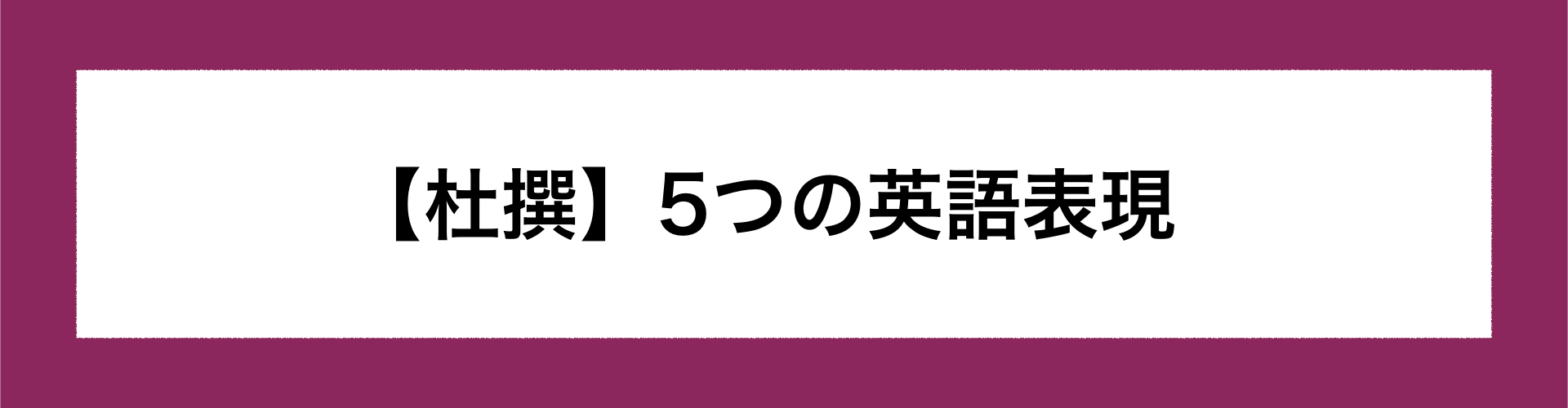

【杜撰】の英語表現には「sloppy」「careless」などがあります。
| 【杜撰】5つの英語表現 | ||
| 1 | sloppy | いい加減な |
| 2 | careless | 不注意な |
| 3 | slipshod | だらしのない、いい加減な |
| 4 | slovenly | だらしのない |
| 5 | loose | ゆるんだ、粗い |
【杜撰】4つの中国語表現
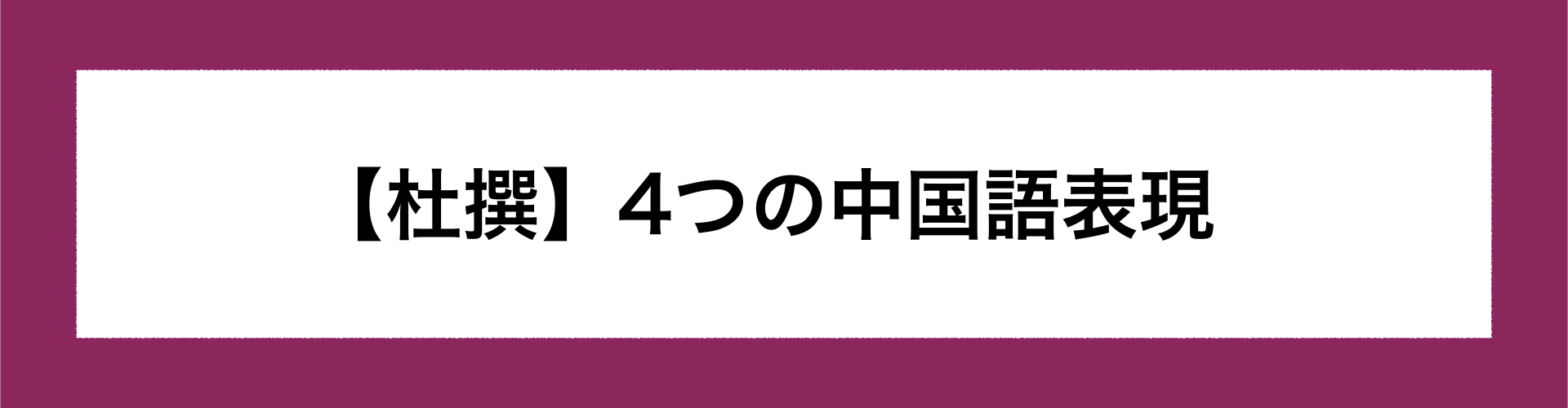

【杜撰】の中国語表現は、「杜撰」「稀松」などです。
| 【杜撰】5つの英語表現 | ||
| 1 | 杜撰(dùzhuàn) | でっちあげる、いい加減に作る |
| 2 | 稀松(Xīsōng) | いい加減、だらけている |
| 3 | 草率(Cǎoshuài) | ぞんざい、いい加減 |
| 4 | 粗劣(Cūliè) | 粗い |
中国語の「杜撰」は、でっちあげるという意味が強いです。



