伝来したのは、乾燥させ糸を引かない【納豆】でしたが、日本で発展し、室町時代にはネバネタと糸を引く【納豆】が一般に広まりました。
歴史のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。


| 【納豆】7つの起源 | |
| 「縄文時代」説 | 「弥生時代」説 |
| 「聖徳太子」説 | 「源義家(八幡太郎)」説 |
| 「光厳法皇」説 | 「加藤清正」説 |
| 「中国」説 | |
起源のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。
有力なのは、お寺の納所(事務所)で作られていた説です。
元々は精進料理として、お坊さんがお寺の納所で作っていたので、納所の字をとって【納豆】という名前がつけられました。
由来・語源のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。

知りたい項目をクリックして下さい。
| ①歴史 |
| ②起源 |
| ③由来・語源 |
| ④【納豆】と「豆腐」は漢字が逆なのかを解説 |
| ⑤賞味期限/冷凍保存と解凍について |
| ⑥種類 |
| ⑦納豆の日 |
| ⑧ケロポンズの「糸引き納豆」 |


【納豆】の歴史

【納豆】の歴史と起源
- ❶発祥国は中国
- ❷ 【納豆(糸引き納豆)】が一般に広まったのは室町時代
- ❸【納豆】という言葉が載っている最古の書物「新猿楽記」

【納豆】の発祥国は中国
中国では、紀元前2世紀頃から、大豆を発酵させた豉(し)という食べ物が存在していました。
「豉」は、乾燥させ糸を引かない「塩辛納豆(寺納豆・浜納豆)」の元祖で、奈良時代に調味料の一種として持ち込まれました。
その後、平安時代に中国へ留学したお坊さんが「豉」を再び国内に持ち帰り、お寺で作るようになりました。
お寺で作られたので「寺納豆」と呼ばれ、現在でも京都の大徳寺(大徳寺納豆)や一休寺(一休寺納豆)などで作られています。
平安時代に書かれた法令集・延喜式(えんぎしき)には、「豉」の製造方法も書かれています。
【納豆(糸引き納豆)】が一般に広まったのは室町時代
現在食べられている、ネバネタと糸を引く【納豆(糸引き納豆)】が一般に広まったのは室町時代です。
中国から伝わった「豉」が日本で発展し、日常食として食べられるようになりました。
室町時代に書かれた、御伽草子「精進魚類物語」では、擬人化された【納豆】が登場します。
室町時代は、主に納豆汁として食べられていたようです。
現在のように醤油をかけた納豆をご飯にのせて食べるようになったのは、江戸時代のことです。
【納豆】という言葉が載っている最古の書物「新猿楽記」
【納豆】という言葉が載っている最古の書物は、平安時代に藤原明衡(ふじわらあきひら)が書いた「新猿楽記(しんさるがくき)」です。
「新猿楽記」は、当時の庶民の生活などが書かれた書物です。
ここに書かれている納豆は、乾燥させ糸を引かない「塩辛納豆」と言われています。
【納豆】7つの起源
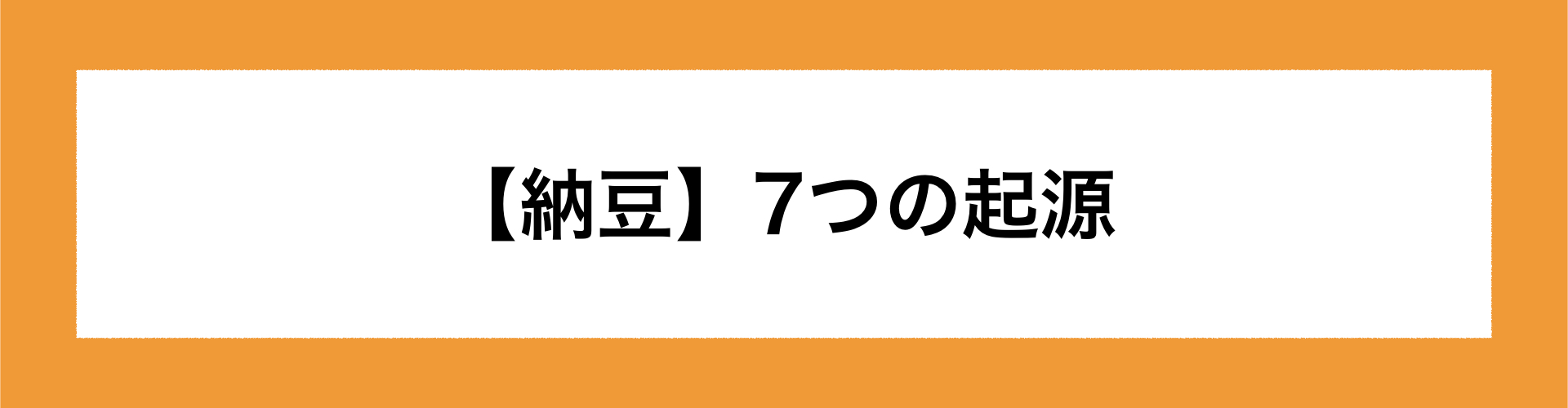
起源
- ❶「縄文時代」説
- ❷「弥生時代」説
- ❸「聖徳太子」説
- ❹「源義家(八幡太郎)」説
- ❺「光厳法皇」説
- ❻「加藤清正」説
- ❼「中国」説

【納豆】の起源には、7つの説がありますが、定説はありません。
その1(「縄文時代」説)
縄文時代には、納豆のような食べ物が存在していたと言われています。
縄文土器から大豆など豆が見つかり、縄文時代に大豆が食べられていたことがわかっています。
縄文時代は、まだ稲作伝来前で藁はありませんが、葉や草で包んで発酵させていたと言われています。
その2(「弥生時代」説)
弥生時代は、中国大陸から大豆や稲作などが伝来し、住居には藁(わら)が使われていました。
また、調理・暖房・照明のため、住居の中に炉(日を使うところ)が作られるようになりました。
枯れた藁には、多くの納豆菌が生育しています。
住居の中で炉が作られるようになり、温度と湿度が納豆菌の繁殖に適した状態になり、偶然に納豆ができたと考えられています。
その3(「聖徳太子」説)
聖徳太子が、自身の馬に食べさせていた煮豆が余ったため、藁に包んで保存していました。
数日経つと、煮豆が発酵して糸を引く豆になっていました。
食べてみると美味しかったので、聖徳太子は人々に作り方を教え、広めたそうです。
その4(「源義家(八幡太郎)」説)
平安時代、源義家が東北に遠征したときのことです。
煮た大豆を熱いまま藁に包んで運んでいたところ、数日後、香ばしい匂いがしてきました。
藁を開けてみると、煮豆が糸を引いていました。
食べてみると美味しかったので、周囲に広めたそうです。
その5(「光厳法皇」説)
南北朝時代、光厳法皇(こうごんてんのう)が丹波山の常照寺で修行をしていたときのことです。
村人から、煮豆を藁で包んだものを大量に献上されました。
毎日少しずつ食べていると、やがて糸を引くようになります。
腐ってしまったのかと思いながらも捨てずに食べてみると、とても美味しかったそうです。
このことを法皇から聞いた村人は、糸を引く豆を作り始めました。
その6(「加藤清正」説)
安土桃山時代、戦国大名・加藤清正(かとうきよまさ)は、朝鮮出兵の時に煮豆を藁に包んで運んでいました。
数日後、香ばしい匂いがするので藁を開いてみると、豆が糸を引いていました。
腐ってしまったのかと思いながらも捨てずに食べてみると、とても美味しかったそうです。
この事は豊臣秀吉にも伝えられ、一般にも広まったとされています。
その7(「中国」説)
中国には、もともと納豆と同じようにネバネバと糸を引くような発酵食品があったそうです。
それがそのまま日本に伝わったとする説です。
その発酵食品は姿を消してしまい、現在は残っていないようです。
【納豆】4つの由来・語源
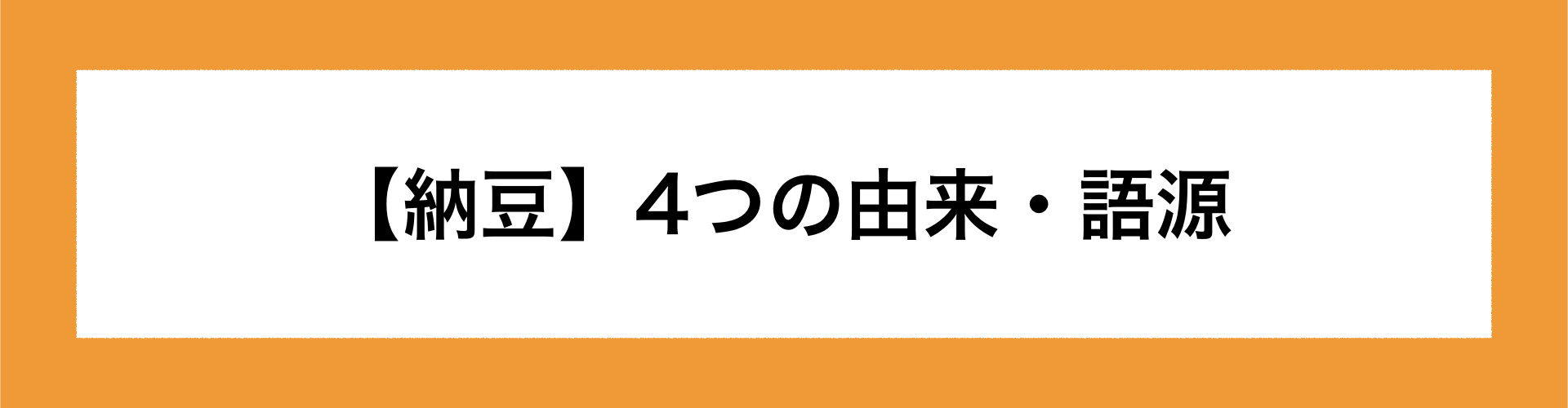
由来・語源
- ❶「お寺の納所(事務所)で作られていた」説
- ❷「藁に納められていた」説
- ❸「納めた豆」説
- ❹「寺院を通じて伝来した」説
- ❺ 都市伝説的な由来・語源

【納豆】には、4つの由来・語源がありますが、定説はありません。
「お寺の納所(事務所)で作られていた」説が有力説です。
その1(「お寺の納所(事務所)で作られていた」説)
【納豆】は、お寺の納所(事務所)で作られていたことに由来する説です。
【納豆】は、元々は精進料理として、お坊さんがお寺の納所で作っていました。
納所の字をとって【納豆】という名前がつけられました。
江戸時代の食物書「本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)」にも書かれている説です。
その2(「藁に納められていた」説)
【納豆】は、藁に納められていたことに由来する説です。
【納豆】は、かつては藁を束ねた「苞(つと)」という包みの中で発酵させて作られていました。
藁に納めた豆なので【納豆】という名前がつけられました。
その3(「納めた豆」説)
【納豆】は、納めた豆に由来する説です。
【納豆】は、壺や桶に納めて貯蔵され、神様や将軍に納めていた豆でした。
このように「納めた豆」なので【納豆】という名前がつけられました。
その4(「寺院を通じて伝来した」説)
【納豆】は、寺院を通じて伝来したという説です。
【納豆】の発音は、「納」の呉音である「なっ」と、「豆」の漢音である「とう」が合わさったものです。
呉音、漢音はどちらも中国に由来する音で、呉音は仏教語に多く使われています。
このことから、【納豆】という言葉は、寺院を通じて伝来したと言われています。
都市伝説的な由来・語源
【納豆】の都市伝説的な由来・語源は、豆腐と間違えられた俗説です。
中国から日本に伝来したときに、【納豆】と「豆腐」の名前が入れ替わってしまったというものです。
豆腐の「腐」は「柔らかいもの、固まる」という意味があり、「豆腐」の漢字は間違ってはいません。
また、【納豆】は日本で生まれた言葉なので、間違えられたということはないのです。
【納豆】と「豆腐」は漢字が逆なのかを解説
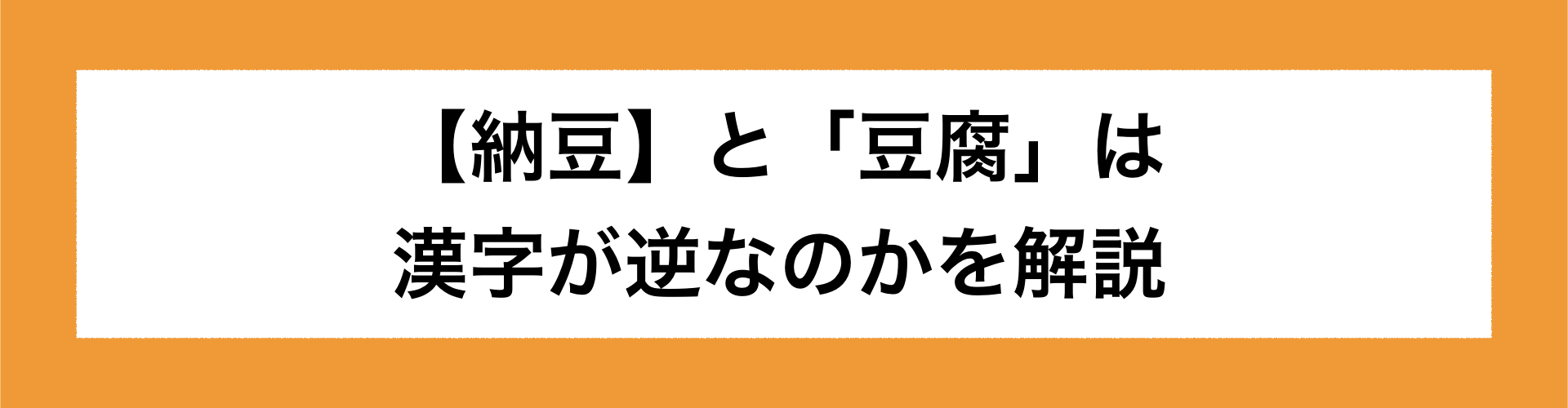
【納豆】と「豆腐」は、漢字が逆ではありません。
豆が納まるで【納豆】、豆が腐るで「豆腐」。
【納豆】は大豆を発酵(腐敗)させたもので、「豆腐」は四角い型に納めて固められたもので、漢字が逆なような気がしますが、逆ではありません。
豆腐の「腐」は「柔らかいもの、固まる」という意味があり、中国語でも同じ「豆腐」の漢字が使われています。
豆が固まったものなので、漢字は「豆腐」でOKなのです。
【納豆】は、お寺の納所で作られていたので、納所の字をとって【納豆】という名前がつけられたのが有力説です。
なのでこちらも、漢字は【納豆】でOKなのです。
【納豆】の賞味期限/冷凍保存と解凍について
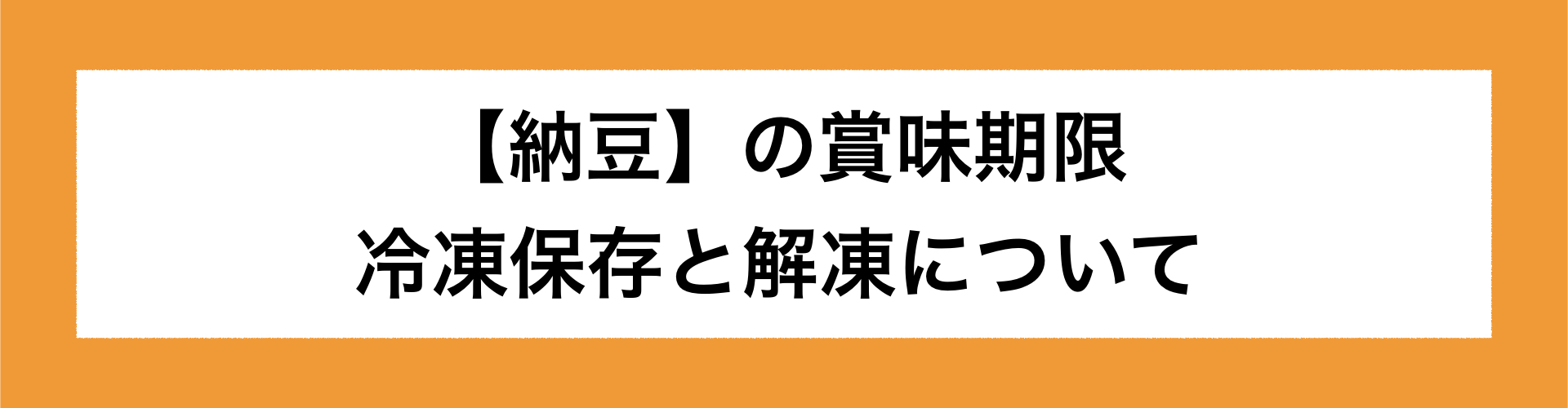
賞味期限/冷凍保存と解凍について
- ❶賞味期限
- ❷冷凍保存と解凍について

賞味期限
【納豆】は腐っている食べ物だと誤解されていることがありますが、間違いです。
腐っている食べ物ではなく、納豆菌で大豆を発酵させた食べ物です。
【納豆】も腐るので、賞味期限が切れてしまったら状態をよく確認し、無理に食べないほうがよさそうです。
冷凍保存と解凍について
【納豆】は、冷凍保存することができます。
賞味期限内に食べきれない時は、ラップで包んで冷凍しましょう。
解凍は、食べる半日から1日前に、冷蔵庫に移して自然解凍します。
一度解凍したものは早めに食べましょう。
納豆は劣化に気づきにくい食品なので、食べる前ににおいや色など状態をよく確認しましょう。
【納豆】の種類

種類
- ❶糸引き納豆
- ❷塩辛納豆

【納豆】には大きく2つの種類があります。
ネバネバと糸を引く「糸引き納豆」と乾燥させ糸を引かない「塩辛納豆(寺納豆・浜納豆)」です。
糸引き納豆
「糸引き納豆」は、大豆を納豆菌で発酵させたもので、ネバネバと糸を引く納豆です。
「糸引き納豆」には、「丸大豆納豆」「ひきわり納豆」「五斗納豆」の3つの種類があります。
| 「糸引き納豆」3つの種類 | ||
| 1 | 丸大豆納豆 (まるだいずなっとう) |
大豆を丸ごと納豆菌で発酵させたもの |
| 2 | ひきわり納豆 | 砕いた大豆を納豆菌で発酵させたもの |
| 3 | 五斗納豆 (ごとなっとう) |
ひきわり納豆に麹や塩を混ぜて発酵、成熟させたもの |
「五斗納豆」は、山形県米沢地方に保存食として伝わる食べ物で、現在は「雪割納豆」という名前で販売されています。
塩辛納豆
「塩辛納豆」は、大豆を麹で発酵させて乾燥させたものです。
糸を引かない納豆で、「寺納豆」「浜納豆」とも呼ばれます。
「納豆の日」とは
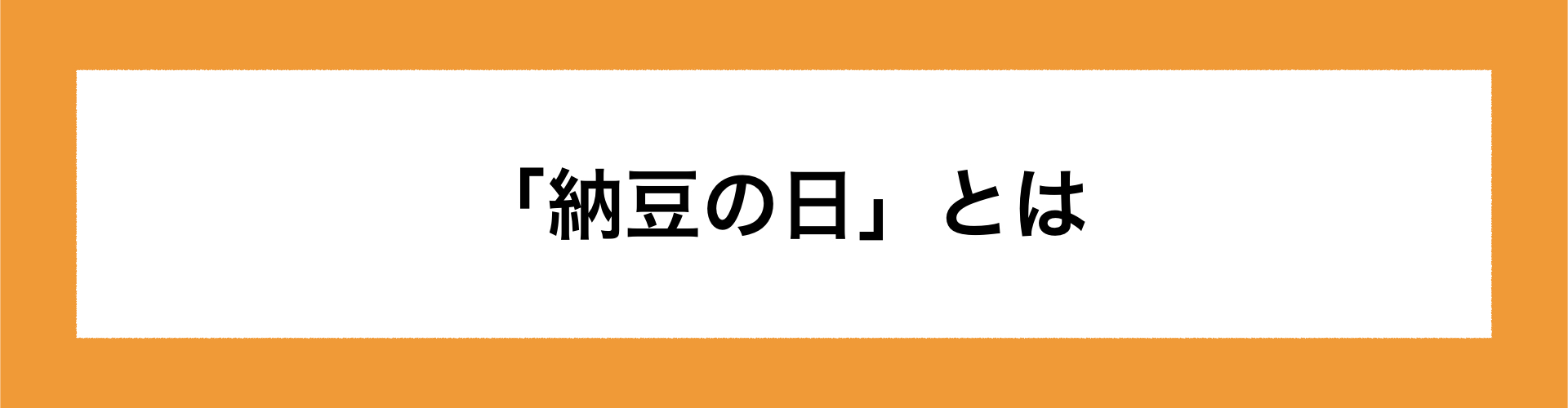

7月10日が「納豆の日」に制定されています。
日付は「なっ(7)とう(10)」(納豆)の語呂合わせで、7月10日となりました。
1981年、関西での納豆の消費拡大を目的に、関西納豆工業協同組合により、関西限定の記念日として制定されました。
その後1992年に、全国納豆工業協同組合連合会により、改めて全国的な記念日として制定されました。
ケロポンズの「糸引き納豆」

音楽ユニット「ケロポンズ」が、「糸引き納豆」という曲を出しています。
ネバネバネバーというメロディーと、体操のようなダンスが子供に大人気です。
ケロポンズは、子供向けの音楽やダンスを作る2人組の音楽ユニットで、増田裕子さんと平田明子さんにより、1999年に結成されました。







