意味のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。


| 修正前 | 「僧は推す月下の門」 |
| 修正後 | 「僧は敲く月下の門」 |
賈島は悩んだ結果、長安の長官であり、唐詩四大家の一人である韓愈(かんゆ)の助言を受け「推す」→「敲く」に改めました。
| 推す | 門を推すと開く(閂がかかっていない状態) |
| 敲く | 推しても門が開かないので叩いている(閂がかかっている状態) |
「閂(かんぬき)」とは、昔使われていた鍵の一種で、門の扉が開かないようにする棒状の金物や横木のことです。
閂がかかっている状態は、お客さんがくるとは思っていない状態なので、不意にお客さんがきたという感激を表すことができます。
この故事から、文章や俳句などを作るときに、何度も練り直す意味で【推敲】が使われるようになりました。
由来・語源のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。
知りたい項目をクリックして下さい。
| ①意味・読み方 |
| ② 由来・語源 |
| ③ 例文・使い方 |
| ④ 漢文の現代語訳・書き下し文 |
| ⑤【推敲】と意味・由来が同じ四字熟語「月下推敲」 |
| ⑥類語・類義語 |
| ⑦英語表現 |
| ⑧対義語・反対語 |

| 【推敲】と意味・由来が同じ四字熟語 |
| 月下推敲 |

| 【推敲】8つの類語・類義語 | |||
| リライト | 手直し | 添削 | 訂正 |
| 修正 | 校正 | 校閲 | 加筆 |

| 【推敲】6つの類語 | |
| work on one’s manuscript to improve the wording | refine |
| polish | improve |
| rewrite | elaboration |

| 【推敲】の反対語・対義語 |
| 杜撰 |


【推敲(すいこう)】の意味・読み方
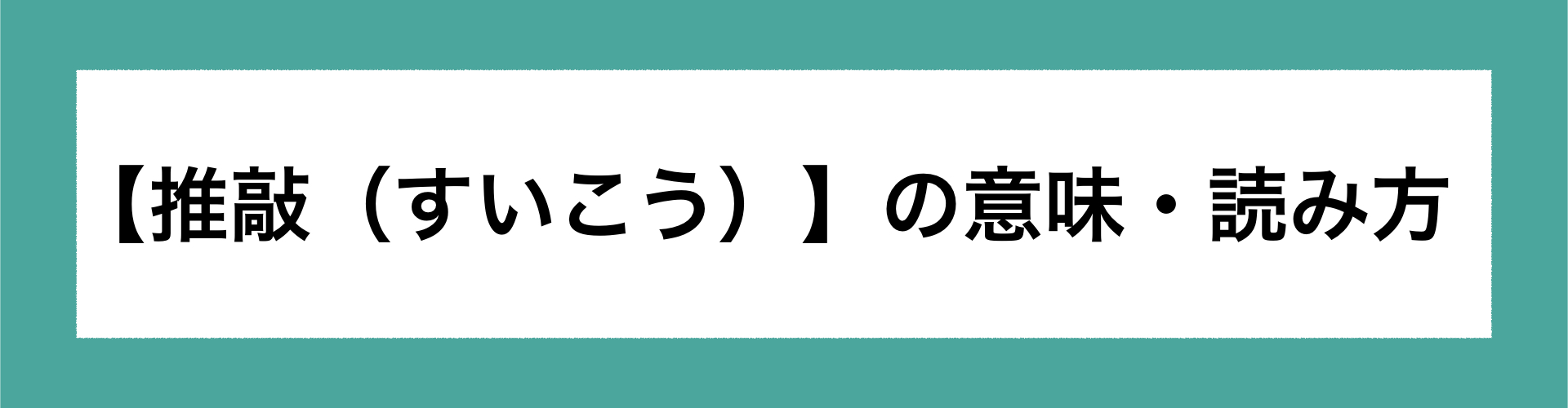
意味・読み方
- ❶【推敲(すいこう)】の意味
- ❷「推」の意味
- ❸「敲」の意味
- ❹【推敲】の読み方

【推敲(すいこう)】の意味
【推敲】とは、文章や俳句などを作るときに、何度も練り直すことです。
| 【推敲】の意味 |
| 文章や俳句などを作るときに、より良いものにしようと何度も練り直すこと |
「推」の意味
「推」は、後ろから力を加え、物事を更に前方へやるという意味です。
| 「推」の意味 |
| ・後ろから力を加え、物事を更に前方へやる ・何かを推薦する |
「推」は、音読みで「すい」、訓読みで「おす」と読みます。
「敲」の意味
「敲」は、指先や拳で軽くたたくことです。
| 「敲」の意味 |
| ・指先や拳で軽くたたくこと ・トントンたたくこと |
「敲」は、音読みで「こう」、訓読みで「たたく・むち」と読みます。
【推敲】の読み方
【推敲】は「すいこう」と読みます。
「推考」と書かれることがありますが、間違いです。
【推敲】の由来・語源となった故事とは/出典は「唐詩紀事(とうしきじ)」
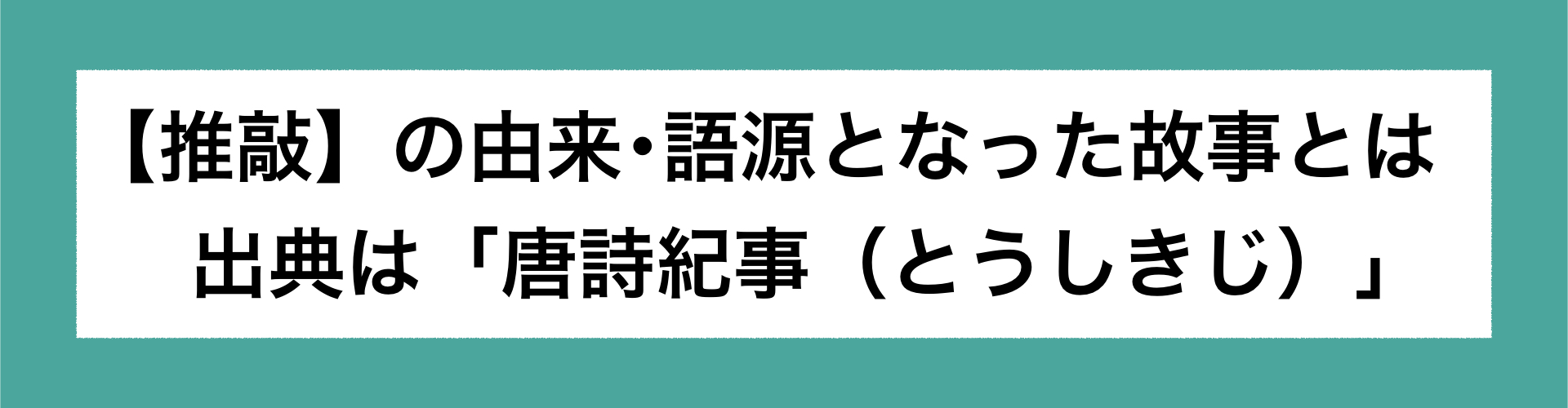
由来・語源
- ❶由来・語源となった故事/あらすじ
- ❷故事の出典は「唐詩紀事(とうしきじ)」
- ❸賈島の詩「題李凝幽居(李凝の幽居に題す)」
- ❹なぜ「敲く(たたく)」なのか

由来・語源となった故事/あらすじ
由来は、中国の唐時代の詩人・賈島(かとう)が、「李凝(りぎょう)の幽居に題す」という詩を作った時の逸話です。
詩の中の「僧は推す月下の門」という句の、「推す(おす)」を「敲く(たたく)」に直すか迷っていました。
夢中で考えていた賈島は、長安の長官であり、唐詩四大家の一人である韓愈(かんゆ)の行列にぶつかってしまいます。
ぶつかった理由を尋ねられた賈島が韓愈に迷っていることを相談すると、韓愈は「敲くにしたほうが良い」と助言します。
この助言を受け、賈島は「推す」→「敲く」に改めました。
このことから、文章や詩を練り直す意味で「推敲」が使われるようになりました。
故事の出典は「唐詩紀事(とうしきじ)」
【推敲】の由来・語源となった故事は、中国の唐代の書物「唐詩紀事(とうしきじ)」に書かれています。
「唐詩紀事」は、唐時代の詩人について、詩や逸話、小伝、評論などをまとめた書物です。
取り上げられている詩人は1150人で、この書物によって後世に伝わった詩人・作品は非常に多いです。
唐詩研究の重要な資料とされている書物です。
賈島の詩「題李凝幽居(李凝の幽居に題す)」
「僧は推す月下の門」は、「題李凝幽居(李凝(りぎょう)の幽居(ゆうきょ)に題す)」の一節です。
「五言律詩(ごごんりっし)」といい、一句五字、八句でできている詩です。
| 「題李凝幽居(李凝の幽居に題す)」 |
| 閑居少鄰並(閑居 鄰並 少に) 草径入荒園(草径 荒園に入る) 鳥宿池中樹(鳥は宿る 池辺の樹) 僧敲月下門(僧は敲く 月下の門) 過橋分野色(橋を過ぎて 野色を分かち) 移石動雲根(石を移して 雲根を動かす) 暫去還來此(暫く去りて 還た此に来たれば) 幽期不負言(幽期 言に負(そむ)かず) |
| 「題李凝幽居(李凝の幽居に題す)」の現代語訳 |
| この閑静な住まいには、隣家もなく、草の小道は荒れた庭に続いている。 鳥は池辺の木にとまっている。 僧は月あかりの下、門をたたいた。 橋を渡っても野原の景色が続き、雲のわく石を山中から移し置いている。 しばらく離れていたが、再びここへ来た。 約束は、決して破ったりはしない。 |
なぜ「敲く(たたく)」なのか
韓愈が「敲く(たたく)」を選んだのは、感激をより強く伝えるためです。
「推す」と「敲く」では、次のような違いがあります。
| 推す | 門を推すと開く(閂がかかっていない状態) |
| 敲く | 推しても門が開かないので叩いている(閂がかかっている状態) |
「閂(かんぬき)」とは、昔使われていた鍵の一種で、門の扉が開かないようにする棒状の金物や横木のことです。
閂がかかっている状態は、お客さんがくるとは思っていない状態なので、不意にお客さんがきたという感激を表すことができます。
【推敲】例文・使い方
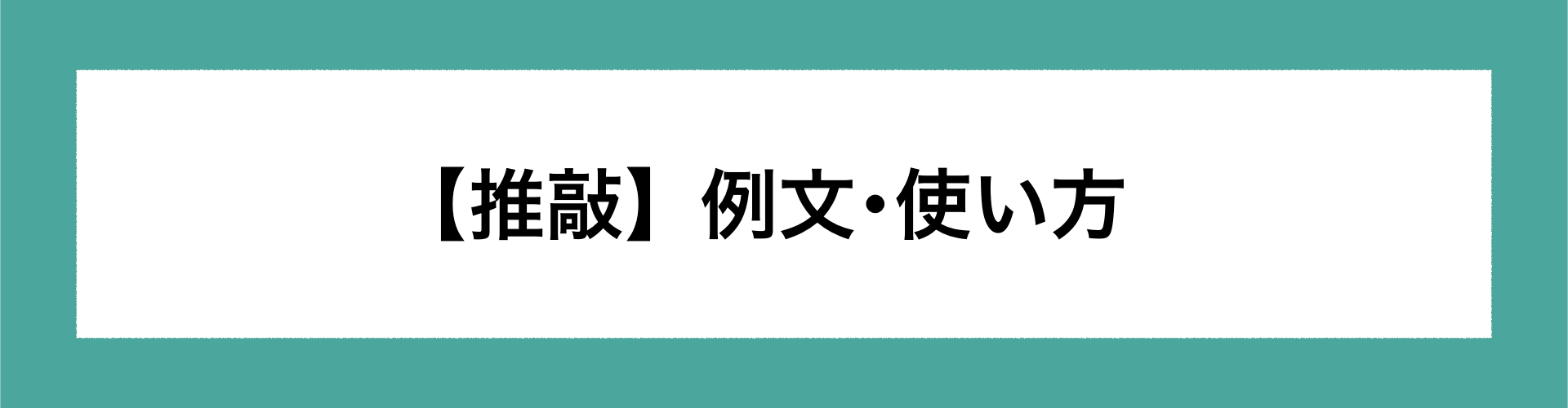
例文・使い方
- ❶例文
- ❷使い方

例文/簡単な短文で
| 例文1 | 文章を推敲することで、より良い小説が完成する。 |
| 例文2 | 論文は推敲中だ。 |
| 例文3 | この文章は、推敲のあとが感じられない。 |
| 例文4 | 推敲に推敲を重ねて、卒論が完成した。 |
| 例文5 | 推敲を加えたら、とてもいい句が完成した。 |
使い方
【推敲】は、「推敲を重ねる」「推敲する」「推敲を加える」「推敲中」などの言い回しで使われることが多いです。




【推敲】漢文の現代語訳・書き下し文
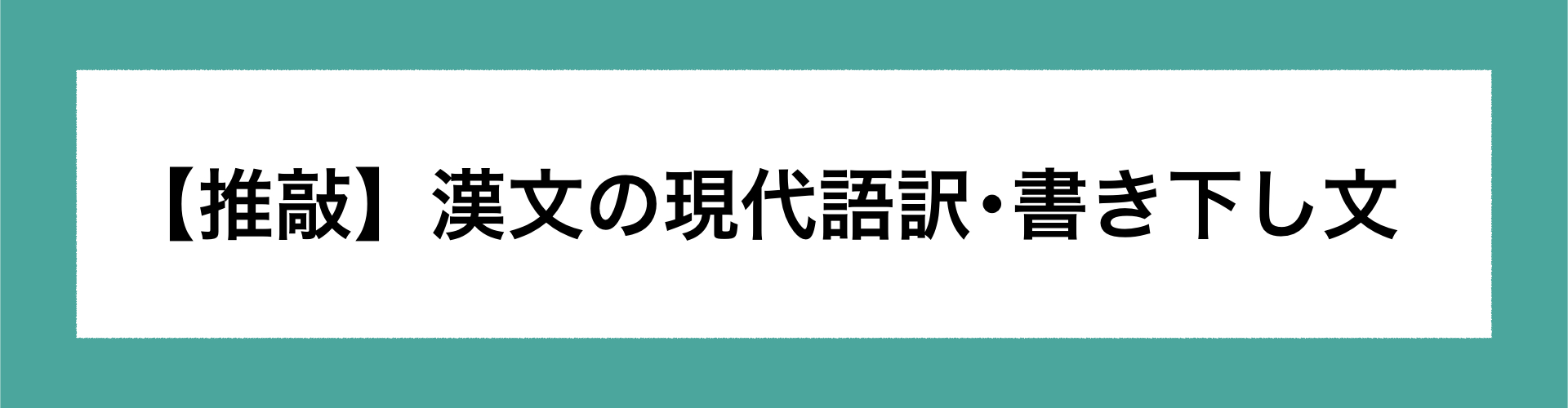

| 原文・白文 | 賈島赴挙至京、 |
| 書き下し文 | 賈島(かとう)挙(きょ)に赴きて京(けい)に至り |
| 読み方 | かとう きょにおもむきて けいにいたり、 |
| 現代語訳 | 賈島が科挙を受けるために都(長安)に行き、 |
| 原文・白文 | 騎驢賦詩、 |
| 書き下し文 | 驢に騎りて詩を賦し、 |
| 読み方 | ろに のりて しをふし、 |
| 現代語訳 | ロバに乗って詩を作っていると、 |
| 原文・白文 | 得僧推月下門之句。 |
| 書き下し文 | 「僧は推す月下の門」の句を得たり。 |
| 読み方 | 「そうはおす げかのもん」のくをえたり。 |
| 現代語訳 | 「僧は推す月下の門」という句ができた。 |
| 原文・白文 | 欲改推作敲。 |
| 書き下し文 | 推を改めて敲と作さんと欲す。 |
| 読み方 | すいをあらためて こうをなさんとほっす。 |
| 現代語訳 | しかし、「推す」を改めて「敲(たたく)」という文字にしたいと思った。 |
| 原文・白文 | 引手作推敲之勢、未決。 |
| 書き下し文 | 手を引きて推敲の勢いを作すも、未まだ決せず。 |
| 読み方 | てをひきて すいこうの いきおいをなすも、いまだけっせず。 |
| 現代語訳 | 手動かして推すと敲くの仕草をしてみたが、まだ決まらない。 |
| 原文・白文 | 不覺衝大尹韓愈。 |
| 書き下し文 | 覚えず大尹韓愈に衝たる。 |
| 読み方 | おぼえず たいいん かんゆにあたる。 |
| 現代語訳 | 思わず大尹(都の長官)の韓愈(の列)に突っ込んでしまった。 |
| 原文・白文 | 乃具言。 |
| 書き下し文 | 乃ち具に言ふ。 |
| 読み方 | すなわち つぶさにいう。 |
| 現代語訳 | (賈島は)そこで、(列に突っ込んでしまった理由を)詳しく説明した。 |
| 原文・白文 | 愈曰、敲字佳矣。 |
| 書き下し文 | 愈曰はく、敲の字佳し と。 |
| 読み方 | ゆいわく、こうのじよしと。 |
| 現代語訳 | 韓愈は「敲の字が良い」 と言った。 |
| 原文・白文 | 遂竝轡論詩。 |
| 書き下し文 | 遂に轡を並べて詩を論ずること之を久しくす。 |
| 読み方 | ついに くつわをならべて しをろんずること これをひさしくす。 |
| 現代語訳 | 二人はたづなを並べて進みながら、しばらく詩について論じ合った。 |
【推敲】と意味・由来が同じ四字熟語「月下推敲」
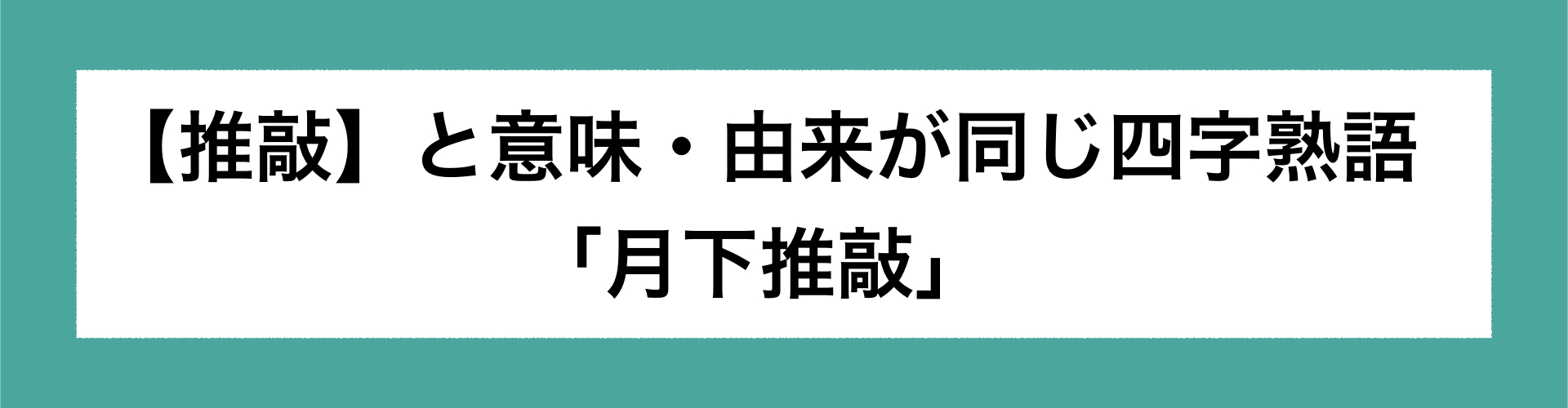
【推敲】と意味・由来が同じ四字熟語に「月下推敲(げっかすいこう)」があります。
「月下推敲」は、文章や俳句などを作るときに、何度も練り直すことです。
| 「月下推敲(げっかすいこう)」 | |
| 意味 | 文章や俳句などを作るときに、何度も練り直すこと |
| 出典 | 唐詩紀事(とうしきじ) |
【推敲】8つの類語・類義語
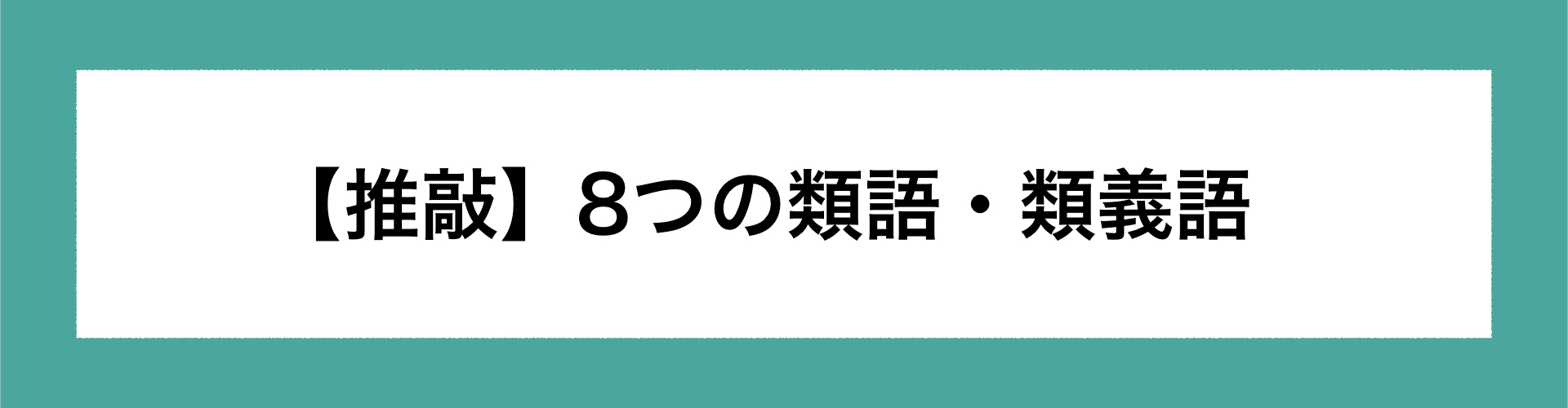
類語・類義語
- ❶8つの類語・類義語
- ❷【推敲】と「校正」の違いとは

【推敲】8つの類語・類義語
【推敲】とは、文章や俳句などを作るときに、何度も練り直すことです。
類語・類義語は次のようになります。
| 【推敲】8つの類語・類義語 | ||
| 1 | リライト | 文章を書き直すこと |
| 2 | 手直し・てなおし | 不完全なものを直すこと |
| 3 | 添削・てんさく | 文章などを削ったり書き加えたりして、よりよくすること |
| 4 | 訂正・ていせい | 誤りを正しく直すこと |
| 5 | 修正・しゅうせい | よくない点を改めること |
| 6 | 校正・こうせい | 文字や文章の誤りを修正すること |
| 7 | 校閲・こうえつ | 文章の内容に誤りがないか確認し、修正すること |
| 8 | 加筆・かひつ | 文章を直したり、書き加えたりすること |
【推敲】と「校正」の違いとは
【推敲】と「校正」の違いは、誤字脱字の修正です。
どちらも「文章を直す」という意味は同じですが、「校正」には誤字脱字など、表記の間違いの修正という意味が込められています。
| 【推敲】と「校正」の違い | |
| 推敲 | ・文章や俳句などを作るときに、何度も練り直すこと ・文章をよりよくするための修正 |
| 校正 | ・文字や文章の誤りを修正すること ・誤字脱字など、表記の間違いの修正 |
【推敲】6つの英語表現
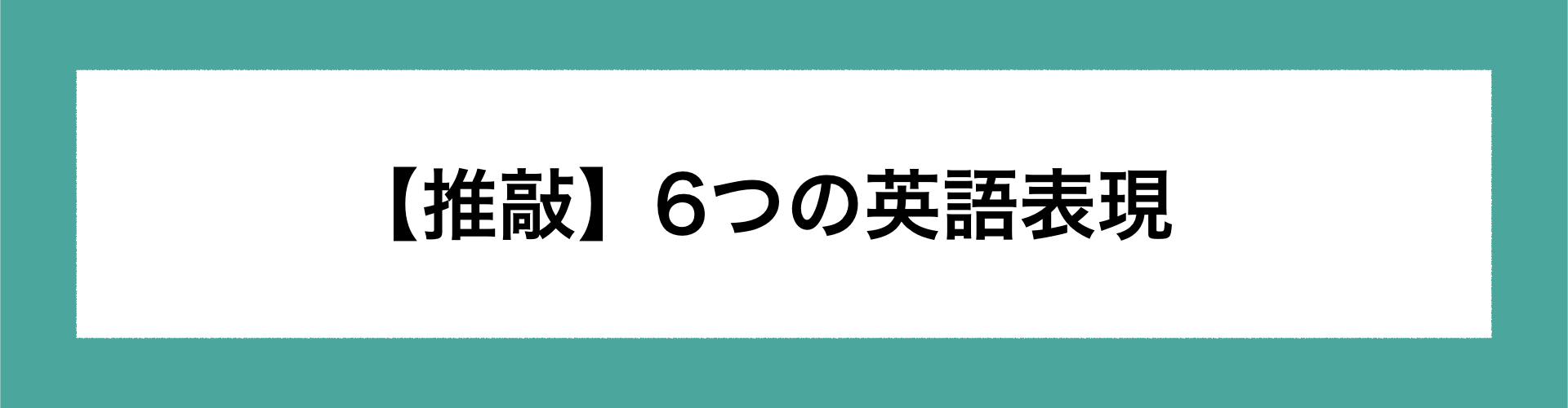
英語表現
- ❶6つの英語表現
- ❷英語の例文

6つの英語表現
【推敲】には、6つの英語表現があります。
| 【推敲】6つの英語表現 | ||
| 1 | work on one’s manuscript to improve the wording | |
| 推敲する | ||
| 2 | refine | |
| 磨き上げる・洗練する | ||
| 3 | polish | |
| 推敲する・磨きをかける・仕上げる | ||
| 4 | improve | |
| 改良する・向上させる | ||
| 5 | rewrite | |
| 書き直す | ||
| 6 | elaboration | |
| 推敲・綿密に仕上げる | ||
英語の例文
| 例文1 | To refine a sentence. | |
| 文章を推敲する。 | ||
| 例文2 | The paper still needs to be polished. | |
| 論文は、まだ推敲を加える必要がある。 | ||
【推敲】の対語義・反対語
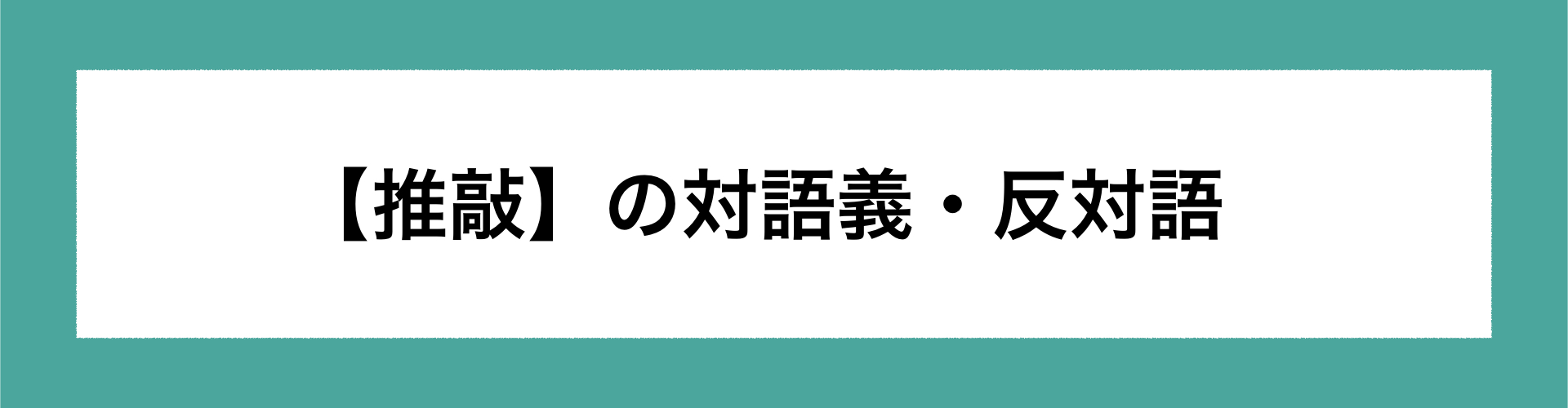

【推敲】の対語義・反対語は、「杜撰(ずさん)」です。
「杜撰」とは、誤りが多くいい加減なことです。
| 「杜撰」の意味 |
| ・文章や詩に典拠の確かでないことを書くこと ・誤りが多くいい加減なこと |





