
春という季節の朝は、寒くもなく暑くもなく、とても心地が良いです。
あまりにも心地が良くて、布団から抜け出せずにゴロゴロしながら、「昨日の雨で花が散ってしまったかな」とどうでもいい事を考えている内容の詩です。
どうでもいい事を考えたり、布団から抜け出せないという怠惰な行動を通して、春の朝の心地良さを表現している詩です。
語源・由来のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。


知りたい項目をクリックして下さい。
| ①意味・読み方 |
| ②語源・由来 |
| ③漢詩の現代語訳・書き下し文 |
| ④幸田露伴の【春暁】/漢詩の現代語訳・書き下し文 |
| ⑤ 類語 |
| ⑥中国語表現 |
| ⑦英語表現 |
| 【春暁】2つの類語 | |
| 春曙 | 有明 |

| 【春暁】の中国語表現 |
| 春晓(chūnxiǎo) |

| 【春暁】2つの英語表現 | |
| 1 | spring dawn |
| 2 | dawn of a spring day |


【春暁】意味と読み方
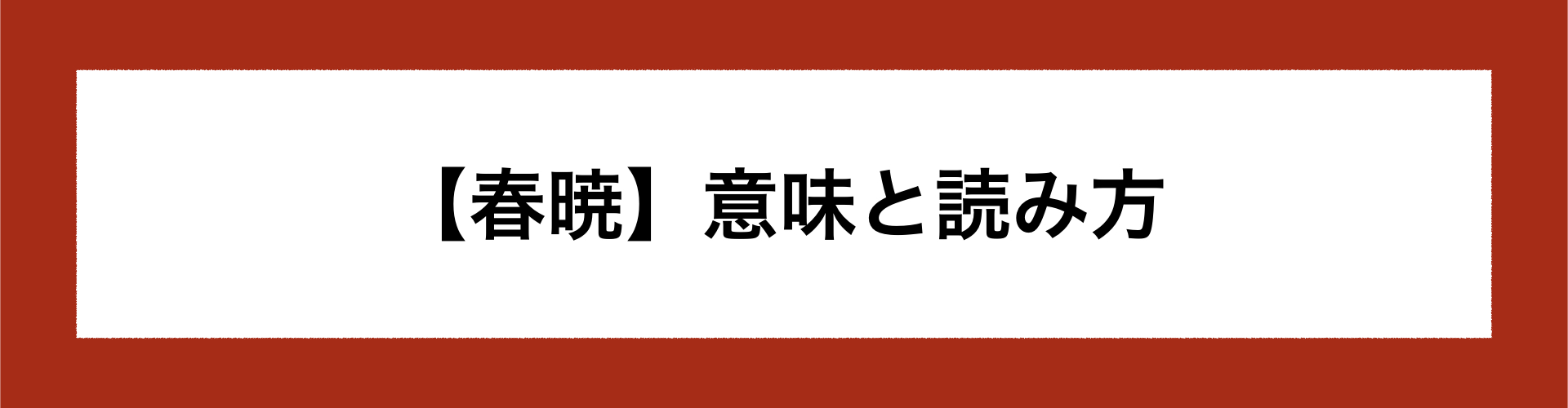
意味と読み方
- ❶【春暁】の意味
- ❷ 【春暁】の読み方

【春暁】の意味
【春暁】の意味は、「春の明け方」です。
| 【春暁】の意味 |
| 春の明け方(まだ薄暗いころ) |
「朝」ではなく、夜が明けようとする、まだ薄暗いころを指します。
【春暁】の読み方
【春暁】の読み方は、「しゅんぎょう」です。
| 【春暁】の読み方 |
| しゅんぎょう |
「暁」が難しいですが、音読みで「ぎょう」と読みます。
「はるあかつき」と読むのは間違いです。
【春暁】語源は中国の漢詩「春暁」に由来

語源・由来・漢詩の現代語訳
- ❶【春暁】語源は中国の漢詩「春暁」に由来
- ❷「春暁」漢詩の現代語訳・書き下し文
- ❸「五言絶句(ごごんぜっく)」とは/押韻の箇所も解説
- ❹ 「孟浩然(もうこうねん)」とは
- ❺「唐詩三百首(とうしさんびゃくしゅ)」とは
- ❻「唐詩選(とうしせん)」とは

【春暁】語源は中国の漢詩「春暁」に由来
【春暁】という言葉は、中国・唐時代の詩人「孟浩然(もうこうねん)」の漢詩、「春暁」に由来します。
「春暁」という詩は、春の朝の心地良さを表現しています。
春という季節の朝は、寒くもなく暑くもなく、とても心地が良いです。
あまりにも心地が良くて、布団から抜け出せずにゴロゴロしながら、「昨日の雨で花が散ってしまったかな」とどうでもいい事を考えている内容の詩です。
どうでもいい事を考えたり、布団から抜け出せないという怠惰な行動を通して、春の朝の心地良さを表現しているのです。
「春暁」は、五言絶句(ごごんぜっく)という形式で書かれています。
中国の詩集である「唐詩三百首(とうしさんびゃくしゅ)」や「唐詩選(とうしせん)」に収められています。
【春暁】漢詩の現代語訳・書き下し文
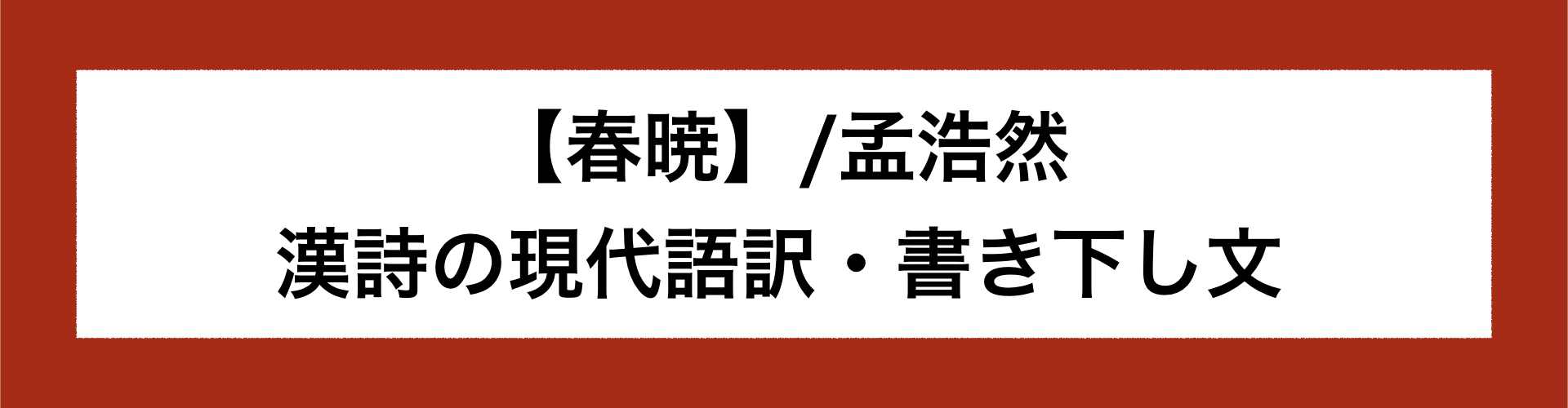
| 原文・白文 | 春眠不覚暁 |
| 読み仮名 | しゅんみん あかつきをおぼえず |
| 書き下し文 | 春眠暁を覚えず |
| 現代語訳 | 春の眠りは心地よいため、夜明に気付かず、なかなか目が覚めない。 |
| 原文・白文 | 処処聞啼鳥 |
| 読み仮名 | しょしょ ていちょうをきく |
| 書き下し文 | 処処啼鳥を聞く |
| 現代語訳 | あちこちから鳥のさえずりが聞こえてくる |
| 原文・白文 | 夜来風雨声 |
| 読み仮名 | やらい ふううのこえ |
| 書き下し文 | 夜来風雨の声 |
| 現代語訳 | 昨夜は、風や雨の音がしていた |
| 原文・白文 | 花落知多少 |
| 読み仮名 | はなおつること しるたしょうぞ |
| 書き下し文 | 花落つること 知る多少ぞ |
| 現代語訳 | 花はどれほど散ったのだろう |
「五言絶句(ごごんぜっく)」とは/押韻の箇所も解説
「五言絶句(ごごんぜっく)」は、中国・唐時代に完成した漢詩の形式の1つです。
1つの詩が4句(4行)で作られているのが「絶句」。
それにプラスして、1句が5文字で作られているのが、「五言絶句」です。
| 【春暁】の押韻が使われている箇所 | |
| 1句 | 春 眠 不 覚 暁 |
| 2句 | 処 処 聞 啼 鳥 |
| 3句 | 夜 来 風 雨 声 |
| 4句 | 花 落 知 多 少 |
このように、全部で20文字と短い形式です。
通常は、2句と4句で韻を踏みますが(押韻)、1句で韻を踏むこともあります。
【春暁】では、押韻が3箇所(1句・2句・4句)で使われています。
「孟浩然(もうこうねん)」とは
「春暁」の作者である「孟浩然(もうこうねん)」は、中国・唐時代に活躍した詩人です。
自然の美をうたった親しみやすい作品が評価されていて、日本では「春暁」が最も有名です。
才能が認められたのは、意外にも遅く40歳の時。
科挙を受験したが失敗してしまい、人生の多くを故郷で過ごしています。
「唐詩三百首(とうしさんびゃくしゅ)」とは
「唐詩三百首(とうしさんびゃくしゅ)」は、中国・清時代に編集された唐詩選集です。
政治家の孫洙(そんしゆ)が編纂し、1763年(乾隆28年)に完成しました。
唐詩の中から選び出された、詩人77人の約300首が載っています。
全8巻で、【春暁】は7巻の五言絶句37首のうちの1つです。
「唐詩選(とうしせん)」とは
「唐詩選(とうしせん)」は、中国・明時代に編集された唐詩選集です。
詩人の李攀竜(りはんりゅう)によって16世紀に編纂されたと伝えられていますが、実際は、書籍商人が編纂したと言われています。
全7巻で、唐詩の中から選び出された、詩人128人の約465首が載っています。
幸田露伴(こうだ ろはん)の【春暁】/漢詩の現代語訳・書き下し文

幸田露伴(こうだ ろはん)の【春暁】
- ❶ 幸田露伴の【春暁】/漢詩の現代語訳・書き下し文
- ❷「幸田露伴(こうだろはん)」とは

幸田露伴の【春暁】/漢詩の現代語訳・書き下し文
孟浩然の【春暁】をテーマに、小説家の幸田露伴が漢詩を書いています。
孟浩然の【春暁】は五言絶句ですが、幸田露伴の【春暁】は七言絶句です。
押韻は3箇所(1句・2句・4句)で、「何・和・多」です。
| 幸田露伴の【春暁】/漢文 |
| 残寒不去奈春何 僅頼鶯声自是和 尤悦衾辺梅蕾子 花開比昨両三多 |
| 幸田露伴の【春暁】/書き下し文 |
| 残寒去らず 春を奈何せん 僅かに頼る 鶯声の自から是れ和するに 尤も悦ぶ 衾辺の梅蕾子 花開くこと 昨に比して両三多きを |
| 幸田露伴の【春暁】/現代語訳 |
| 冬の寒さがまだ残っている、春はいつ来るのだろうか。 かすかに鶯の声が聞こえることで、こころが和んでいる。 特ににうれしいのは、寝床の近くにある梅の蕾が、 昨日よりも咲いて、2.3個増えていることだ。 |
「幸田露伴(こうだろはん)」とは
幸田露伴は、明治時代〜昭和時代に活躍した日本の小説家です。
日本の近代文学を代表する作家の一人で、若い彫刻家の悲恋を描いた「風流仏(ふうりゅうぶつ)」で注目を集めました。
代表作に「五重塔」「運命」などがあります。
昭和12年(1937年)には第一回文化勲章を授与されています。
【春暁】2つの類語
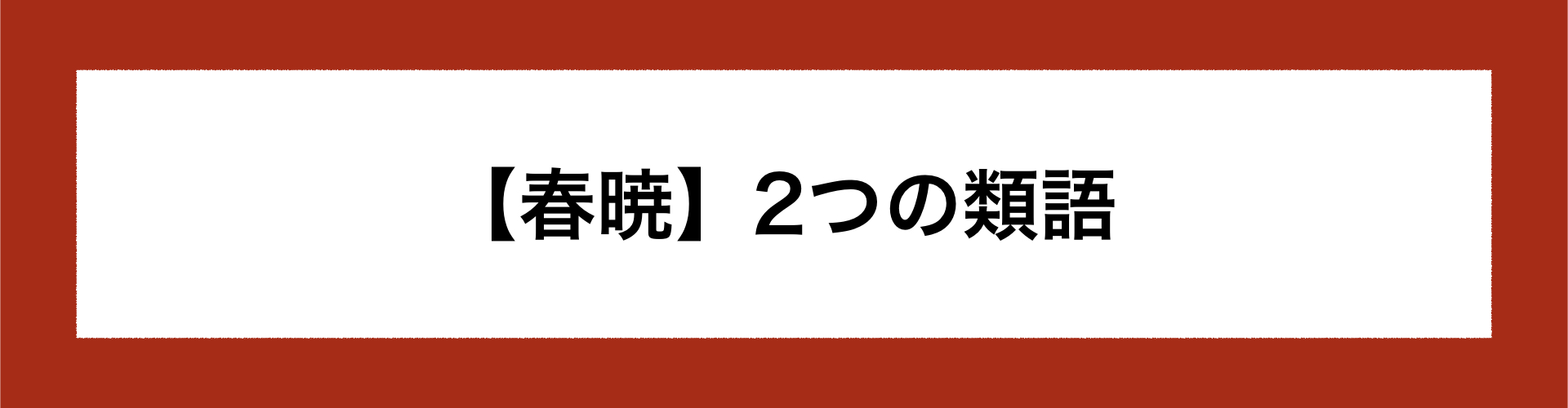
類語
- ❶【春暁】の2つの類語
- ❷【春暁】と「春曙」の違い

【春暁】2つの類語
【春暁】の類語は、「春曙」などです。
| 【春暁】2つの類語 | ||
| 1 | 春曙 (しゅんしょ・はるあけぼの) |
春の明け方(明るくなってきたころ) |
| 2 | 有明 (ありあけ) |
空にまだ月が残っているのに夜が明けること |
【春暁】と「春曙」の違い
【春暁】と「春曙」の違いは、明るさです。
【春暁】は春の明け方のまだ薄暗いころを指しますが、「春曙」は春の明け方の明るくなってきたころを指します。
| 【春暁】と「春曙」の違いは明るさ | ||
| 春暁 | 春の明け方(まだ薄暗いころ) | |
| 春曙 | 春の明け方(明るくなってきたころ) | |
【春暁】の中国語表現
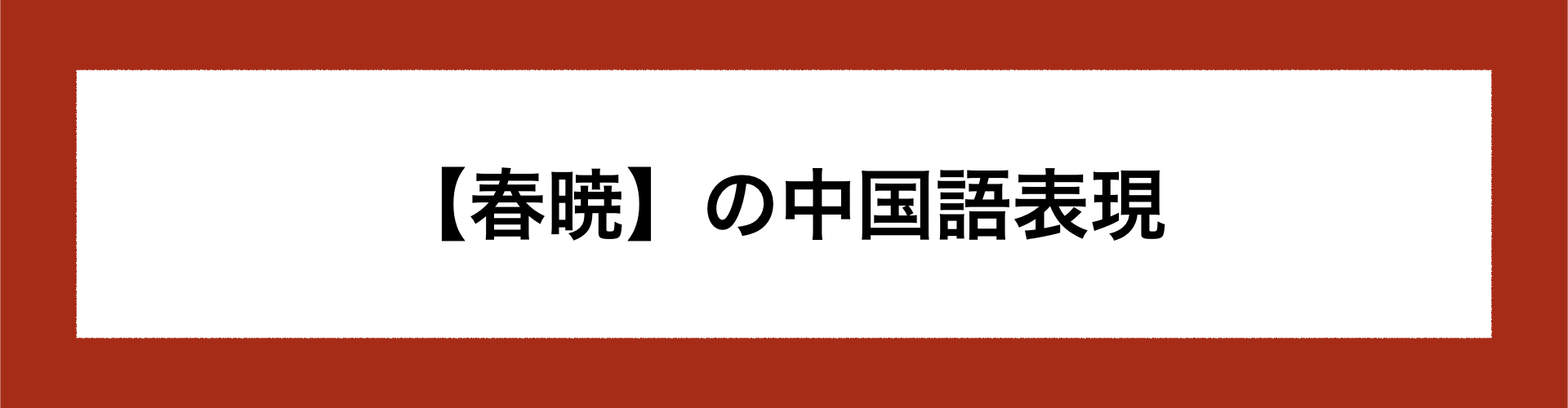

【春暁】の中国語表現は「春晓」です。
| 【春暁】の中国語表現 |
| 春晓(chūnxiǎo) |
【春暁】2つの英語表現


【春暁】の英語表現は、「spring dawn」などです。
| 【春暁】2つの英語表現 | ||
| 1 | spring dawn | |
| 春の夜明 | ||
| 2 | dawn of a spring day | |
| 春の日の夜明 | ||




