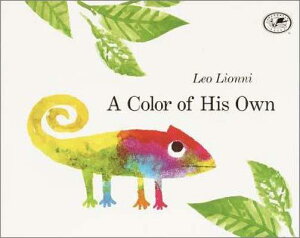| 【蛇足】の意味 |
| 余計なもの、必要ない無駄なもの |
| 【蛇足】の由来・語源 |
| 「戦国策」の「斉策上・閔王伝」に書かれている、蛇の絵に関するの故事。 調子に乗って蛇の足の絵を描いている間に、他の人にお酒を飲まれてしまった故事に由来する。 |
|
【蛇足】の6つの類語・類義語 |
||
| 余計 | 無駄 | 余分 |
| 過剰 | 不要 | 無用の長物 |

故事成語【蛇足】の意味とは
【蛇足】とは、このような意味です。
| 余計なもの、必要ない無駄なもの |
【蛇足】の読み方とは
「蛇足」は、一般的に「だそく」と読みます。
「じゃそく」と読まれることもあります。
【蛇足】の由来・語源は「戦国策」に書かれている中国の故事
由来・語源は「戦国策」に書かれている中国の故事
「蛇足」は、戦国時代の書物「戦国策」に書かれている故事に由来しています。
「戦国策」の「斉策上・閔王伝」に書かれている、蛇の絵に関するエピソードです。
楚国の将軍は、魏国を打ち破った後、斉国を打ち破ろうと兵を向けていました。
斉国の王は、遊説士の陳軫(ちんしん)に、楚国が兵を引き上げるよう説得することを依頼します。
楚国の将軍を説得する時に陳軫が使った例え話が、蛇の絵に関するエピソード(蛇足)なのです。
「戦国策」とは
「戦国策」とは、戦国時代の遊説士の策略などを、国別にまとめた33編から成る書物です。
元々「国策」「国事」「事語」「短長」「長書」「脩書」と呼ばれていた書物がありました。
これらを、前漢の時代に、学者・政治家である劉向(りゅうきょう)が一つにまとめました。
「戦国策」は「戦国時代」の名前の由来となった書物でもあります。
【蛇足】由来・語源となった故事の物語の内容
お酒を与えられた使用人たち
楚国の神官が、使用人たちに、お酒を与えました。
そのお酒は、大勢で飲むには少なく、一人で飲むには余る量でした。
使用人たちは相談し、地面に蛇の絵を書いて、一番に描き上げた人がお酒を飲むことにしようと決めました。
一番目に蛇の絵を描き上げた使用人
一番に蛇の絵を描き上げた使用人は、お酒を飲もうとしましたが、調子に乗ってこのようなことを言いました。
| 「私は蛇に足を書くことができる」 |
この使用人は、左手でお酒を持ちながら、右手で蛇の足を描き足します。
二番目に蛇の絵を描き上げた使用人
蛇の足が描き上がらないうちに、他の人が蛇の絵を描き上げこのように言いました。
| 「蛇には元々足がないのに、どうして足を描くことができるのか」 |
そして、そのままお酒を飲んでしまいました。
結局、一番に絵を書き上げた使用人は、お酒を飲むことができませんでした。
まとめ
陳軫は、楚国の将軍を説得する時に「蛇足」のたとえ話をしました。
「調子に乗って斉国に兵を向けると、破滅する」と。
この「蛇の絵」のエピソードから、余計なもの、必要ない無駄なもの意味で「蛇足」が使われるようになりました。
【蛇足】故事の白文・書き下し文・現代語訳
お酒を与えられた使用人たち
| 原文・白文 | 楚有祠者 |
| 書き下し文 | 楚に祠る者有り |
| 現代語訳 | 楚の国に、祭祀を司る人がいました |
| 原文・白文 | 賜其舎人卮酒 |
| 書き下し文 | 其の舎人に卮酒を賜ふ |
| 現代語訳 | あるとき、自分の使用人たちに大杯のお酒を与えました |
| 原文・白文 | 舎人相謂曰、 |
| 書き下し文 | 舎人相謂ひて曰はく、 |
| 現代語訳 | 使用人たちは相談して言いました、 |
使用人たちの相談
| 原文・白文 | 「数人飲之不足、一人飲之有余。 |
| 書き下し文 | 「数人之を飲まば足らず、一人之を飲まば余り有り。 |
| 現代語訳 | 数人でお酒を飲むには少なく、一人で飲むと余ってしまう。 |
| 原文・白文 | 請画地為蛇、先成者飲酒」 |
| 書き下し文 | 請ふ地に画きて蛇を為り、先づ成る者酒を飲まん。」と。 |
| 現代語訳 | 地面に蛇の絵を描いて、最初に描けた者がお酒を飲むことにしよう。」と。 |
一番目に蛇の絵を描き上げた使用人
| 原文・白文 | 一人蛇先成 |
| 書き下し文 | 一人の蛇先づ成る |
| 現代語訳 | 一人が蛇の絵を描き上げました |
| 原文・白文 | 引酒且飲之 |
| 書き下し文 | 酒を引きて且に之を飲まんとす |
| 現代語訳 | お酒を引き寄せて、今にも飲もうとしていました |
| 原文・白文 | 乃左手持卮、右手画蛇曰、 |
| 書き下し文 | 乃ち左手に卮を持ち、右手に蛇を画きて曰はく |
| 現代語訳 | 左手でお酒を持ち、右手で蛇を描きながら言いました |
| 原文・白文 | 「吾能為之足」 |
| 書き下し文 | 「吾能く之が足を為る」と |
| 現代語訳 | 「私は蛇の足を描くことができる」と |
二番目に蛇の絵を描き上げた使用人
| 原文・白文 | 未成、一人之蛇成 |
| 書き下し文 | 未だ成ざるに、一人の蛇成る |
| 現代語訳 | 蛇の足がまだ完成しないうちに、他の人の蛇の絵が描き上がりました |
| 原文・白文 | 奪其卮曰、 |
| 書き下し文 | 其の卮を奪ひて曰はく、 |
| 現代語訳 | (二番目に蛇の絵を描き上げた使用人は)お酒を奪って言いました |
| 原文・白文 | 「蛇固無足 |
| 書き下し文 | 「蛇固より足無し |
| 現代語訳 | 蛇には元々足がない |
| 原文・白文 | 子安能為之足」 |
| 書き下し文 | 子安くんぞ能く之が足を為らんや」と |
| 現代語訳 | あなたはどうやって蛇の足を描くのか、いや描けるはずがない」と |
最後にお酒を飲むことができたのは
| 原文・白文 | 遂飲其酒 |
| 書き下し文 | 遂に其の酒を飲む |
| 現代語訳 | その人(二番目に蛇の絵を描き上げた使用人)は、そのままお酒を飲みました |
| 原文・白文 | 為蛇足者、終亡其酒。 |
| 書き下し文 | 蛇の足を為る者、終に其の酒を亡へり |
| 現代語訳 | 蛇の足を描いた者は、とうとうお酒を飲み損ねてしまいました |
【蛇足】の使い方・例文
「蛇足」は「必要のない・無駄・余計」の他、謙遜や戒めの意味で使われることもあります。
その1(必要のない・無駄・余計)
| 例文1 | 進行予定を変更するなんて、蛇足でしかない |
| 例文2 | 昨日のセミナーは蛇足が多く、いまいちだった |
その2(謙遜)
| 例文1 | 蛇足ではありますが、私から意見を述べさせていただきます |
| 例文2 | 蛇足ですが、当社から新商品の紹介をさせていただきます |
その3(戒め)
| 例文1 | 彼らの計画は蛇足が多いので、再考した方がいいだろう |
| 例文2 | 君の説明は蛇足が多い。それでは先方に理解してもらえないだろう |
【蛇足】と由来・語源が同じことわざ(蛇を画きて足を添う)
「蛇足」と由来・語源が同じことわざに「蛇を画きて足を添う」があります。
同じ故事が由来となっていて、意味も全く同じです。
| 例文 | 先生の最後の話は、蛇を画きて足を添うだった |
【蛇足】の類語・類義語
その1(余計)
「余計」とはこのような意味です。
| ・物が余っていること、必要な数より多くあること ・邪魔になるのでない方がいい物、やらない方がいい事 |
「蛇足」には余計なものという意味があり、似た言葉と言えます。
その2(無駄)
「無駄」とはこのような意味です。
| 役に立たないこと |
「蛇足」には無駄なものという意味があり、似た言葉と言えます。
その3(余分)
「余分」とはこのような意味です。
| ・余った分、残り ・必要より多いこと |
「蛇足」には必要のない無駄なものという意味があり、似た言葉と言えます。
その4(過剰)
「過剰」とはこのような意味です。
| 一定数を超え、多すぎて余ること |
「蛇足」には余計なものという意味があり、似た言葉と言えます。
その5(不要)
「不要」とはこのような意味です。
| 必要でないこと |
「蛇足」には必要のない無駄なものという意味があり、似た言葉と言えます。
その6(無用の長物)
「無用の長物」とはこのような意味です。
| 役に立たず邪魔になるもの、無駄なもの |
「蛇足」には無駄なものという意味があり、似た言葉と言えます。
【蛇足】の英語表現
その1(make an unnecessary addition)
| 英語 | 日本語 |
| unnecessary | 不要 |
| addition | 追加 |
直訳すると「不要なものを追加する」となります。
「蛇足・蛇足を加える」の意味で使うことができます。
その2(a superfluity)
「superfluity」は「余分」という意味の単語です。
「蛇足」の意味で使うことができます。
その3(put a fifth wheel to the coach)
直訳すると「馬車に5つ目の車輪をつける」です。
馬車の車輪は4つなのに、5番目の車輪なので「余計」「余分」と言った意味で使われます。
「蛇足」の意味で使うことができます。
その4(redundant)
「redundant」は「余分・不要」という意味の単語です。
「蛇足」の意味で使うことができます。
【蛇足】の対義語・反対語
その1(画竜点睛・がりょうてんせい)
「画竜点睛」とはこのような意味です。
| ・物事を完成させるのに最も大事なこと ・なくてはならないこと |
「画竜点睛」の「なくてはならないこと」
「蛇足」の「必要のない無駄なもの」が反対の意味になります。
その2(必須)
「必須」とはこのような意味です。
| ・なくてはならないこと ・絶対に欠かせないもの |
「必須」の「なくてはならないこと」
「蛇足」の「必要のない無駄なもの」が反対の意味になります。
その3(不可欠)
「不可欠」とはこのような意味です。
| 欠かすことができないこと |
「不可欠」の「欠かすことができない」
「蛇足」の「必要のない、無駄な」が反対の意味になります。