【他山の石】は意味を間違いやすい言葉で、文化庁の調査によると、約2割の人は、間違った使い方をしているようです。
| 正しい意味 | 他人の誤った言動も、自分の成長の助けになる |
| 間違いやすい意味 | 他人の良い言動は、自分の行いの手本となる |
意味のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。


| 書き下し文 | 他山の石以て玉を攻むべし |
| 現代語訳 | よその山から出た、つまらない石であっても、自分の宝石を磨く砥石としては役に立つ |
この言葉から「他人の誤った言動も、自分の成長の役に立つ」という意味で【他山の石】が使われるようになりました。
由来・語源のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。
| 【他山の石】7つの類語・類義語 | |
| 反面教師 | 人の振り見て我が振り直せ |
| 人を以って鏡となす | 前車の覆るは後車の戒め |
| 殷鑑遠からず | 人こそ人の鏡 |
| 上手は下手の手本下手は上手の手本 | |

| 【他山の石】5つの反対語・対義語 | |
| 爪の垢を煎じて飲む | 朱に交われば赤くなる |
| 薫陶を受ける | 感化される |
| 門前の小僧習わす経を読む | |

| 【他山の石】4つの英語表現 | |
| failure be a lesson to you. | |
| learn a lesson from other’s mistakes. | |
| The fault of another is a good teacher. | |
| Learn wisdom by the follies of others. |

| 【他山の石】中国語表現 |
| 彼の失敗を他山の石としなさい。 |


【他山の石】の意味・読み方/わかりやすく解説
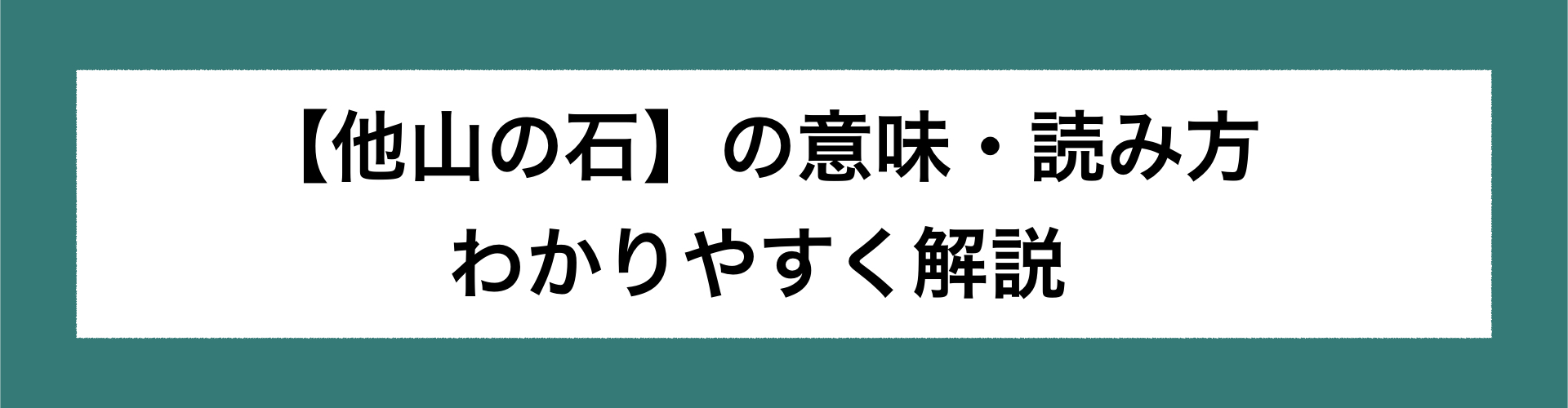
意味・読み方
- ❶正しい意味
- ❷間違いやすい意味
- ❸読み方

【他山の石】正しい意味/わかりやすく解説
【他山の石】の意味は「他人の誤った言動も、自分の成長の助けになる」です。
| 【他山の石】の意味 |
| ・他人の誤った言動も、自分の成長の助けになる ・他人の誤った言動も、自分の行いの参考になる |
「他人の失敗から学ぶ」「他人の誤りを自分の戒めとする」という良い意味で使われる言葉です。
【他山の石】間違いやすい意味
【他山の石】は間違いやすい言葉です。
本来の意味は「他人の誤った言動も、自分の成長の助けになる」です。
「他人の良い言行は自分の行いの手本となる」と勘違いされることがありますが、間違いです。
平成25年の文化庁の「国語に関する世論調査」では、約2割の人が間違った意味で理解しているとの結果が出ています。


2つが存在する状態を「言葉のゆれ」と言います。
「間違った使い方」の使用率が「正しい使い方」を上回った場合は、「間違った使い方」ではなく「言葉の変化」ととらえるのが自然なようです。
| 間違った使い方の使用率 > 正しい使い方の使用率 → 言葉の変化 |
参考:文化庁(言葉遣いに関すること)
参考:国立国語研究所
読み方
【他山の石】の読み方は、「たざんのいし」です。
【他山の石】由来・語源は石の故事

由来・語源
- ❶由来・語源は石の故事
- ❷「石の故事」とは
- ❸「詩経(しきょう)」とは

由来・語源は石の故事
【他山の石】の由来・語源は、石にまつわる故事です
中国最古の詩集である「詩経(しきょう)」に書かれている、石にまつわる言葉です。
「石の故事」とは
「詩経」の「小雅(しょうが)・鶴鳴(かくめい)」には、次のような言葉が書かれています。
| 原文・白文 | 它山之石 可以攻玉 |
| 書き下し文 | 他山の石以て玉を攻むべし |
| 読み仮名 | たざんのいしをもってたまをおさむべし |
| 現代語訳 | よその山から出た、つまらない石であっても、自分の宝石を磨く砥石としては役に立つ |
「よその山から出たつまらない石」→「他人の間違った言動」
「自分の宝石を磨く砥石としては役に立つ」→「自分の成長の助けとなる」
この言葉から「他人の誤った言動も、自分の成長の役に立つ」という意味で【他山の石】が使われるようになりました。
「詩経(しきょう)」とは
「詩経」は、周代前期(BC11世紀〜BC6世紀頃)に作られた中国最古の詩集です。
黄河流域で歌われた305首がまとめられています。
儒教の経典(五経)の1つとされています。
| 五経(儒教の経典) |
| ・詩経(しきょう) ・書経(しょきょう) ・易経(えききょう) ・春秋(しゅんじゅう) ・礼記(らいき) |
【他山の石】使い方・例文
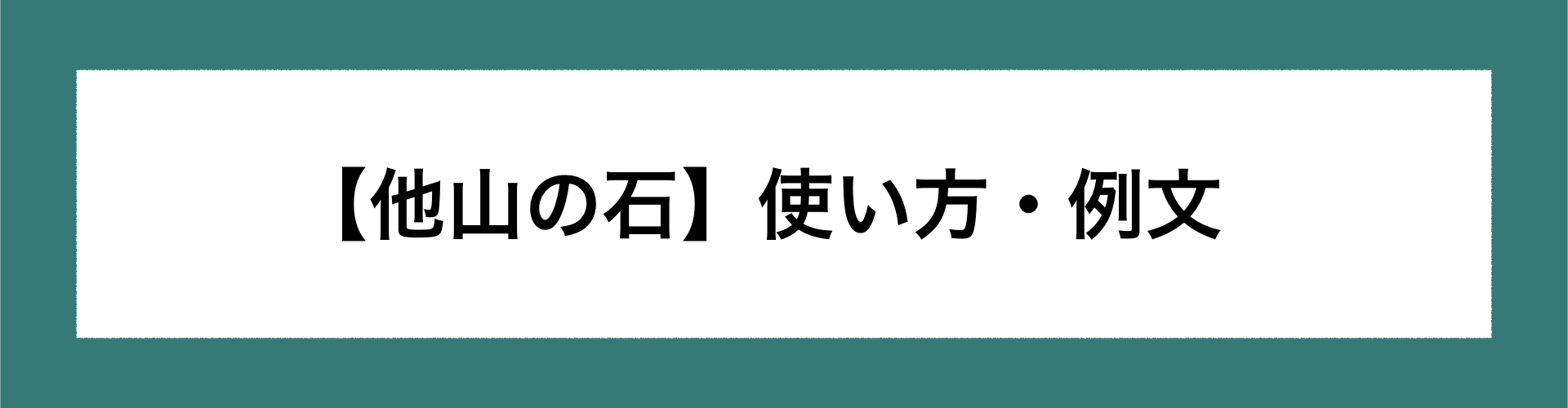
使い方・例文
- ❶正しい使い方
- ❷間違った使い方
- ❸例文

正しい使い方
【他山の石】は、「他人の誤った言動も、自分の成長の助けになる」という意味です。
「他人の失敗から学ぶ」「他人の誤りを自分の戒めとする」という良い意味で使われます。
ただし、「悪い例え」を指すときに使われる言葉なので、使う相手を選びます。
上司など目上の人に対しては使えません。
「他山の石となる」「他山の石とする」という言い回しで使われることが多いです。




間違った使い方「他山の石とせず」
「他山の石とせず」という使い方をされることがありますが、間違いです。
【他山の石】とは、「他人の誤った言動も、自分の成長の参考になる」という良い意味の言葉です。
他人事とせずに学ぶという意味が含まれているので、「せず」で否定すると、「他人の誤りを見ても、自分の行動を改める参考にはしない」」と悪い意味になってしまいます。
【他山の石】をそのまま使うのが正しいです。
【他山の石】と間違いやすい言葉「対岸の火事」
【他山の石】と間違いやすい言葉に「対岸の火事(たいがんのかじ)」があります。
「対岸の火事」の意味は、「他人には重大なことでも、自分には関係がなく何の苦痛もないこと」です。
| 「対岸の火事」の意味 |
| 他人には重大なことでも、自分には関係がなく何の苦痛もないこと |
【他山の石】と「対岸の火事」の違いは、「他人事とせずに学ぶ」という自分を戒める意味の有無です。
【他山の石】には自分を戒める意味が含まれますが、「対岸の火事」には含まれません。
そのため、「他山の石とせず」という使い方は間違いですが、「対岸の火事とせず」という使い方は間違いではありません。
| 正しい使い方 | 対岸の火事とせず |
| 間違った使い方 | 他山の石とせず |
例文
| 例文1 | 友達の失敗も、他山の石として役立てる。 |
| 例文2 | 〇〇社の事例は、他山の石となる出来事だ。 |
| 例文3 | 起業に失敗した人の話を聞いて、他山の石とすることが大切だ。 |
【他山の石】7つの類語・類義語
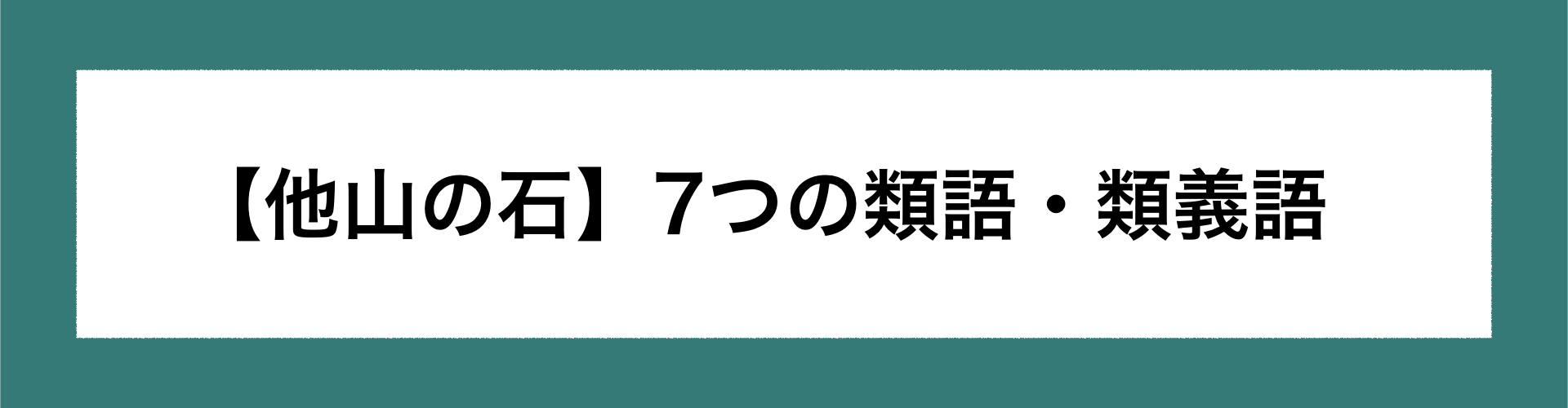

【他山の石】の類語・類義語は、「反面教師」などがあります。
| 【他山の石】7つの類語・類義語 | ||
| 1 | 反面教師 (はんめんきょうし) |
悪い手本となる人や事柄 |
| 2 | 人の振り見て我が振り直せ (ひとのふりみてわがふりなおせ) |
他人の行動を見て、良いところは見習い悪いところは改めること |
| 3 | 人を以って鏡となす (ひとをもってかがみとなす) |
他人の言動を手本に、自らを正していくこと |
| 4 | 前車の覆るは後車の戒め (ぜんしゃのくつがえるはこうしゃのいましめ) |
他人の失敗は、後から行くものの戒めとなること |
| 5 | 殷鑑遠からず (いんかんとおからず) |
戒めとなる失敗例は、身近にあること |
| 6 | 人こそ人の鏡 (ひとこそひとのかがみ) |
他人の言動は、自分の言動を正す良い手本であること |
| 7 | 上手は下手の手本下手は上手の手本 (じょうずは へたのてほん へたは じょうずのてほん) |
下手な者が上手な者を手本にしてまねるのは当然であるが、上手な者もまた下手な者の失敗や不手際などを参考にして上達するものだ |
【他山の石】5つの対義語・反対語
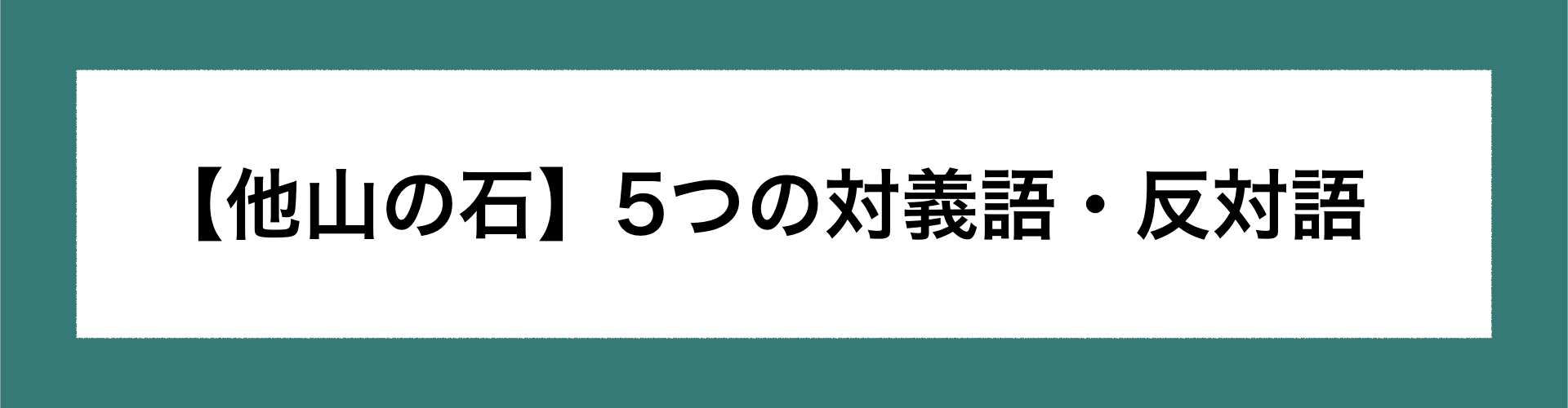

【他山の石】の対義語・反対語は、「爪の垢を煎じて飲む」などがあります。
| 【他山の石】5つの対義語・反対語 | ||
| 1 | 爪の垢を煎じて飲む (つめのあかをせんじてのむ) |
優れた人の爪の垢を薬として飲み、その人にあやかろうということ |
| 2 | 朱に交われば赤くなる (しゅにまじわればあかくなる) |
人は関わる人によって、前にも悪にもなるということ |
| 3 | 薫陶を受ける (くんとうをうける) |
人徳や品格のある人から影響を受け、人格が磨きあげられること |
| 4 | 感化される (かんかされる) |
人から影響を受け、自分の考えや行動が変化すること |
| 5 | 門前の小僧習わす経を読む (もんぜんのこぞうならわぬきょうをよむ) |
常に見聞きしていると、いつの間にかそれを学び知っていること |
【他山の石】4つの英語表現
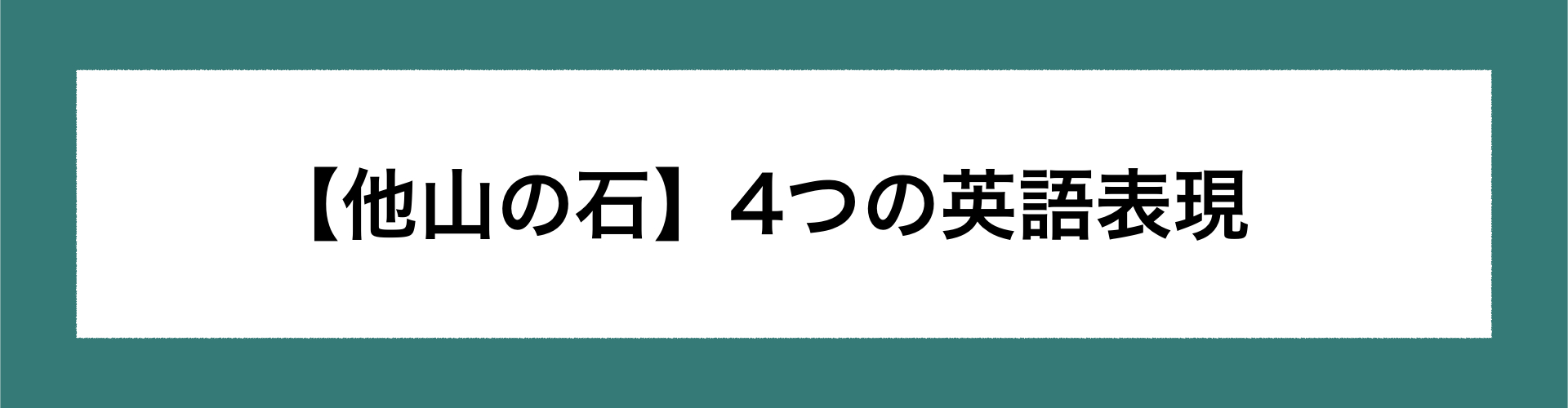

【他山の石】の英語表現は、「failure be a lesson to you.」などがあります。
| 【他山の石】2つの英語表現 | ||
| 1 | failure be a lesson to you. | |
| 失敗は教訓となる | ||
| 2 | learn a lesson from other’s mistakes. | |
| 他人の間違いから教訓を学ぶ/他山の石とする | ||
| 3 | The fault of another is a good teacher. | |
| 他山の石とする | ||
| 4 | Learn wisdom by the follies of others. | |
| 他の人の愚行から英知を学ぶ | ||
| Let his failure be a lesson to you. |
| 彼の失敗を他山の石としなさい。 |
【他山の石】中国語表現
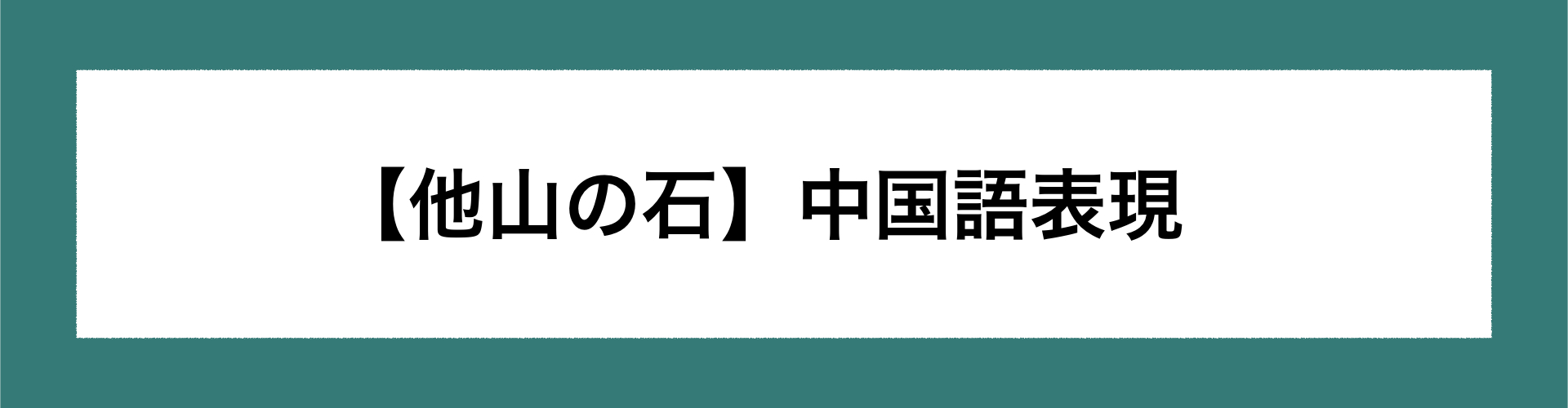
【他山の石】の中国語表現は、「他山之石」です。
| 【他山の石】中国語表現 |
| 他山之石(tāshānzhīshí) |
中国では、かなりポジティブなニュアンスで使われます。



