
中国の宋国のある農民が、兎が切り株にぶつかり、首の骨を追って死んでしまうのを見ました。
これは偶然の出来事でしたが、農民は、切り株の近くで待っていれば、また兎がぶつかって死ぬだろうと考えました。
翌日から、農民は畑仕事をせずに、毎日切り株を見張っていました。
しかし兎を取ることはできず、畑も荒れて作物も実らず、農民は国の笑いものになってしまいました。
このことから、「古いやり方にこだわって、融通がきかないこと」の意味で【守株】という言葉が使われるようになりました。
由来・語源のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。


知りたい項目をクリックして下さい。
| ① 故事成語【守株】の意味・読み方 |
| ②由来・語源 |
| ③漢文の現代語訳・書き下し文 |
| ④例文・使い方 |
| ⑤同じ意味の言葉/別表現 |
| ⑥4つの類義語 |
| ⑦反対語・対義語 |
| ⑧2つの英語表現 |
| 【守株】4つの同じ意味の言葉/別表現 | |
| 株守(しゅしゅ) | 守株待兎(しゅしゅたいと) |
| 株を守りて兎を待つ (かぶをまもりてうさぎをまつ) |
株を守る(くいぜをまもる) |

| 【守株】8つの類語 | |
| 旧套墨守 | 因循姑息 |
| 刻舟求剣 | 柳の下にいつも泥鰌はいない |

| 【守株】の反対語・対義語 | ||
| 1 | 吐故納新(とこのしん) | 古いものを捨て、新しいものを取り入れること |

| 【守株】2つの英語表現 | |
| 1 | lack of innovation |
| 2 | stupidity |


故事成語【守株】の意味・読み方
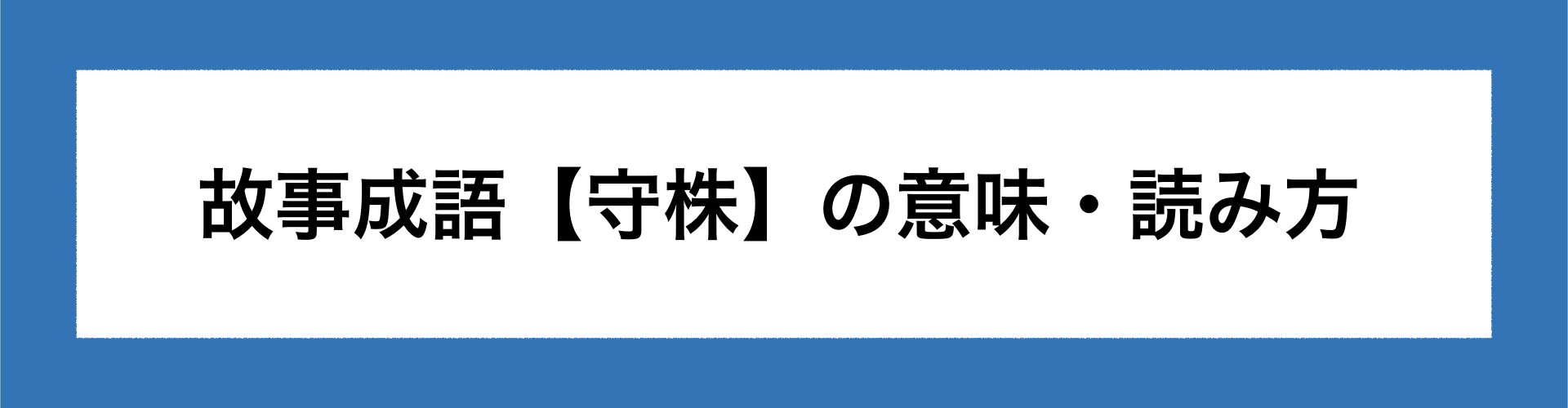
意味・読み方
- ❶【守株(しゅしゅ)】の意味
- ❷【守株】の読み方

【守株(しゅしゅ)】の意味
【守株】の意味は、古いやり方にこだわって、時代に合った対応をしないことです。
| 【守株】の意味 |
| 古いやり方にこだわって、時代に合った対応をしないこと |
【守株】は、「守株待兎(しゅしゅたいと)」の略語です。
【守株】の読み方
【守株】の読み方は、「しゅしゅ」です。
【守株】由来の兎の故事とは
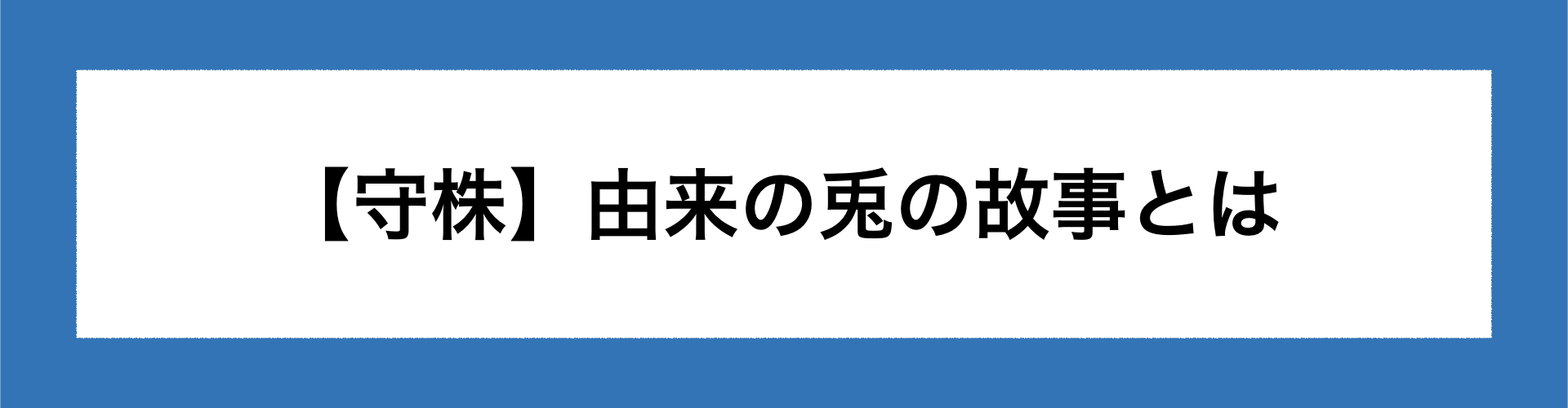
由来・語源
- ❶【守株】の由来は兎の故事
- ❷ 兎と農民の故事/エピソードの内容
- ❸「韓非子(かんぴし)」とは
- ❹「韓非(かんぴ)」とは

【守株】の由来は兎の故事
【守株】という言葉は、兎と農民の故事に由来します。
中国戦国時代の思想書「韓非子(かんぴし)」の「五蠹篇(ごと)」にかかれている、兎と農民のエピソードです。
兎と農民の故事/エピソードの内容
中国・春秋戦国時代に、宋の国に住んでいた農民のエピソードです。
農民は、兎が切り株にぶつかり、首の骨を追って死んでしまうのを見ました。
これは偶然の出来事でしたが、農民は、切り株の近くで待っていれば、また兎がぶつかって死ぬだろうと考えました。
翌日から、農民は畑仕事をせずに、毎日切り株を見張っていました。
しかし兎を取ることはできず、畑も荒れて作物も実らず、農民は国の笑いものになってしまいました。
このことから、「古いやり方にこだわって、融通がきかないこと」の意味で【守株】という言葉が使われるようになりました。
「韓非子(かんぴし)」とは
「韓非子」とは、韓非(かんぴ)によって書かれた、中国戦国時代の思想書です。
法治主義が政治の基礎であると説いたもので、全20巻、55編からなります。
「孤憤篇(こふん)」「五蠹篇(ごと)」の二編は始皇帝を感激させた書物と言われています。
始皇帝は、韓非に会えたら死んでもいいとまで言っていたようです。
「韓非(かんぴ)」とは
「韓非」とは、中国戦国時代の思想家・政治家です。
法治主義を説いた「法家」の代表的な人物で、「韓非子(かんぴし)」と呼ばれることもあったようです。
【守株/守株待兎】漢文の現代語訳・書き下し文
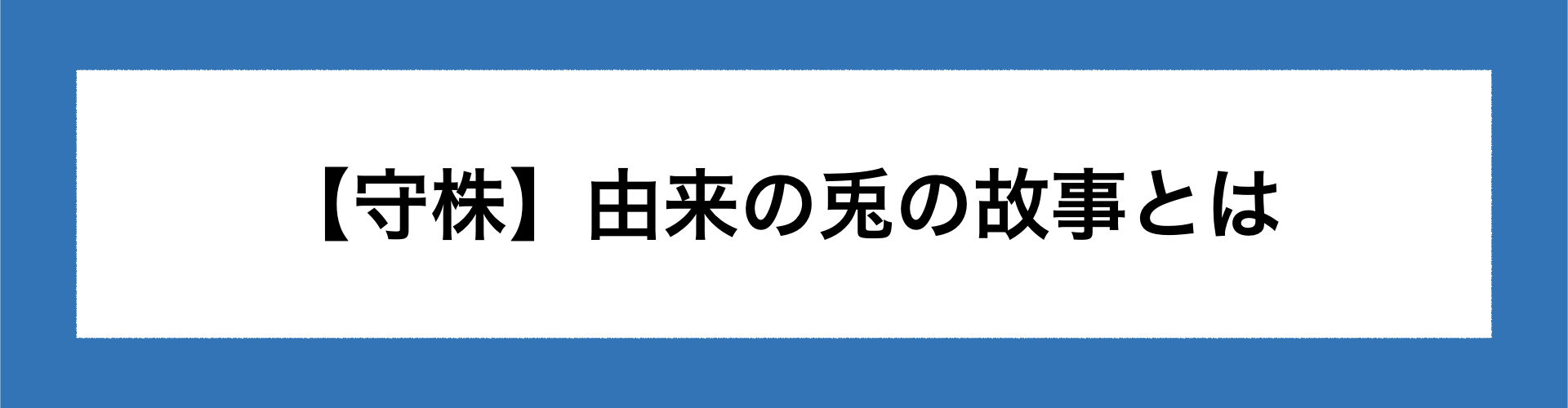

| 原文・白文 | 宋人有耕田者。 |
| 読み仮名 | そうひとに たをたがやすものあり。 |
| 書き下し文 | 宋人に田を耕す者有り。 |
| 現代語訳 | 宋国に、田んぼを耕している者がいました。 |
| 原文・白文 | 田中有株。 |
| 読み仮名 | でんちゅうに かぶあり。 |
| 書き下し文 | 田中に株有り。 |
| 現代語訳 | 田んぼの中に切り株があった。 |
| 原文・白文 | 兔走触株、折頸而死。 |
| 読み仮名 | うさぎはしりてかぶにふれ、くびをおりてしす。 |
| 書き下し文 | 兔走りて株に触れ、頸を折りて死す。 |
| 現代語訳 | うさぎが走って切り株にぶつかり、首を折って死んだ。 |
| 原文・白文 | 因釈其耒而守株、冀復得兔。 |
| 読み仮名 | よりてそのほこをすてて かぶをまもり、またうさぎをえんことを こいねがう。 |
| 書き下し文 | 因りて其の耒を釈てて株を守り、復た兔を得んことを冀ふ。 |
| 現代語訳 | その農民はすき(農具)を捨てて株を見張り、またうさぎが死ぬことを願った。 |
| 原文・白文 | 兔不可復得、而身為宋国笑。 |
| 読み仮名 | |
| 書き下し文 | 兔復た得べからずして、身は宋国の笑ひと為る。 |
| 現代語訳 | うさぎは二度とは手に入れることはできず、その人は宋の国中の笑い者となった。 |
【守株】の例文・使い方
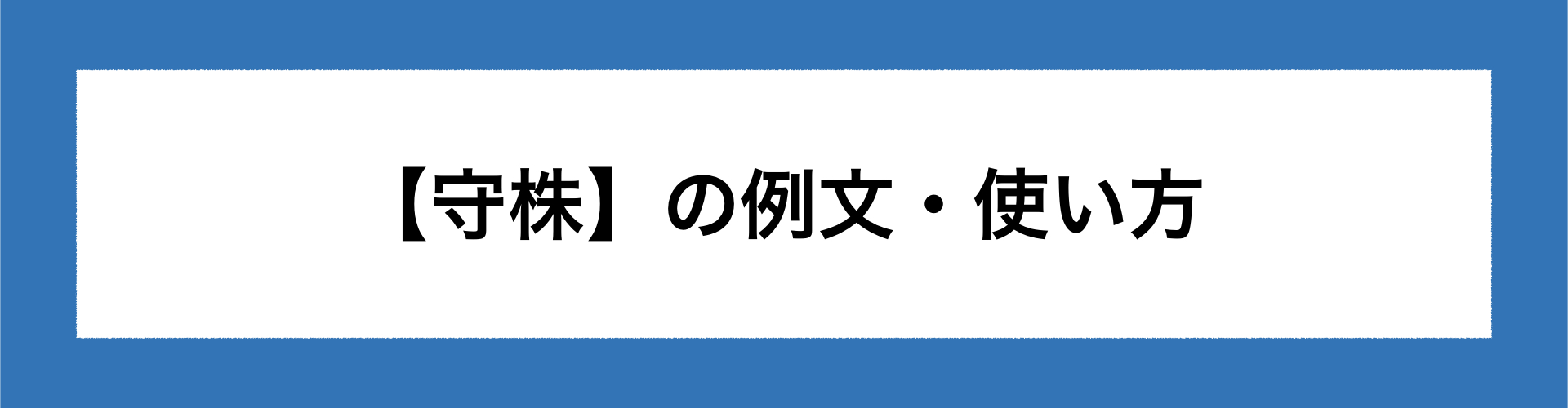
例文・使い方
- ❶例文
- ❷使い方

例文
【守株】の例文は、次のようになります。
| 例文1 | いつまでも守株な考えをしていると、時代に取り残されてしまう。 |
| 例文2 | 社長は守株な人だから、新しい事業を始めるのは難しいだろう。 |
| 例文3 | 田舎に規制すると、守株な人たちが多いなと感じる。 |
使い方




【守株】4つの同じ意味の言葉/別表現
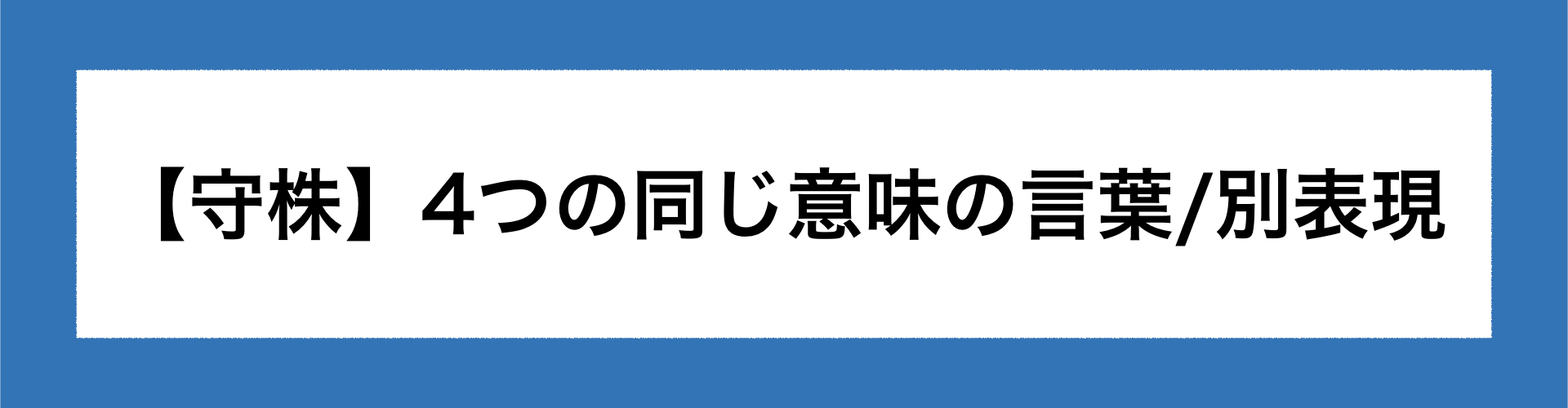

【守株】は、次のように表現することができます。
| 【守株】4つの同じ意味の言葉/別表現 | |
| 株守(しゅしゅ) | 守株待兎(しゅしゅたいと) |
| 株を守りて兎を待つ (かぶをまもりてうさぎをまつ) |
株を守る(くいぜをまもる) |
どれも同じ故事に由来しています。
【守株】4つの類義語
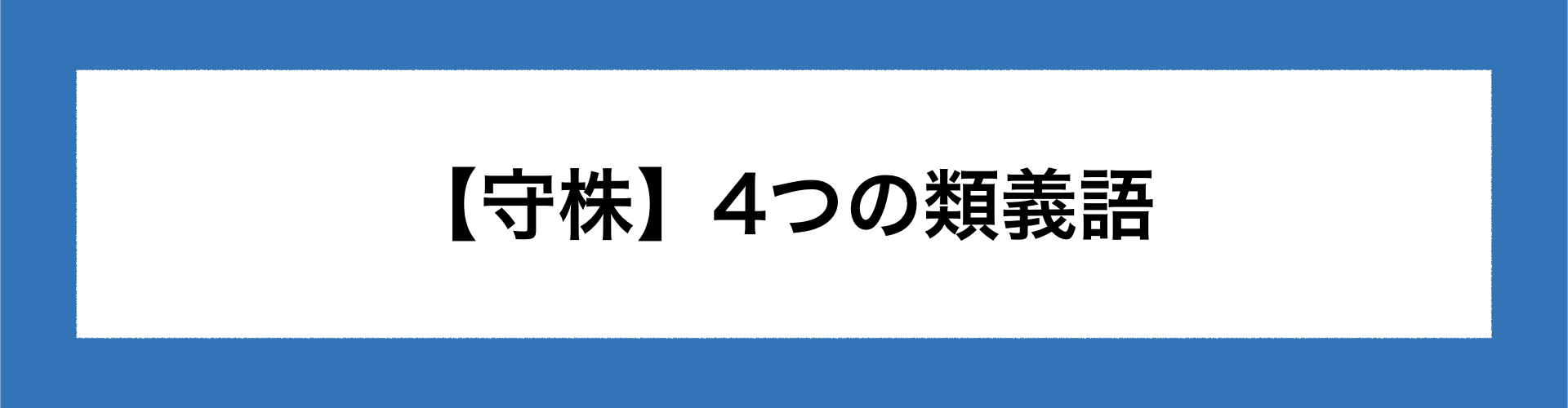

【守株】の類義語は、「旧套墨守(きゅうとうぼくしゅ)」などです。
| 【守株】8つの類語 | ||
| 1 | 旧套墨守 (きゅうとうぼくしゅ) |
古いしきたりや方法を固く守ること |
| 2 | 因循姑息 (いんじゅんこそく) |
古いしきたりや方法に固執して、その場しのぎでやり過ごすこと |
| 3 | 刻舟求剣 (こくしゅうきゅうけん) |
時代の変化に気づかず、いつまでも古い方法に固執すること |
| 4 | 柳の下にいつも泥鰌はいない (やなぎのしたにいつもどじょうはいない) |
一度上手くいったからといって、いつも同じように上手くいくわけではないということ |
【守株】の反対語・対義語
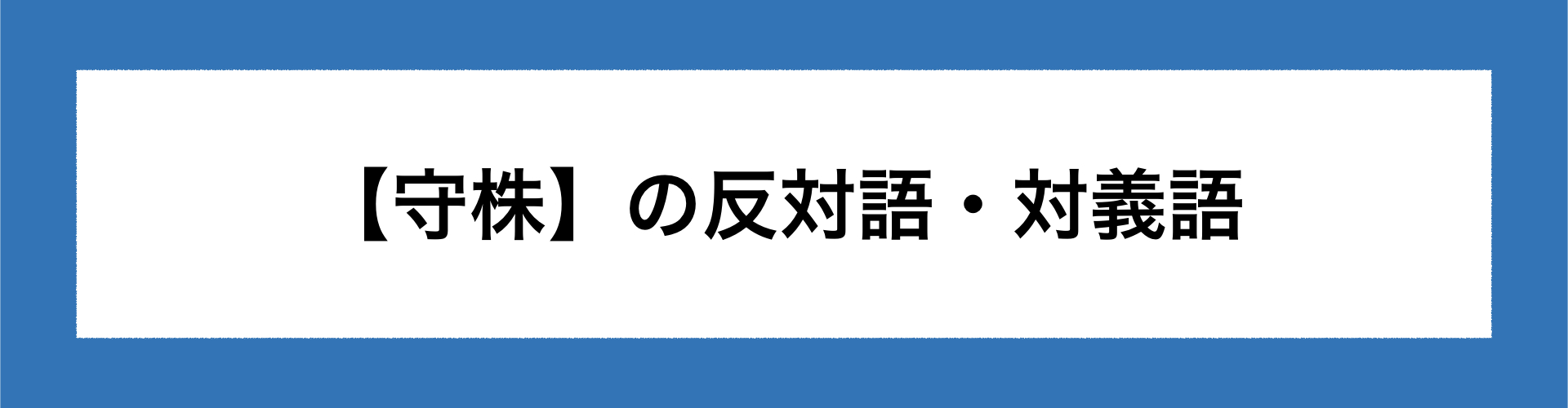

【守株】の反対語・対義語は、「吐故納新(とこのしん)」です。
| 【守株】の反対語・対義語 | ||
| 1 | 吐故納新(とこのしん) | 古いものを捨て、新しいものを取り入れること |
【守株】2つの英語表現
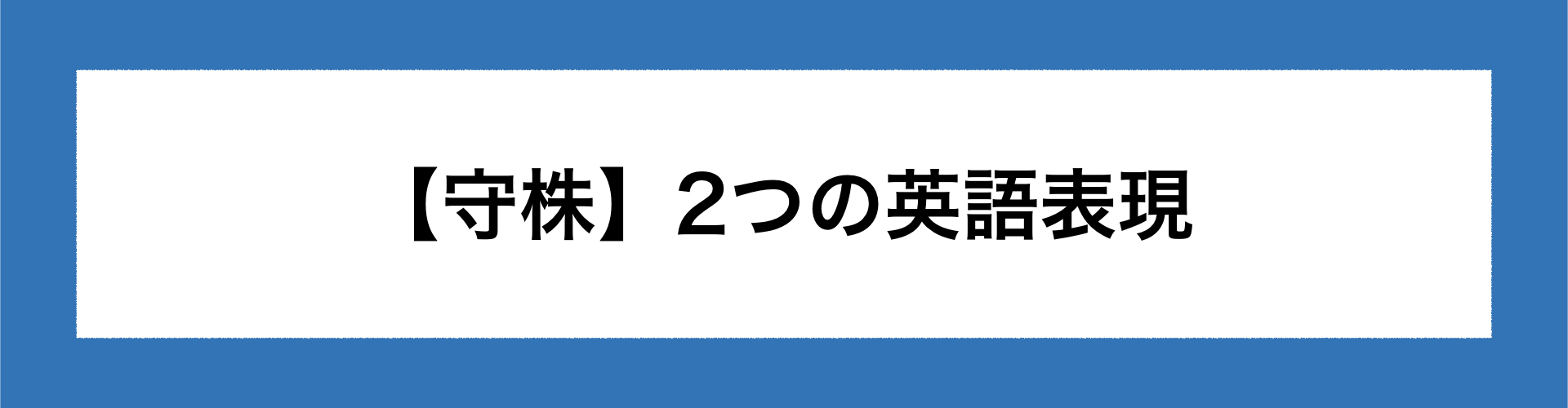

【守株】の英語表現は、「lack of innovation」などです。
| 【守株】2つの英語表現 | ||
| 1 | lack of innovation | |
| 革新の欠如 | ||
| 2 | stupidity | |
| ばか、愚かさ | ||
