

中国三国時代に、西晋国の武将である孫楚(そんそ)が言葉の言い間違えをしました。
しかし、孫楚は間違えを認めずに、屁理屈を並べて言い逃れをしました。
このことから、「負け惜しみを言うこと」「言い逃れをすること」を【漱石枕流】と言うようになりました。
文豪・夏目漱石の名前は、本名ではなくペンネームです。
漱石というペンネームは、この【漱石枕流】という言葉に由来します。
由来・語源のより詳しい情報はこちらをクリックして下さい。
知りたい項目をクリックして下さい。
| ①意味・読み方 |
| ②由来・語源 |
| ③漢文/原文の現代語訳・書き下し文 |
| ④【漱石枕流】に由来するペンネーム・言葉 |
| ⑤使い方・例文 |
| ⑥類語 |
| ⑦英語表現 |

| 【漱石枕流】6つの類語 | |
| 枕流漱石 | 指鹿為馬 |
| 我田引水 | こじつけ |
| 孫楚漱石 | 牽強付会 |

| 【漱石枕流】4つの英語表現 | |
| 1 | be too proud to 〜 |
| 2 | sour grapes |
| 3 | obstinacy |
| 4 | sore loser who stubbornly refuses to admit being wrong |


【漱石枕流】意味・読み方
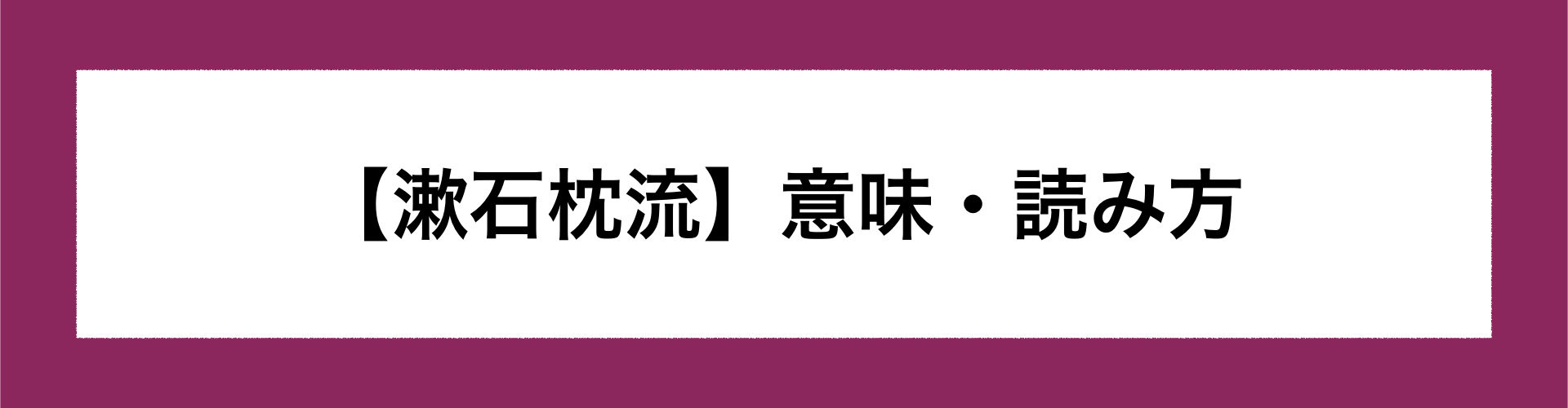
意味・読み方
- ❶【漱石枕流】の意味
- ❷「漱石」の意味
- ❸【漱石枕流】の読み方

【漱石枕流】の意味
【漱石枕流】の意味は、「負けず嫌いで、負け惜しみの強いこと」です。
| 【漱石枕流】の意味 |
| ・負けず嫌いで、負け惜しみの強いこと ・自分の失敗を認めずに、屁理屈を並べて言い逃れをすること |
「漱石」の意味
「漱石」の意味は、「負け惜しみ、頑固者」です。
| 「漱石」の意味 |
| ・負け惜しみ ・頑固者 |
【漱石枕流】の読み方
【漱石枕流】の読み方は、「そうせきちんりゅう」です。
| 【漱石枕流】の読み方 |
| そうせきちんりゅう |
【漱石枕流】由来・語源

由来・語源
- ❶【漱石枕流】語源は「負けず嫌いの武将の故事」に由来
- ❷負けず嫌いの武将の故事/エピソードの内容
- ❸「世説新語(せせつしんご)」とは
- ❹ 「晋書(しんじょ)」とは

【漱石枕流】語源は「負けず嫌いの武将の故事」に由来
【漱石枕流】という言葉は、中国の負けず嫌いの武将の故事に由来しています。
中国南北朝時代の「世説新語(せせつしんご)」や、唐時代の「晋書(しんじょ)」に書かれているエピソードです。
負けず嫌いの武将の故事/エピソードの内容
西晋国(中国三国時代)の武将である孫楚(そんそ)にまつわるエピソードです。
孫楚は、早めに隠居して、山奥で自由に生活したいと考えていました。
この考えを、友人の王武子(おうぶし)に伝えたところ、次のように言葉を言い間違えてしまいました。
| 言葉 | 意味 | |
| 正しい言葉 | 枕石漱流 (ちんせきそうりゅう) |
石を枕に寝て、川の流れでうがいをする生活 (世間から離れ、山奥で自由な生活をする) |
| 間違えた言葉 | 漱石枕流 (そうせきちんりゅう) |
石でうがいをし、川の流れを枕に寝る |
王武子に間違ったことを指摘されますが、孫楚は、「石でうがいをするのは歯を強くするため、流れを枕にするのは耳を洗うため」と負け惜しみを言い、間違いを認めませんでした。
このことから、「負け惜しみを言うこと」「言い逃れをすること」を【漱石枕流】と言うようになりました。
【漱石枕流】は、間違えから生まれた言葉だったのです。
「世説新語(せせつしんご)」とは
「世説新語」は、中国の南北朝時代に宋国の王「劉義慶(りゅう ぎけい)」がまとめた逸話集です。
後漢末から東晋までの著名人の逸話が、文学・政治など36のジャンルにまとめられています。
事実とは言い難い、フィクションな逸話も含まれているようです。
「晋書(しんじょ)」とは
「晋書(しんじょ)」とは、中国・晋時代に書かれた歴史書です。
中国王朝の正史である「二十四史」の1つで、晋の他、後漢や三国時代についても記述があります。
帝紀(10巻)、志(20巻)、列伝(70巻)、載記(30巻)の全130巻から成ります。
【漱石枕流】漢文/原文の現代語訳・書き下し文
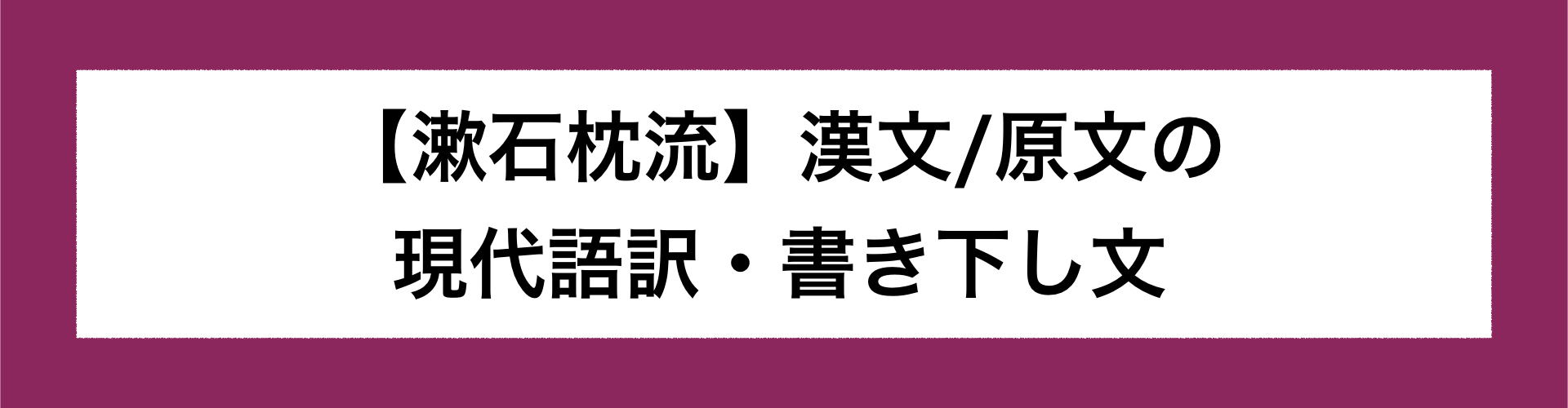

| 原文・白文 | 孫子荊、年少時欲隠。 |
| 読み仮名 | そんしけい、 としわかきとき かくれんとほっす。 |
| 書き下し文 | 孫子荊、年少き時、隠れんと欲す。 |
| 現代語訳 | 孫子荊は若い時、俗世間を離れて隠居生活を送りたいと思っていた。 |
| 原文・白文 | 語王武子、当枕石漱流、 |
| 読み仮名 | おうぶしにかたるに、 、まさにいしにまくらし ながれに くちすすがんとすべきに、 |
| 書き下し文 | 王武子に語るに、当に石に枕し流れに漱がんとすべきに、 |
| 現代語訳 | 友人の王武子と話していて、「石を枕に、川の流れでうがいをするつもりだ。」と言うべきところを、 |
| 原文・白文 | 誤曰、「漱石枕流。」 |
| 読み仮名 | あやまりていわく、 いしにくちすすぎ ながれにまくらす。」と。 |
| 書き下し文 | 誤りて曰はく、 「石に漱ぎ流れに枕す。」 |
| 現代語訳 | 間違って 「石でうがいをし、川の流れを枕に寝る。」と言ってしまった。 |
| 原文・白文 | 王曰、「流可枕、石可漱乎。」 |
| 読み仮名 | おういわく、 「ながれは まくらすべく、 いしはくちすすぐべきか」と。 |
| 書き下し文 | 王曰はく、「流れは枕すべく、 石は漱ぐべきか。」と。 |
| 現代語訳 | 王武子は、「川の流れを枕にし、石でうがいをすることが できるのだろうか。」と言った。 |
| 原文・白文 | 孫曰、「所以枕流、欲洗其耳。 |
| 読み仮名 | そんいわく、「ながれに まくらするゆえんは、 そのみみをあらわんと ほっすればなり。 |
| 書き下し文 | 孫曰はく、「流れに枕する所以は、其の耳を洗はんと欲すればなり。 |
| 現代語訳 | 孫が言った 「川の流れを枕にする理由は、耳を洗うためだ、 |
| 原文・白文 | 所以漱石、欲礪其歯。」 |
| 読み仮名 | いしに くちすすぐゆえんは、 そのはを みがかんとほっすればなり。」と。 |
| 書き下し文 | 石に漱ぐ所以は、其の歯を礪かんと欲すればなり。」と。 |
| 現代語訳 | 石でうがいをする理由は、歯を磨くためだ。」と。 |
【漱石枕流】に由来するペンネーム・言葉
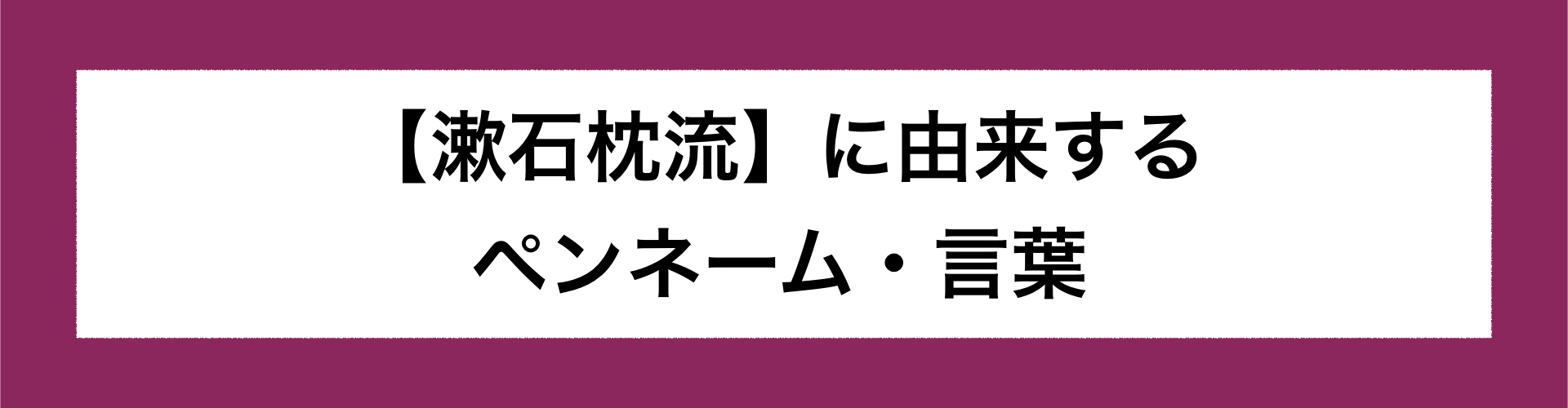
【漱石枕流】に由来するペンネーム・言葉
- ❶夏目漱石の名前の由来は【漱石枕流】
- ❷「流石(さすが)」の語源は【漱石枕流】

夏目漱石の名前の由来は【漱石枕流】
明治時代に活躍した文豪「夏目漱石(なつめそうせき)」の名前は、【漱石枕流】に由来します。
夏目漱石は、自分のことを変わり者だと思っていました。
夏目漱石が、【漱石枕流】の「負けず嫌い」「偏屈者」という意味を気に入って、自分のペンネームにしたそうです。
元々「漱石」は、友人で俳人の正岡子規のペンネームの一つだったのですが、譲ってもらったそうです。
| 夏目漱石(なつめそうせき) | |
| 本名 | 夏目金之助(なつめきんのすけ) |
| 出身 | 江戸牛込馬場下横町 (うしごめばばしたよこまち) (現在の新宿区喜久井町(きくいちょう)) |
| 有名作品 | 「こころ」「吾輩は猫である」「坊っちゃん」「文鳥・夢十夜」「三四郎 」「それから」「明暗」 |
「流石(さすが)」の語源は【漱石枕流】
「流石(さすが)」は、期待通りの結果を残した人への感心する気持ちを表す言葉です。
「流石(さすが)」の語源は【漱石枕流】に由来します。
孫楚(そんそ)のように、屁理屈を並べて言い返せるのは、「さすが!」頭が良いからです。
【漱石枕流】から漢字をとり、「流石(さすが)」という字が当てられました。
【漱石枕流】使い方・例文
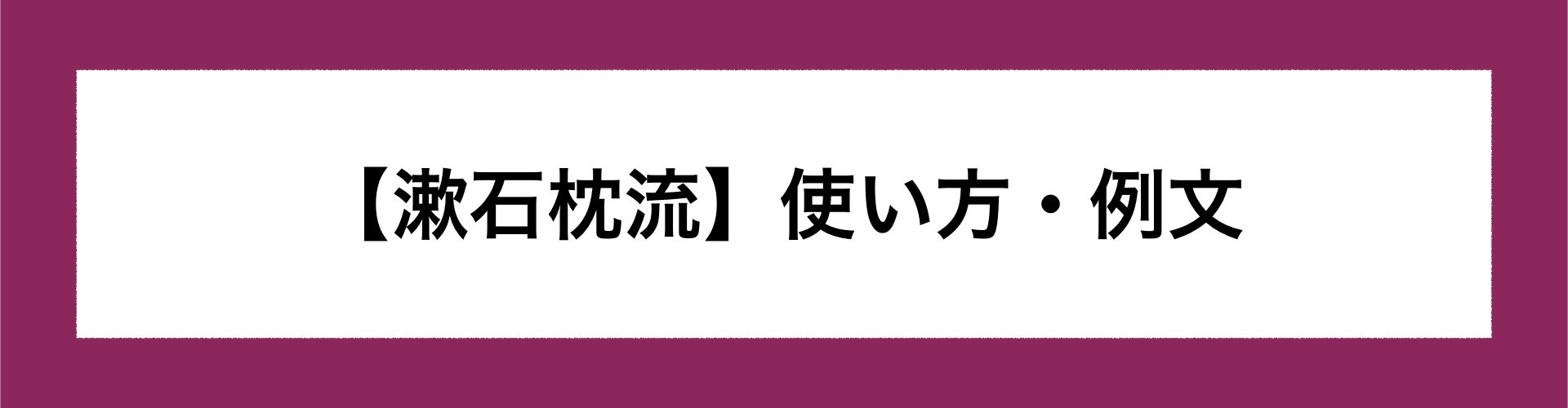
使い方・例文
- ❶使い方
- ❷例文

使い方
【漱石枕流】の使い方は、次のようになります。




例文
【漱石枕流】の例文は、次のようになります。
| 例文1 | 彼の言っていることは漱石枕流で、内容がめちゃくちゃだ。 |
| 例文2 | 彼女はまさに漱石枕流だ。あの言い訳は困ったものだ。 |
| 例文3 | 漱石枕流ばかりしていると、周りの人がストレスを感じてしまうよ。 |
【漱石枕流】6つの類語
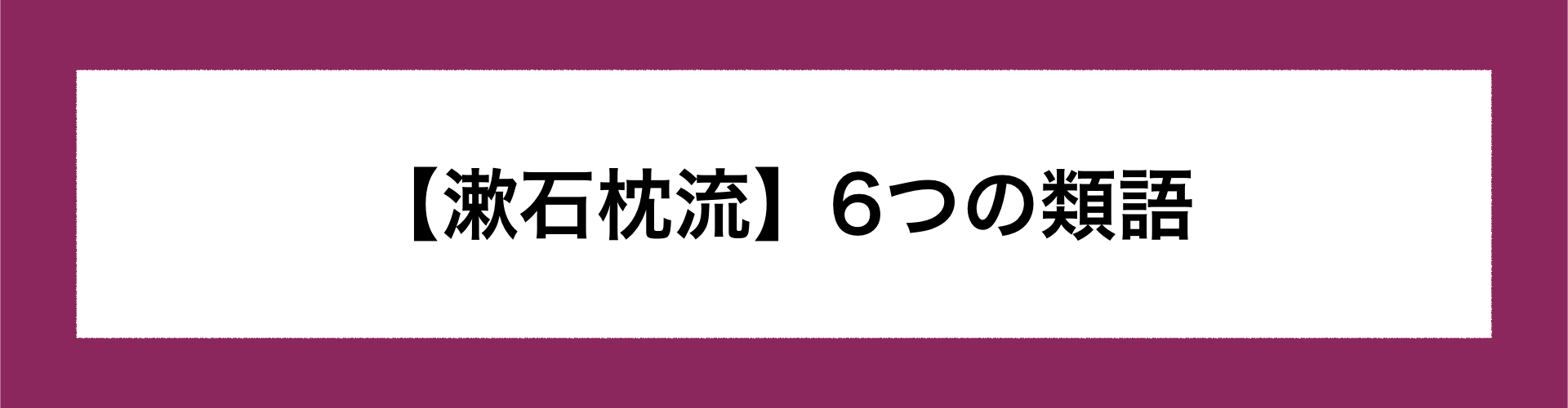

【漱石枕流】の類語は、「指鹿為馬」などです。
| 【漱石枕流】6つの類語 | ||
| 1 | 枕流漱石 (ちんりゅうそうせき) |
・負けず嫌いで、負け惜しみの強いこと ・自分の失敗を認めずに、屁理屈を並べて言い逃れをすること |
| 2 | 指鹿為馬 (しろくいば) |
間違いを認めず無理に押し通すこと |
| 3 | 我田引水 (がでんいんすい) |
自分に都合のいいように考えたり、行動したりすること |
| 4 | こじつけ | 本来は関係ない物事を、無理に関連付けること |
| 5 | 孫楚漱石 (そんそそうせき) |
自身の失敗や負けを認めようとしないこと |
| 6 | 牽強付会 (けんきょうふかい) |
自分に都合のいいように、むりにこじつけること |
【漱石枕流】4つの英語表現
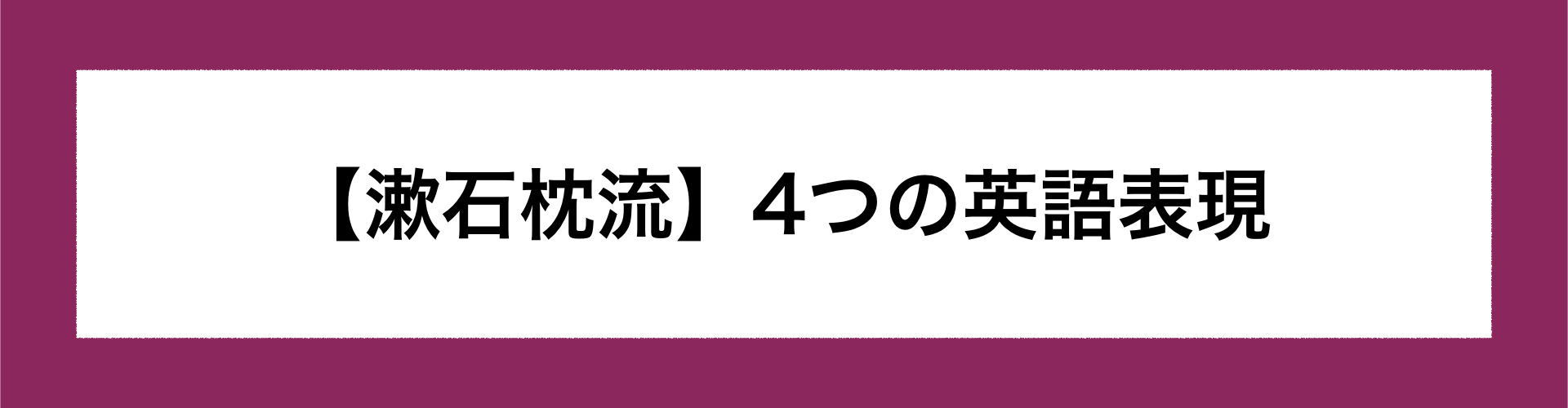

【漱石枕流】の英語表現は、「be too proud to 〜」などです。
| 【漱石枕流】4つの英語表現 | ||
| 1 | be too proud to 〜 | |
| 〜するのはプライドが許さない | ||
| 2 | sour grapes | |
| 負け惜しみ | ||
| 3 | obstinacy | |
| 頑固、強情 | ||
| 4 | sore loser who stubbornly refuses to admit being wrong | |
| 頑固に自分が間違っていることを認めようとしない負けず嫌いの人 | ||
